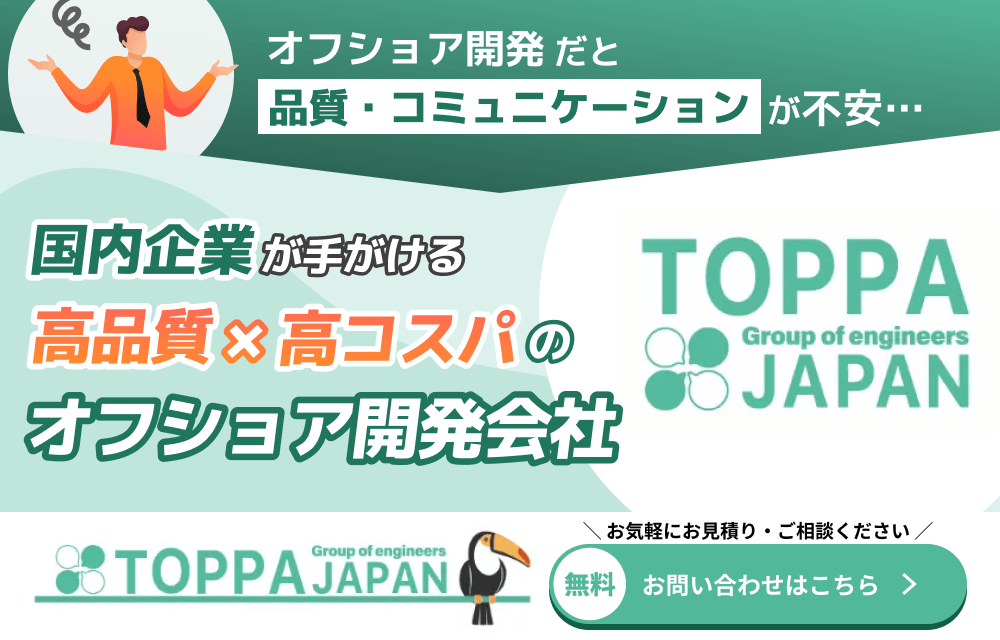システム改修は、今ある資産を活かして業務課題を解決する有効な手段ですが、進め方を間違えると予算超過やトラブルの原因にもなりかねません。
本記事では、システム改修の基本的な意味から、類似用語との違い、改修を検討すべき5つのタイミング、費用の相場とコストを抑えるコツを解説します。
さらに、失敗しないための具体的な進め方5ステップや、おすすめの開発会社も紹介。
この記事を読めば、システム改修の全体像を掴み、ベンダーへの的確な依頼や社内調整をスムーズに進められるようになります。
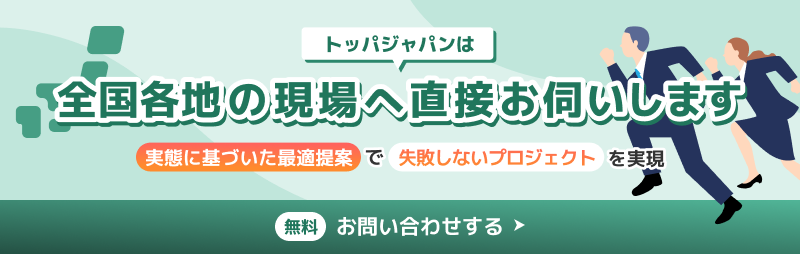
システム改修とは?
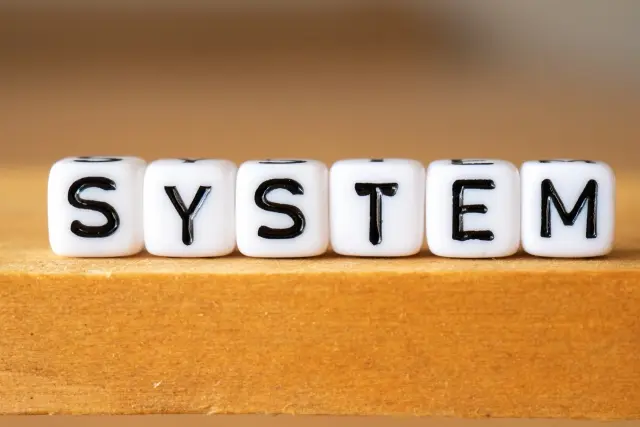
システム改修とは、現在使用しているシステムを土台に、機能の追加や改善を施すことです。
ゼロから作り直すのに比べて、費用や期間を抑えながら業務上の課題を解決できます。
ここでは、混同されがちな開発・保守・更改との違いを解説します。
システム開発・保守・更改(リプレイス)との違い
システム改修と類似する用語に、開発・保守・更改(リプレイス)があります。
これらは目的や規模、費用が異なるため、依頼する前に正しく理解しておく必要があります。
それぞれの主な違いは以下のとおりです。
| 用語 | 目的 | コスト | 期間 |
| システム改修 | 既存システムの機能追加・改善 | 低~中 | 短~中 |
| 新規開発 | 新しいシステムをゼロから構築 | 高 | 長 |
| 保守 | システムの安定稼働と維持管理 | 低 | (長期に渡り継続) |
| 更改(リプレイス) | 老朽化したシステムや基盤の入れ替え・刷新 | 高 | 長 |
自社の課題が、今あるシステムの基盤を活かして解決できるものか、あるいはシステム全体の刷新が必要なのかを見極めるのが最初のステップです。
これらの違いを把握しておけば、システム会社への相談や見積もりの依頼もスムーズに進められるでしょう。
なぜシステム改修は必要なのか?検討すべき5つのタイミング
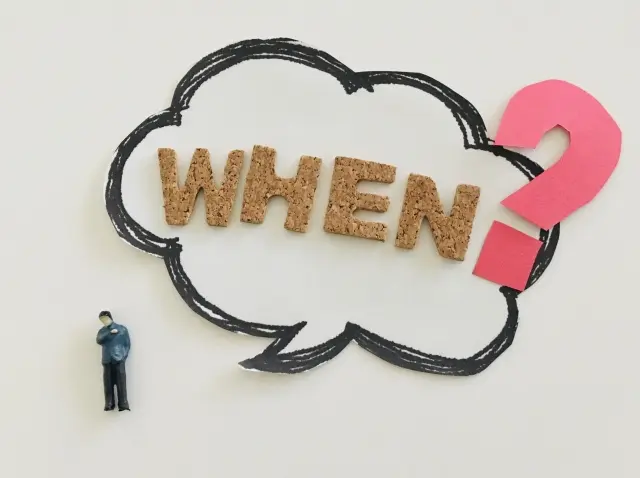
システム改修は、ビジネスの変化に対応し、システムの価値を維持・向上させるために必要です。
放置すると業務効率の低下やセキュリティ上のリスクにつながる可能性があります。
ここでは、システム改修を検討すべき代表的な5つのタイミングを解説します。
- 不具合(バグ)の修正
- 業務効率化のための機能改善・UI/UX向上
- 事業拡大や変更に伴う機能追加
- 法改正や制度変更への対応
- OSサポート終了に伴うセキュリティ強化
自社のシステムがこれらの状況に当てはまらないか、確認してみましょう。
①不具合(バグ)の修正
システムに発生する不具合(バグ)の修正は、改修を検討する代表的なタイミングです。
データの不整合やシステムが頻繁に停止する状態は、日々の業務を滞らせる直接的な原因になります。
「特定の操作でエラーが起きる」「処理に時間がかかりすぎる」といった問題は、従業員の生産性を下げてしまうでしょう。
軽微な不具合でも、放置すれば大きなトラブルに発展する可能性があります。
安定した業務環境を維持するために、問題が発覚した際は迅速な原因究明と改修が求められます。
②業務効率化のための機能改善・UI/UX向上
業務効率化を目指す機能改善やUI/UX(画面の使いやすさ)の向上も、システム改修の動機になります。
システム導入から時間が経つと、業務内容とシステムの機能が合わなくなる場合があるからです。
【現場から挙がる声の例】
- 操作手順が多くて面倒
- 画面のどこに何があるかわかりにくい
- 手入力の項目が多く、ミスが起きやすい
- 複数のシステムに同じ情報を入力している
上記のような声が聞こえてきたら、改修を検討するサインです。
画面レイアウトの見直しや入力補助機能の追加など、日々の業務に即した改修によって、作業時間は短縮され生産性の改善が見込めるでしょう。
③事業拡大や変更に伴う機能追加
事業の成長や方針転換に合わせて、システムにも新しい機能の追加が求められます。
ビジネスが変化しているにもかかわらずシステムが古いままでは、業務の実態と合わなくなり、手作業での対応が増えてしまいます。
| 事業変化の例 | 求められるシステム対応の例 |
| 新しい拠点や店舗の開設 | 在庫や売上を一元管理する機能 |
| 新商品・サービスの開始 | 新しい商品マスタや料金体系の登録機能 |
| 海外への事業展開 | 多言語・多通貨に対応する機能 |
ビジネスの成長に応じてシステムを拡張していくことで、事業のスピードを落とさずに済みます。
将来の事業計画を見据え、システムの拡張性を考慮した改修計画を立てましょう。
④法改正や制度変更への対応
法改正や業界の制度変更も、システム改修が必要になるタイミングです。
税率の変更や新たな法規制に対応できていないシステムを使い続けると、法令違反となり企業の信頼を損なうリスクがあります。
例えば、近年ではインボイス制度や電子帳簿保存法への対応が多くの企業で必要になりました。
法改正の情報は、施行されるかなり前から告知される場合がほとんどです。
関連省庁の発表などを定期的に確認し、余裕をもったスケジュールで改修計画を立てましょう。
⑤OSサポート終了に伴うセキュリティ強化
システムの基盤となるOSやミドルウェアのサポート終了は、セキュリティ強化を目的とした改修のタイミングといえます。
メーカーの公式サポートが終了すると、新たな脆弱性が発見されても修正プログラムが提供されません。
【サポート終了後に放置するリスク】
- ウイルス感染の危険性が高まる
- 不正アクセスによる情報漏洩
- サイバー攻撃の標的になりやすい
- 関連する他のシステムへの悪影響
上記のようなセキュリティリスクを抱えたままシステムを運用するのは危険です。
OSやミドルウェアのサポート期間をあらかじめ把握し、計画的にバージョンアップや新しい環境への移行を進めることで、企業の機密情報を安全に守れます。
システム改修の費用相場とコストを抑えるポイント

システム改修を進めるうえで、費用は最も気になる点ではないでしょうか。
予算を確保するためにも、費用の内訳や相場感を事前に把握しておく必要があります。
ここでは、改修費用の内訳と料金目安から、コストが高騰しやすいケース、費用を抑えるための具体的なコツまでを解説します。
費用の内訳と規模別の料金目安
システム改修の費用は、主に「何に」「どれくらいの工数をかけるか」で決まります。
まず、費用の内訳と、改修規模に応じた料金の目安を把握しておきましょう。
【費用の主な内訳】
| 項目 | 説明 |
| 要件定義・設計費 | 改修の目的や範囲を定め、具体的な仕様を設計するための費用 |
| 開発費 | 設計書に基づき、プログラミングや機能追加を行うための費用 |
| テスト費 | 改修した箇所が問題なく動作するかを検証するための費用 |
| 運用サポート費 | リリース後の問い合わせ対応や保守管理のための費用 |
【規模別の料金目安】
| 改修規模 | 内容の例 | 料金目安 |
| 小規模 | 画面の軽微な修正、単一機能のバグ修正 | 50万円~200万円 |
| 中規模 | 複数の機能追加、UI/UXの改善 | 300万円~800万円 |
| 大規模 | システム全体の設計変更、基盤の刷新 | 1,000万円以上 |
これらの金額はあくまで目安です。
改修内容の複雑さやシステムの現状によって費用は変動するため具体的な数字を提示することが難しく、システム改修の具体的内容や規模を確認してから算出する企業がほとんどです。
多くの場合、システム改修費用は、「人月単価×人数×月数」で算出されるため、複数の開発会社から見積もりを取り、内容を比較検討しましょう。
コストが高騰しやすいケースとは
システム改修では、状況によって費用が想定よりも高騰しやすくなります。
特に、改修したい内容が曖昧なままプロジェクトを進めてしまうと、後から仕様変更や追加要望が頻発し、費用がかさむ原因になります。
「とりあえず使いやすくしてほしい」といった抽象的な依頼は、認識のズレを生みやすいため注意が必要です。
また、誰も詳細な仕様を把握していない古いシステム(レガシーシステム)の改修も、調査に時間がかかるため高額になりがちです。
改修費用を抑えるコツ
改修費用を適切に管理し、コストを抑えるためには、計画段階での工夫が求められます。
【改修費用を抑えるためのポイント】
- 改修の目的と範囲を明確にする
- 優先順位をつけて段階的に改修を進める
- 自社で対応できる部分は内製化を検討する
- 既存のシステムや機能を可能な限り活用する
- クラウドサービスやオープンソースの利用を検討する
- 実績が豊富で信頼できる開発会社を選ぶ
すべてを一度に実施するのではなく、できるところから取り入れる姿勢がコスト削減につながります。
特に、改修の目的と範囲を明確にする「要件定義」は、その後の工程の土台となるため、時間をかけて丁寧に進めましょう。
失敗しないシステム改修の具体的な流れと進め方5ステップ

システム改修を成功させるためには、計画的な進行が不可欠です。
思い付きで進めると、手戻りや追加費用が発生しやすくなります。
ここでは、改修プロジェクトを円滑に進めるための具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。
- Step1:ヒアリングと現状分析
- Step2:要件定義(改修内容の具体化)
- Step3:設計・開発・テスト
- Step4:リリース(本番環境への反映)
- Step5:運用・保守
この流れを意識することで、関係者間の認識のズレを防ぎ、スムーズな進行が可能になります。
Step1:ヒアリングと現状分析
システム改修は、現状の課題を正確に把握するヒアリングと分析から始まります。
現場の意見を聞かずに進めると、的外れな改修になりかねません。
【現状分析で明確にすべき点】
- 誰が、どの業務で、何に困っているのか
- システム上の課題と業務フロー上の課題の切り分け
- 課題の発生頻度や業務への影響度
- 複数の課題がある場合の優先順位
ここで集めた現場の生の声が、後の工程すべての土台となります。
「何となく使いにくい」といった漠然とした不満を、具体的な課題に落とし込みましょう。
Step2:要件定義(改修内容の具体化)
次に、分析結果をもとに改修の目的と範囲を定める「要件定義」を行います。
この工程で関係者間の認識を合わせておかないと、プロジェクトの途中で仕様変更が多発し、予算超過や納期遅延の原因になります。
例えば、「売上管理を楽にしたい」という課題に対し、「〇〇のデータを自動で集計し、△△の形式で出力できる機能を追加する」というレベルまで具体化する作業です。
何をどこまで改修するのかを文書化し、関係者全員の合意を得てから次のステップに進みましょう。
Step3:設計・開発・テスト
要件定義が固まったら、システムの設計、開発、そして品質を保証するためのテストを実施します。
それぞれの工程は、定義された要件を実際に動く形にするための中心的な作業です。システム改修では、既存システムへの影響範囲を考慮した設計や、既存機能に影響が出ていないかを確認する回帰テストが特に重要です。
| 工程 | 目的 | 主な作業内容 |
| 設計 | 要件を実現するためのシステムの仕様を決める | 画面レイアウト、機能、データ構造の設計 |
| 開発 | 設計書に基づきプログラムを作成する | プログラミング、機能の実装 |
| テスト | システムが要件通りに動作するか検証する | 機能の単体テスト、システム全体の結合テスト、回帰テスト |
テスト工程では、想定される様々な利用パターンを試すことで、リリース後の不具合を最小限に抑えられます。
利用者にもテストに参加してもらい、実際の業務に近い視点で動作を確認するのも有効です。
Step4:リリース(本番環境への反映)
テストをクリアしたシステムを、実際に業務で使えるように本番環境へ反映させるのが「リリース」です。
リリース作業は、現在の業務への影響を最小限に抑えつつ、慎重に進める必要があります。
【安全にリリースするための注意点】
- 業務時間外や休日に作業を実施する
- 事前に利用者へリリース日時と変更内容を周知する
- リリース直前のデータのバックアップを取得する
- 万が一のトラブルに備え、元の状態に戻す手順を確認しておく
周到な準備を行うことで、予期せぬトラブルのリスクを減らせます。
リリース後は、システムが正常に動作しているかを関係各所で確認するまでがこのステップに含まれます。
Step5:運用・保守
システムはリリースして終わりではなく、その後の安定稼働を支える「運用・保守」が続きます。
実際に使ってみて初めてわかる改善点や、新たな不具合が発生する場合があるからです。
運用・保守の具体的な活動としては、システムの稼働状況の監視、利用者からの問い合わせ対応、定期的なデータバックアップなどが挙げられます。
システムを長期的に、そして安全に活用していくためには、この運用・保守の体制をあらかじめ整えておくことが求められます。
システム改修を依頼する場合の会社の選び方
システム改修を外部に依頼する場合、どの会社を選ぶかがプロジェクトの成否を左右します。
技術力や費用はもちろん、長期的に協力し合えるパートナーを見つけることが求められます。
ここでは、開発会社を選ぶ際に必ず確認したいポイントを解説します。
| 確認すべき観点 | 具体的なチェックポイント |
| 実績と専門性 | 自社の業界や類似システムでの改修実績 |
| 技術力と対応力 | 古いシステムや最新技術への対応経験・トラブル時の対応力 |
| コミュニケーション | 担当者の説明の分かりやすさ・質問への回答の速さと的確さ |
| コストパフォーマンス | 見積もりの内訳が明確で、金額が適正か |
| サポート体制 | リリース後の運用保守の範囲や契約内容 |
| 契約条件 | 納期や仕様変更に対して柔軟な対応が可能か |
これらの観点をリスト化し、複数の会社を比較評価すると良いでしょう。
特に、見積もりの金額だけでなく、なぜその金額になるのかという根拠や、プロジェクトの進め方について、納得のいく説明をしてくれる会社を選ぶ必要があります。
担当者との相性も含め、信頼関係を築けるパートナーを見つけましょう。
システム改修におすすめの開発会社3選
どの開発会社に依頼すれば良いか迷う担当者の方に向けて、システム改修で実績のあるおすすめの開発会社を3社紹介します。
それぞれに特徴や強みがありますので、自社の課題や改修の目的に合った会社を見つけるための参考にしてください。
- トッパジャパン株式会社
- 株式会社GeNEE
- 株式会社ファスト
各社のサービス内容や実績を比較し、信頼できるパートナーを選びましょう。
また、以下の記事ではレガシーシステムのおすすめの開発会社を紹介しているので、合わせて参考にしてください。
▼関連記事
レガシーシステム開発会社おすすめ12選!失敗しない選び方と放置するリスクも解説
トッパジャパン株式会社

出典:トッパジャパン株式会社
トッパジャパン株式会社は、ベトナムの優秀な開発チームを活用したオフショア開発により、「品質」と「コスト」の両立を実現する開発会社です。
コスト削減はもちろんのこと、標準化された開発プロセスと独立した品質検査チームによって、高品質なシステム開発を可能にしています。
日本人SEがベトナムチームとの橋渡し役を担う体制も選択でき、円滑なコミュニケーションでプロジェクトを進められる点が強みです。
フロントエンドからクラウド、AIといった最新技術まで、幅広いスキルを持つエンジニアが多数在籍しており、多様なニーズや短納期にも柔軟に対応します。
国立大学のオンプレミス環境からクラウドへの移行プロジェクトや、Salesforceを基盤とした施設予約システムの構築など実績も豊富です。
株式会社GeNEE

出典:株式会社GeNEE
株式会社GeNEEは、顧客ごとの課題に合わせたオーダーメイドのシステム開発を得意とする会社です。
戦略策定や企画・調査から設計、開発、保守運用までを一気通貫で支援します。
企業の根幹を支える基幹システムから特定の業務システムまで、フルスクラッチ開発で対応できる技術力が特徴です。
QCD(品質・コスト・納期)管理を徹底し、プロジェクトを成功に導く管理能力も強みの1つです。
AWSなどのクラウドプラットフォームを活用したWebシステム開発にも精通しており、企業のDX推進を力強く加速させるパートナーとなりうるでしょう。
株式会社ファスト

出典:株式会社ファスト
株式会社ファストは、特に金融業界や通信業界といった、高い信頼性が求められる分野のシステム開発・保守に豊富な実績を持つ会社です。
情報系システムの老朽化対応やシステム統合・再構築といった、システム改修で直面しがちな課題解決に強みがあります。
顧客先にチーム単位で常駐する体制を特徴とし、クライアントへのコストメリットを提供しつつ、リーダーの育成や若手のフォローまで含めた手厚いサポートを実現しています。
まとめ
システム改修は、不具合修正や業務効率化、法改正への対応など、変化するビジネス環境に企業が対応し、成長を続けるために不可欠な取り組みです。
成功の鍵は、改修の目的と範囲を明確にし、費用対効果を意識しながら計画的にプロジェクトを進めることです。
また、見積もり金額だけでなく、実績や技術力、サポート体制を総合的に評価し、長期的な視点で信頼できる開発パートナーを選ぶことが求められます。
この記事を参考に、まずは自社のシステムの課題を整理するところから始めてみましょう。
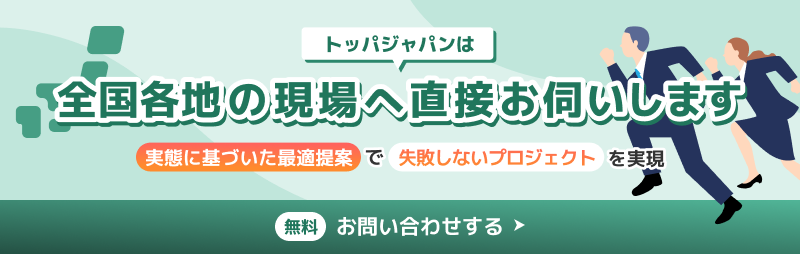
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説