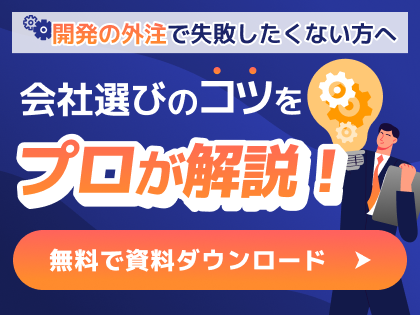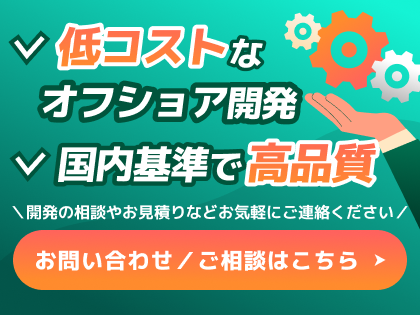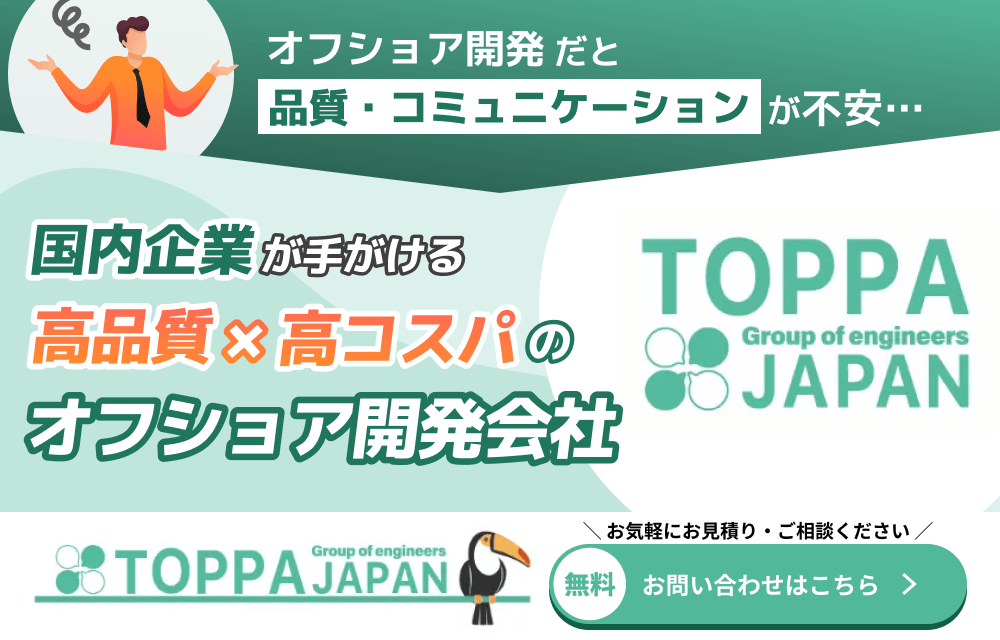教育現場のDX推進が加速する中、効果的なシステム開発とパートナー選びは、教育機関の未来を左右する重要な課題となっています。
本記事では、教育業界に特化したシステム開発会社4社の特徴と強みを紹介するとともに、選定時に注目すべき6つのポイントを詳しく解説します。
また、実際の導入成功事例を通じて、効果的なシステム導入のアプローチについても具体的に見ていきます。さらに、教育機関がIT化・DX推進に取り組むべき理由と、その導入によってもたらされる主な効果についても掘り下げます。
教育業界のシステム開発会社【4選】
オフショア開発を手がける企業の中には、教育システムに特化したサービスを提供する会社が増えています。コストパフォーマンスの高さと専門性を兼ね備えた開発会社を選ぶことで、学校や教育機関の課題解決に大きく貢献できます。
今回は、教育分野での開発実績が豊富なオフショア開発会社4社をピックアップしました。それぞれの強みや特徴を理解することで、自校の状況に最適な開発パートナーを見つける参考にしてください。
トッパジャパン

出典:トッパジャパン株式会社
トッパジャパンは、ベトナムの優秀な開発者と連携した高品質なオフショア開発サービスを提供しています。開発コストの高騰や人材不足といった課題に直面する教育機関は、ぜひ一度お問い合わせください。
【トッパジャパンの強み】
- 品質とコストの両立:単に安価なだけでなく、標準化された開発プロセスにより高品質を保証
- 幅広い技術スキル:フロントエンド、バックエンド開発から技術リーダーまで多彩な人材が在籍
- 柔軟な対応力:顧客ニーズに合わせたカスタマイズ開発体制の構築
また、開発以外にも「教育ソリューションサービス」を提供しており、「ICT支援・ヘルプデスク」では2024年度に48校の支援実績があり、教員のICT活用をサポートしています。「保守・メンテナンス」では61校をサポートし、機器トラブルにも迅速対応してきました。
さらに「教育ICT・DXコンサルティング」や「GIGA端末・教育IT機器の導入支援」も手がけ、ICT環境整備の全段階をカバーしています。セキュリティ要件の厳しい学校向けシステムにも対応できる技術力の高さが魅力です。
カオピーズ

出典:株式会社カオピーズ
カオピーズは学習支援に「柔軟性」「創造性」「安心・信頼性」をもたらすことがモットーの、日本専門のオフショア開発会社です。教育分野にも力を入れており、学習支援ツールから管理システム、コミュニケーションツールまで幅広く開発しており、教育現場の業務効率化に貢献しています。
【教育向けソリューション】
- 教員・講師向け支援:校務支援システムや授業運営効率化ツールの提供
- 生徒向け支援:学習支援ツールやLMS(学習管理システム)の開発
- 塾・学校向け支援:業務管理の効率化、スケジュール管理、成績記録の自動化
ベトナム屈指の技術系大学出身者を中心とした優秀なエンジニア陣と、日本語堪能なブリッジSEの存在が、コミュニケーションの壁を解消。100社以上との取引実績と400件を超える開発経験から、AI、RPA、ブロックチェーンなど最新技術の導入にも対応できる点も強みです。
ビナヤマト

出典:ビナヤマト
ビナヤマトは、ベトナムと日本の架け橋として2009年に設立されたオフショア企業です。ハノイ工科大学出身の優秀なエンジニアが中心となり、日本人技術者による品質管理のもと、高水準の開発サービスを提供しています。
【ビナヤマトの特徴】
- 日本流の品質管理を徹底した開発体制
- ハノイ工科大学出身の優秀なエンジニアを多数採用
- 長年の経験を持つ日本人エンジニアによる指導
- ベトナム進出企業向けコンサルティング支援も提供
教育分野では「EduCross」というクラウド型eラーニングシステム(LMS)が代表的な製品です。初期費用ゼロ、月額300円から導入可能という低コストが魅力で、学校教育や塾、教育系出版社、企業内教育など様々な場面で活用できます。
必要に応じて有償でのカスタマイズにも対応する柔軟性も備えており、教育機関の多様なニーズに応えられる体制を整えています。
エスエイティーティー

出典:エスエイティーティー
エスエイティーティー株式会社(SATT)は、駿台グループの一員として質の高いIT教育サービスを提供している企業です。教育、人材育成、技術進歩を軸に、駿台グループのICT技術推進を担う重要な役割を果たしています。
【SATTの事業内容】
- 学校総合支援(コンサルティング、校務支援、教育支援)
- eラーニング事業
- システム開発事業(一般システム、駿台予備学校向けシステム、AIサービス)
開発面では、ミャンマーでのオフショア開発に着手し、高い技術力と低コストを両立させています。日本の1人月分の委託料でミャンマー現地の2〜3名のエンジニア作業に相当するため、コスト効率が非常に高いのが特徴です。
また、以下の記事ではシステム開発のコスト削減策について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発のコスト削減策6選!コストが高騰する原因や成功事例も紹介
教育ICTやシステム開発企業の選定ポイント

教育ICTやシステム開発企業を選ぶ際のポイントは、以下の6つです。
- 開発実績の確認
- サポート体制の充実度
- コストパフォーマンス
- セキュリティ対策
- ユーザビリティと操作性
- 柔軟な対応力
それぞれ詳しく解説します。
開発実績の確認
教育システムの開発企業を選ぶ際、最も信頼できる指標となるのが過去の開発実績です。教育分野は一般企業向けシステムとは異なる特殊な要件が多いため、教育現場での導入経験が豊富な企業を選ぶことが重要です。
【開発実績の確認ポイント】
- 類似規模・種類の教育機関での導入事例数
- 成功事例の具体的な成果や効果測定データ
- 長期運用している導入先の有無
特に注目すべきは、自校と同じ学校の種類(小中高校、大学、専門学校など)での導入実績です。例えば小学校と大学では求められるシステムの機能や運用方法が大きく異なるため、該当する学校の種類での経験が豊富な企業を優先的に検討しましょう。
また「○○大学に導入しました」という情報だけでなく、導入によって「テスト採点時間が30%削減された」「学生の授業満足度が15%向上した」など、定量的な効果が示されているかを確認することが重要です。
また、以下の記事ではシステム開発を外注・内製するメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発を外注・内製するメリット・デメリットを解説!判断基準や開発費用も紹介
サポート体制の充実度
教育システムは導入して終わりではなく、日常的な運用や突発的なトラブル対応が必要です。特に教員のICTリテラシーにはバラつきがあるため、手厚いサポート体制を持つ企業を選ぶことが重要です。
【サポート体制のチェックポイント】
- 問い合わせ窓口の種類と対応時間
- 研修・トレーニングプログラムの内容
- マニュアルや操作ガイドの充実度
- 障害発生時の対応フロー
理想的なのは、電話・メール・チャットなど複数の窓口を用意し、学校の活動時間に合わせて対応できる体制が整備されている企業です。特に授業中のシステムトラブルは即時対応が求められるため、緊急時の対応体制が整っているかを確認しましょう。
また、導入時の研修プログラムも重要です。操作説明だけでなく、教育現場での活用事例や指導のポイントなど、教育的視点を含んだ研修を提供しているかをチェックしましょう。段階的な研修計画や継続的なフォローアップ体制があると、教員のICT活用スキルを徐々に向上させることができます。
また、以下の記事ではシステム開発の費用相場について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の費用相場は?コスト内訳や費用を安く抑えるコツも解説
コストパフォーマンス
教育機関では限られた予算内でICT環境を整備する必要があるため、コストパフォーマンスは開発企業選定の重要な判断基準となります。ただし、初期費用の安さだけで判断するのではなく、総所有コストと得られる効果のバランスを考慮することが大切です。
【コスト評価のポイント】
- 初期導入費用と継続的な運用コストの内訳
- ライセンス体系と学校規模に応じた柔軟性
- 追加開発やカスタマイズ時の費用体系
- 導入後の費用対効果の検証方法
初期費用だけでなく、保守・運用費用やライセンス更新料、バージョンアップ費用など、中長期的に発生するコストを含めた総合的な評価が必要です。5年間の総所有コストで比較すると、初期費用は高くても運用コストが低い企業のほうが結果的に経済的な場合もあります。
また、学校の規模や利用状況に応じた柔軟な料金体系を持つ企業を選ぶことも重要です。利用者数や機能ごとの従量課金制や、必要な機能だけを選択できる料金体系があれば、無駄なコストを抑えることができます。
また、以下の記事では国別のオフショア開発の平均コストや価格の決まり方について比較・紹介しています。オフショア開発の依頼国にお悩みの方は、あわせてご覧ください。
→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社
セキュリティ対策
教育機関では生徒・学生の個人情報や成績データなど、機密性の高い情報を取り扱うため、高水準のセキュリティ対策を講じている企業を選ぶことが重要です。
【セキュリティ確認事項】
- 情報セキュリティ認証の取得状況(ISO27001など)
- データ暗号化やアクセス制御の仕組み
- バックアップ体制と災害復旧計画
- セキュリティインシデント発生時の対応フロー
まず確認すべきは、第三者機関による情報セキュリティの認証取得状況です。ISO27001やプライバシーマークなどの認証を取得している企業は、一定水準以上のセキュリティ管理体制を整えていると評価できます。
また、システム自体のセキュリティ機能も重要です。ユーザー認証の強度、データ暗号化の方式、アクセス権限の細かな設定など、多層的なセキュリティ対策が施されているかをチェックしましょう。特に重要なのは、教職員と生徒・学生、保護者など、利用者の役割に応じた適切なアクセス権限設定が可能かどうかです。
ユーザビリティと操作性
教育システムは教員や生徒が日常的に使用するものであり、使いやすさがポイントです。特に教育現場ではICTスキルの差が大きいため、誰もが直感的に操作できるシンプルなインターフェースを持つシステムを選びましょう。
【ユーザビリティの評価ポイント】
- 画面デザインの分かりやすさと一貫性
- 操作手順のシンプルさと効率性
- 多様なデバイスへの対応状況
- アクセシビリティへの配慮
必要な機能にすぐにアクセスできる整理された画面構成と、一貫性のある操作方法を持っているのが理想的なシステムです。教員が授業準備や成績入力などの業務を効率的に行えるよう、よく使う機能へのショートカットや、一括処理機能などが充実しているかをチェックしましょう。
また、様々な端末での利用のしやすさも重要です。学校でのPC利用、家庭でのタブレットやスマートフォン利用など、マルチデバイス環境での動作検証を行っているか確認してください。レスポンシブデザインが採用され、画面サイズに応じて最適な表示がされるシステムが望ましいでしょう。
柔軟な対応力
教育現場では学校ごとに異なるカリキュラムや運用体制があり、また教育方針や重点施策も年度によって変化します。そのため、学校の状況に応じて柔軟にカスタマイズや機能拡張が可能なシステムであることが重要です。
【柔軟性の評価ポイント】
- カスタマイズの可能範囲と方法
- 他システムとの連携・統合の実績
- 将来的な拡張性と最新技術への対応
- 要望への対応スピードとプロセス
まず、システムのカスタマイズ性をチェックしましょう。学校独自の評価基準や帳票フォーマットへの対応、独自機能の追加等がどの程度可能か、またカスタマイズにかかる期間や費用の目安を確認することが大切です。
既存システムとの連携も重要なポイントです。校務支援システムや学習eポートフォリオ、図書館システムなど、学校内の他システムとのデータ連携が可能かを確認しましょう。
また、以下の記事ではシステム開発が安い会社について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発が安い会社4選!費用相場や開発費用を安く済ませるポイントも紹介
教育システム導入の成功事例

ここでは、トッパジャパンが手がけた教育システム導入の成功事例をご紹介します。システム導入を検討されている教育機関の方々は、ぜひ自校の状況と照らし合わせながらお読みください。
オンプレ環境をクラウドシステムに移行プロジェクト
ある大学では、経費削減を主な目的として、従来のオンプレミス環境からクラウドサーバーへの移行を計画していました。このプロジェクトの特徴は、セキュリティ対策として国内外のクラウドサービスを併用する必要があった点です。
この案件ではシステム移行にとどまらず、情報共有化や業務自動化ツールの開発も並行して行いました。クラウド環境の利点を最大限に活かした設計により、当初の目標以上の経費削減が実現できたのです。
結果として、削減できた予算は学生募集戦略に再配分することが可能となり、教育機関としての本来業務強化につなげることができました。
迷惑メール判別ツール開発プロジェクト
大学のセキュリティ対応部署では、学生や職員宛に届く大量のメールについての問い合わせ対応に追われていました。特に、海外からのメールが迷惑メールか正常メールかの判断に多くの時間が費やされ、業務効率低下の原因となっていました。
このプロジェクトでは、AIを活用したメール自動判別ツールを開発し、迷惑メールと正常メールを識別できるシステムを構築しました。
ツール導入の結果、セキュリティ担当者の作業負担が大幅に軽減され、空いた時間をより高度なセキュリティ対策に充てられるようになりました。
メタ認知支援のためのICTツールの研究
高等学校では、生徒の自己分析・自己決定能力を向上させるためのICTツール研究を継続的に行っています。学校現場と開発会社が密に連携し、実際の教育現場からのフィードバックを取り入れながらシステム開発を進めているのが特徴です。
このプロジェクトでは、既存システムの詳細な解析を行った上で、運用保守業務を担当。実際の授業で発生する課題や要望を迅速に取り入れ、定期的なバージョンアップにより機能改善を行っています。
教育業界のIT化・DX推進が求められる理由

教育現場のIT化・DX推進は、もはや必須の取り組みとなっています。従来の紙と黒板中心の教育から脱却し、デジタル技術を活用した新たな学びの形が求められる背景には、複数の社会的要因が存在します。
【IT化・DX推進が求められる主な理由】
- コスト削減
- 教育の質向上と個別最適化
- デジタルネイティブ世代への対応
- 遠隔教育の実現と教育機会の拡大
- 教職員の業務効率化と働き方改革
- 社会全体のデジタル変革への適応
特にコスト面では、デジタル化によって削減できた予算を人材確保や施設改善など、教育の質を直接高める分野に再配分できる利点があります。
また、GIGAスクール構想を契機に全国の学校で1人1台端末環境が整備されたことで、これらを活用した新たな教育実践が求められています。コロナ禍での休校対応でも明らかになったように、デジタル環境は教育の継続性を支える重要なインフラです。
また、以下の記事ではシステム開発の見積もりについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の見積もりの見方を解説!見積書の項目や見積もり手法・算出方法も紹介
教育のICT化がもたらす主な効果

教育現場でのICT導入は授業のデジタル化にとどまらず、以下のような効果をもたらします。
- 学習の効率化と質の向上
- 生徒のモチベーション向上
- 各生徒に最適な学びの実現
- 教員の負担軽減
それぞれ詳しく解説します。
学習の効率化と質の向上
ICT導入により、教育の効率性と質が大幅に向上します。従来の黒板とテキストによる一方通行の授業から、多様な学習体験を提供できる環境へと変化するのです。
【学習効率化と質向上の主な効果】
- 視覚・聴覚に訴える多彩な教材提示が可能
- 学習管理システム(LMS)による情報共有の迅速化
- 理解度に応じた指導の最適化
電子黒板やタブレット端末を活用した授業では、動画や図表などのマルチメディアコンテンツを効果的に取り入れることで、抽象的な概念も視覚的に理解しやすくなります。また、LMSを通じた教材配信により、生徒は授業外でも学習を継続でき、自分のペースで何度も復習できる環境が整います。
また、以下の記事ではラボ型開発について解説しています。あわせてご覧ください。
→ ラボ型開発とは?アジャイル開発や他の契約形態の違いやおすすめの事例も紹介
生徒のモチベーション向上
ICT活用は生徒の学習意欲を高めるツールです。デジタル機器ならではの特性を活かした授業は、生徒にとって魅力的で取り組みやすく、学習への積極性を引き出す効果があります。
【モチベーション向上の主な要素】
- 動画・音声・アニメーションによる魅力的な授業展開
- ゲーム要素を取り入れた学習の実現
- 調べ学習やプレゼンテーション作成による主体性の育成
- ICT活用による授業参加のハードル低下
タブレットや電子黒板を活用した授業では、静的なテキストだけでは伝わりにくい内容も、動きのある映像や音声で効果的に伝えられます。また、クイズ形式を取り入れた学習では、楽しみながら知識を定着させることが可能です。
また、プレゼンテーション作成や発表活動でICTを活用することで、生徒の自己表現力も高まります。自分で調べ、考え、発表する経験が自信につながり、教科への興味関心を深める好循環を生み出すのです。
各生徒に最適な学びの実現
ICT化の大きな効果の一つが、一斉授業の限界を超えた個別最適化学習の実現です。従来の「一人の教師が同じ内容を全員に教える」モデルから、一人ひとりの理解度や進度に合わせた学習が可能になります。
【個別最適化学習の主な特徴】
- AIを活用した適応型学習教材の提供
- 生徒ごとの学習データに基づいた指導の精度向上
- 習熟度や苦手分野に応じた問題提供
- 特別支援を必要とする児童生徒への効果的な対応
1人1台端末を持てる環境を整備することで、AIを搭載したドリル教材などを通して、生徒それぞれの解答傾向や習熟度をリアルタイムで分析可能です。システムは自動的に各生徒の理解度に合った問題を出題するため、基礎的な内容のつまずきも早期に発見して対応できます。
特に重要なのは、学習データの蓄積により教師の指導精度が向上する点です。生徒の正答率や解答時間、解答プロセスまで把握できるため、個々の生徒に必要な支援を的確に行えるようになります。
教員の負担軽減
ICT化は教員の業務効率化と働き方改革にも貢献します。日本の教員の長時間労働が社会問題となる中、ICTを活用した業務効率化は教育の質を維持しながら、持続可能な学校運営を実現する鍵となっています。
【教員の負担軽減効果】
- 教材作成と再利用による授業準備の効率化
- 配布資料や連絡事項をオンライン共有にすることによる時間短縮
- 校務支援システムによる成績処理・出欠管理の効率化
- ペーパーワーク削減と転記作業の自動化
授業準備では、デジタル教材の作成と共有・再利用により効率化が図れます。一度作ったスライド資料は次年度以降も活用でき、共同編集機能を使って教員間で改良していくことも可能です。また、生徒への配布資料をデジタル化すれば、印刷・仕分け・配布の手間が大幅に削減できます。
重要なのは、削減された時間が教育の質向上に再投資される点です。業務効率化によって生まれた時間を、授業研究や生徒との対話、個別指導などに充てることで、教育の充実につながる好循環が生まれます。
また、以下の記事ではベトナムでラボ型開発を行うメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ ベトナムでラボ型開発を行うメリットは?注意点やおすすめの会社も紹介
まとめ
教育業界のシステム開発において、適切なパートナー選びは成功への第一歩です。開発企業を選定する際は、開発実績、サポート体制、コストパフォーマンス、セキュリティ対策、ユーザビリティ、柔軟な対応力といった6つのポイントを総合的に評価することが重要です。
教育のIT化・DX推進は単なるデジタル化ではありません。学習効率と質の向上、生徒のモチベーション向上、個別最適化学習の実現、教員の負担軽減といった多面的な効果をもたらします。
教育現場ならではの課題を理解し、教育効果を最大化するシステム開発と活用が、これからの教育ICTの質を大きく左右するでしょう。
トッパジャパン|きめ細かいサポートが特徴の教育ソリューションサービス
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説