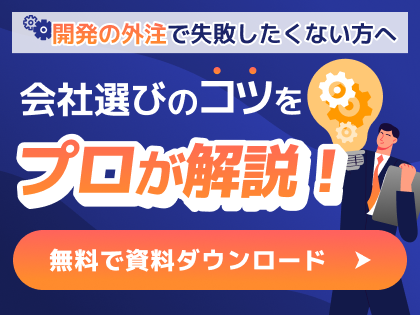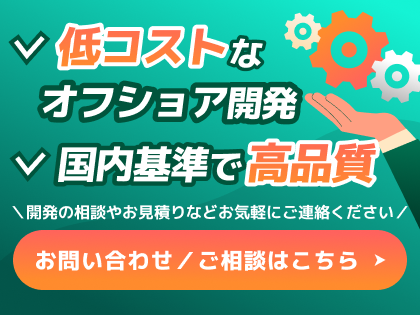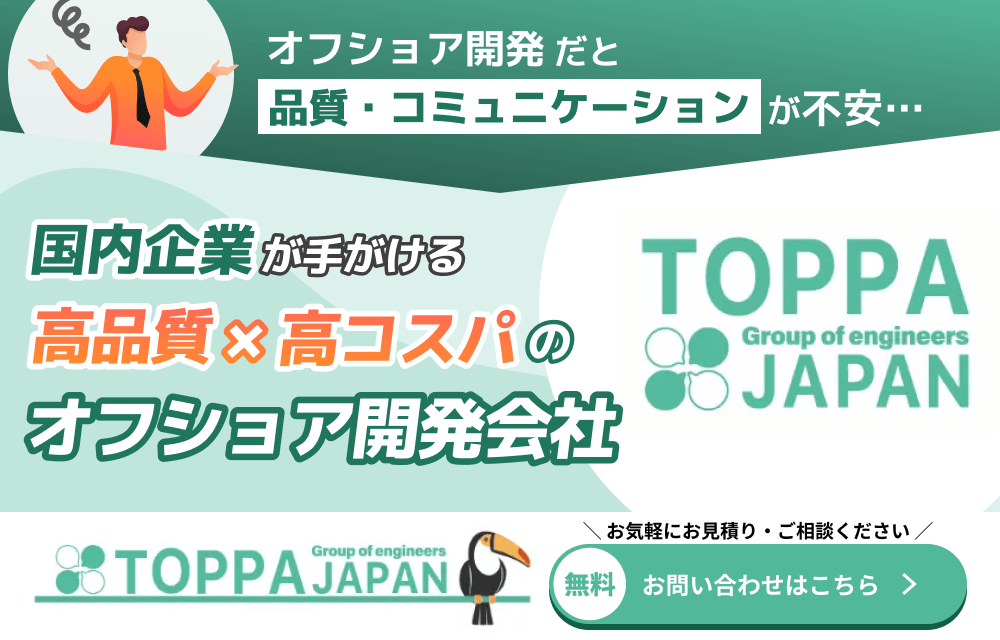エンジニアの単価は、契約形態や職種、使用言語、スキルレベルによって大きく異なります。近年は、AIやクラウドなどの先端技術領域で需要が高まっており、単価も上昇傾向にあるのです。
本記事では、2025年時点のエンジニア単価の相場を「契約形態別」「職種別」「使用言語別」に分類して解説します。また、単価が高いエンジニアの特徴や、企業が外注する際の価格目安についても紹介します。
ご自身のキャリアを見直すヒントにしたい方も、業務委託の発注を検討している企業担当者の方も、ぜひ最後までご覧ください。
エンジニアの平均単価相場
エンジニアの単価相場は、契約形態や職種、使用言語によって大きく異なります。とくに近年はリモート案件の増加や、AI・クラウド分野の需要拡大により、全体的に単価が上昇傾向にあるのです。
ここでは、2025年時点の主要な単価相場を「契約形態別」「職種別」「使用言語別」に分けて解説します。ご自身のスキルやキャリアプランに照らし合わせながら、単価アップの参考にしてください。
【契約形態別】エンジニアの平均単価
エンジニアは契約形態によって単価が変わります。まずは、雇用形態別のエンジニアの単価について紹介します。
| 契約形態 | 月額単価の目安 | 特徴 |
| 正社員 | 約25万〜50万円 | 安定収入だが、成果に応じた単価変動なし |
| 派遣社員 | 約30万〜60万円 | 福利厚生が整う一方で、スキルで差が出にくい |
| 業務委託(常駐) | 約55万〜85万円 | スキル次第で高単価も可能 |
| フリーランス | 約60万〜100万円 | 自由度が高く、高単価案件も選びやすい |
| 副業・週2〜3 | 日給1.5万〜3.5万円程度 | スキルマッチ度が高いと高単価での契約も可能 |
業務委託・フリーランス契約では、単価100万円超の案件もあります。さらに、副業の場合は週数日でも高い単価設定がされる傾向があり、本業+αの収入源として注目されています。
ただし、これらの単価はスキルや年齢、実績により異なるため、あくまでも目安として参考にしてください。
【職種別】エンジニアの平均単価
一口にエンジニアと言っても、その対応業務はさまざまです。ここでは、職種別のエンジニアの平均単価を紹介します。
| 職種 | 月額単価の目安 | 備考 |
| フロントエンドエンジニア | 60万〜90万円 | JavaScriptフレームワーク経験者は高単価 |
| サーバーサイドエンジニア | 70万〜100万円 | API設計・DB設計ができると高評価 |
| Webアプリケーションエンジニア | 60万〜95万円 | フルスタック対応可だと単価も上がる |
| インフラ/クラウドエンジニア | 70万〜100万円 | AWS/GCP資格保持者に高単価が出る傾向 |
| モバイルアプリエンジニア | 65万〜100万円 | iOS/Android双方に対応できると有利 |
| AI/機械学習エンジニア | 75万〜110万円 | Python+統計+実装力のある人材に集中 |
| データエンジニア | 70万〜100万円 | DWH/ETL構築経験者に高単価 |
AIやクラウド分野は、今後も需要が拡大する分野として注目されています。特にデータサイエンス×実装スキルを併せ持つ人材には、月額130万円超の案件も珍しくありません。
これらの単価も、スキルや年齢、実績により異なるため、あくまでも目安として参考にしてください。
【使用言語別】エンジニアの平均単価
エンジニアの平均単価は、使用言語でも変化します。ここでは、使用言語ごとのエンジニアの平均単価を紹介します。
| 使用言語 | 月額単価の目安 | 特徴 |
| Java | 70万〜100万円 | エンタープライズ系で安定した需要 |
| Python | 70万〜110万円 | AI/データ分析分野で高単価 |
| PHP | 60万〜90万円 | Web制作・CMS開発で広く使われている |
| Ruby | 65万〜95万円 | スタートアップ系で人気 |
| JavaScript | 60万〜100万円 | フロントからNode.jsまで幅広く活用可能 |
| Go | 70万〜100万円 | 高パフォーマンスなマイクロサービス向け |
| Kotlin/Swift | 70万〜100万円 | モバイルアプリ開発で安定した需要 |
| TypeScript | 65万〜95万円 | 大規模フロントエンド案件で採用増加中 |
TypeScriptやGoなどのモダン言語は高単価傾向にあります。逆に、古い技術スタックや保守系案件では、やや単価が下がることもあります。
単価アップを狙うなら、人気の高い言語の習得を目指すと良いでしょう。
また、以下の記事ではシステム開発の費用相場について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の費用相場は?コスト内訳や費用を安く抑えるコツも解説
エンジニアの単価を決める要素
エンジニアの単価は、単にスキルの高さだけで決まるものではありません。市場のニーズや契約形態、実績、業務範囲など、複数の要因が複雑に絡み合って形成されています。
ここでは、単価に大きく影響する主な6つの要素について解説します。
1. スキルセットと経験年数
エンジニアの単価を決める要素の一つが「持っているスキルのレベルと経験値」です。
同じ言語でも、単に実装できるだけなのか、要件定義や設計まで任されているのかで評価は大きく変わります。
| 初級(実装メイン) | 〜60万円 |
| 中級(設計〜実装対応) | 70〜90万円 |
| 上級(要件定義/マネジメント可) | 90万円以上 |
また、経験年数だけでなく「どんなプロジェクトに関わってきたか」も重要な指標です。単価アップを目指すには、対応可能な業務を増やすことが重要になります。
2. 業務範囲の広さ
エンジニアの単価を左右する大きな要素のひとつが、業務範囲の広さです。たとえば、実装だけを担当するエンジニアと、要件定義や設計、進行管理などの上流工程に関わるエンジニアとでは、期待される責任の重さや業務の難易度が異なります。そのため、当然ながら単価にも差が出ます。
特にフリーランスや業務委託の現場では、単なる開発要員としてではなく、クライアントとの打ち合わせから仕様策定、チームへの技術的な指導まで含めて求められることも多いです。こうした幅広い役割を担えるエンジニアほど高い単価で契約されやすくなります。
業務範囲が広がればその分プレッシャーも大きくなりますが、自身のスキルを総合的に評価してもらえる機会にもつながります。
3. 専門性の高さ
どの技術分野に強みを持っているかも、単価を決めるうえで重要なポイントです。特に近年では、クラウド(AWSやGCP)、AI・機械学習、セキュリティ、データエンジニアリングなどの分野に精通したエンジニアに対して、企業は高い報酬を提示する傾向にあります。
こうした専門領域では、スキルを持っているだけでなく、実際に業務で使いこなせる実践経験があるかどうかが問われます。たとえば「AWSを扱える」というレベルと、「AWS環境を自ら構築・設計し、運用まで対応した経験がある」というレベルでは、クライアントからの評価はまったく異なります。
専門性の高い技術は学習コストも高い一方で、身につけることで単価を大きく引き上げる武器にもなり得るのです。
4. 稼働日数・契約形態
エンジニアがどのような契約形態で働き、どれくらいの稼働日数を確保できるかも、単価設定に強く影響します。正社員や派遣社員の場合は、企業側が社会保険料や福利厚生などのコストを負担しているため、月額報酬は控えめになる傾向があります。
一方、フリーランスや業務委託契約では、こうしたコストが個人の自己負担となる代わりに、単価は高めに設定されやすいのが特徴です。
また、フルタイムで週5日稼働するのか、週2〜3日だけ稼働する副業スタイルなのかでも、月額報酬の見積もりは変わってきます。特に近年は、専門性の高い人材に対して、週数日の稼働でも高単価で契約する企業も増えており、働き方の柔軟性と単価は必ずしもトレードオフではなくなってきています。
5. 稼働スタイル(常駐 or リモート)
かつては「現場常駐」が前提だったエンジニアの働き方も、近年のリモートワーク拡大によって大きく変わりつつあります。リモート案件の増加は、時間や場所に縛られず働きたいエンジニアにとって大きなメリットですが、単価の面では注意も必要です。
たとえば、セキュリティ要件が厳しい企業や、リアルタイムでのコミュニケーションが必要な開発体制では、いまでも「常駐で対応できる人材」に高い報酬を提示するケースがあります。一方で、設計やマネジメントをリモートで担える人材、または自走力のあるフルスタック系エンジニアは、場所に関係なく高単価を維持している場合も多いです。
つまり、稼働スタイルの選択と単価のバランスは、案件の性質やクライアントのスタンスによって変わってくるため、どちらが有利かは一概には言えません。重要なのは、どんなスタイルでも成果を出せる信頼性を示せるかどうかです。
6. 市場ニーズとタイミング
どれだけスキルが高くても、タイミングや市場の需要に合っていなければ、高単価の案件にはつながりにくいのが現実です。逆に、トレンド技術や人材が不足している分野で経験を積んでいる場合は、平均よりも高い単価で声がかかる可能性が一気に高まります。
たとえば、生成AIやWeb3、クラウドインフラの自動化といった分野では、現場で活躍できるエンジニアがまだまだ不足しています。その結果、企業側は限られた人材に対して高報酬でのオファーを出す傾向があります。
また、プロジェクトの立ち上げ期や年度末など、案件が集中しやすいタイミングも狙い目です。
このように、自身のスキルと市場ニーズがうまく重なったときに、最も高単価で契約できるチャンスが生まれます。単価を上げたいのであれば、技術のトレンドや業界動向を常にキャッチアップしておくことが不可欠です。
また、以下の記事ではシステム開発の見積もりについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の見積もりの見方を解説!見積書の項目や見積もり手法・算出方法も紹介
単価が高いエンジニアの特徴とは?
同じエンジニアでも、契約単価に大きな差がつくことは珍しくありません。その違いを生むのは、スキルレベルや経験だけでなく、「仕事の選び方」や「働き方」にも関係しています。
ここでは、実際に高単価で契約を獲得しているエンジニアに共通する3つの特徴をご紹介します。単価アップを目指すうえでのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
特徴1. トレンド技術への対応力が高い
高単価エンジニアの多くは、技術トレンドに敏感であり、常に学び続ける姿勢を持っています。たとえば、AIや機械学習やクラウドインフラ(AWSやGCP)、DevOps、自動化ツールなど、注目される分野のスキルを早期に身につけることが重要です。
技術には常に流行があります。既存技術にだけ固執していると、需要の減少とともに単価も伸び悩んでしまいます。その点、トレンド技術へのキャッチアップを怠らないエンジニアは、最新案件への参画機会も多く、結果として報酬単価の上昇につながっていくのです。
また、単に知識があるだけでなく、実務に落とし込めるスキルを持っていることが重要です。トレンド技術を業務に活かした経験があるかどうかが、高単価を実現するカギとなります。
特徴2. 要件定義・マネジメントもできる
高単価エンジニアは、実装だけでなく、プロジェクトの上流工程にも関与できることが多いです。たとえば、クライアントと一緒に要件を整理したり、チーム全体の進行管理を担ったりすることができれば、その価値は単なる作業者以上のものになります。
特にスタートアップや中小企業では、「言われたことを作る人」よりも「何を作るべきか一緒に考えられる人」が強く求められます。そのため、ヒアリング力や課題設定力、ドキュメンテーション能力など、開発以外のコミュニケーションスキルも単価に反映されやすいのです。
また、リーダーやPMの役割を担えるエンジニアは、現場の安定稼働に不可欠な存在となるため、継続的に高単価でアサインされる傾向にあります。自らの技術力を活かしつつ、プロジェクト全体の成果に貢献できることが、単価の差を生む決定的な要因になるのです。
特徴3. 営業力・交渉力がある
意外と見落とされがちなのが、自分を売り込む力です。どれだけスキルや実績があっても、それを適切にアピールできなければ、望む単価で契約を結ぶことは難しくなります。
たとえば、ポートフォリオや職務経歴書を工夫して、自分の強みをわかりやすく伝えられるエンジニアは、クライアントやエージェントに好印象を与えやすくなります。また、商談や面談の場で、希望単価の根拠を論理的に説明できることも、高単価での契約を勝ち取るうえでは欠かせません。
さらに、案件選びの段階で「どの仕事に応募するか」を戦略的に見極める目も重要です。相場より単価が高めの案件に積極的にアプローチする、複数のエージェントを活用して比較検討するなど、営業的な動き方をしているエンジニアほど、結果的に高単価を実現しています。
単価は、スキルだけでなく「自分をいかに正当に評価してもらうか」という意識にも左右されるということを忘れてはいけません。
企業がエンジニアを外注する際の単価目安
エンジニアの外注を検討する際、多くの企業が悩むのが「どれくらいの費用を見込めばよいのか」という点です。実際の単価は、契約形態や業務内容、発注先の種類によって大きく異なります。
ここでは、SIerやSESを活用する場合、自社サービスの開発を外注する場合、さらに発注先ごとのコスト感の違いについて、実務担当者向けにわかりやすく解説していきます。
SIer・SES契約での相場
システム開発を外注する際に多くの企業が利用するのが、SIerやSESとの契約です。
SIerを通じてプロジェクトを一括発注する場合、見積もりはプロジェクト単位で提示されるのが一般的ですが、エンジニア単価の相場感としては月額80万円〜120万円程度がひとつの目安となります。なかでも、大手SIerを経由する場合は中間マージンが発生するため、単価が高くなりがちです。
一方、SES契約では常駐型のエンジニア派遣という形式で契約されることが多く、月額単価の目安は60万円〜90万円程度です。エンジニアのスキルや業務範囲によって変動はありますが、即戦力を短期的に確保できるという点で、柔軟性の高い契約形態として利用されています。
ただし、いずれの形式でもコミュニケーションの質や仕様理解力、人材の入れ替わりリスクなど、価格以外の観点も重要になります。
自社サービス開発での外注時単価
自社で新しいサービスやアプリを開発する際、開発会社やフリーランスに業務を委託するケースも増えています。この場合の単価は、開発範囲・フェーズ・契約方法によって大きく異なります。
たとえば、フリーランスエンジニアに業務委託する場合、月額単価は50万円〜100万円前後が相場です。モダンな技術スタックに対応できる人材や、設計から運用まで一貫して任せられる人材であれば、さらに高単価になることもあります。
一方、開発会社に一括で依頼する場合、要件定義から設計・開発・テスト・保守まで含めて請け負う受託開発型となります。プロジェクト単位で見積もるため、数百万円〜数千万円規模の金額となることも多いです。
特にUI/UXデザインやクラウド環境構築、セキュリティ対応などが加わると、コストはさらに増加します。
スピード重視でプロトタイプやMVP開発を依頼する場合は、スタートアップ系開発会社や少人数チームを選ぶことで、1〜2ヶ月の短期プロジェクトに絞って費用を抑えることも可能です。
発注先の選び方とコスト比較
外注費用を検討するうえでは、単価だけでなく発注先の種類ごとの特徴とコスト構造を理解しておくことが重要です。
SIerや大手開発会社に依頼する場合、組織としての安定性やプロジェクト管理体制が整っている反面、中間マージンが加算され、単価は高めになります。一定規模以上のプロジェクトや、官公庁・大企業との取引実績が求められるケースでは、有力な選択肢となるでしょう。
一方、フリーランスや小規模開発チームへの直接発注は、中間コストを削減できるぶん費用を抑えられる可能性があります。ただし、リソースの柔軟性やバックアップ体制の面では注意が必要です。
案件の進行管理やコミュニケーションを自社で担う前提であれば、コストパフォーマンスの高い選択肢になります。
また、エンジニア仲介エージェントを利用する方法もあり、この場合は案件単位ではなく月額稼働ベースでの発注が中心となります。エージェント経由のメリットとしては、スキルマッチングの精度や契約手続きの簡素化が挙げられますが、そのぶんマージンも考慮しなければなりません。
最終的には、コスト・品質・スピードのバランスをどう取るかが判断基準になります。必要な技術レベルやスケジュール感を明確にしたうえで、目的に合った発注先を選ぶことが、プロジェクト成功の鍵を握ります。
まとめ
エンジニアの単価は、スキルや実績だけでなく、業務範囲や働き方、そして市場の需要といったさまざまな要因によって決まります。トレンド技術をいち早くキャッチアップし、上流工程やマネジメントにも対応できるエンジニアは、より高単価で契約されることもあるでしょう。
また、企業側にとっても、発注先の選び方や契約形態によって費用対効果は大きく変わってきます。中長期的な視点で、スキル・コスト・体制のバランスを見極めることが重要です。
単価の相場を正しく把握することは、エンジニアにとってはキャリア戦略を立てる第一歩であり、企業にとっては最適な人材確保の鍵となります。本記事の内容を参考に、自身のポジションや目的に合った判断をしていきましょう。
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説