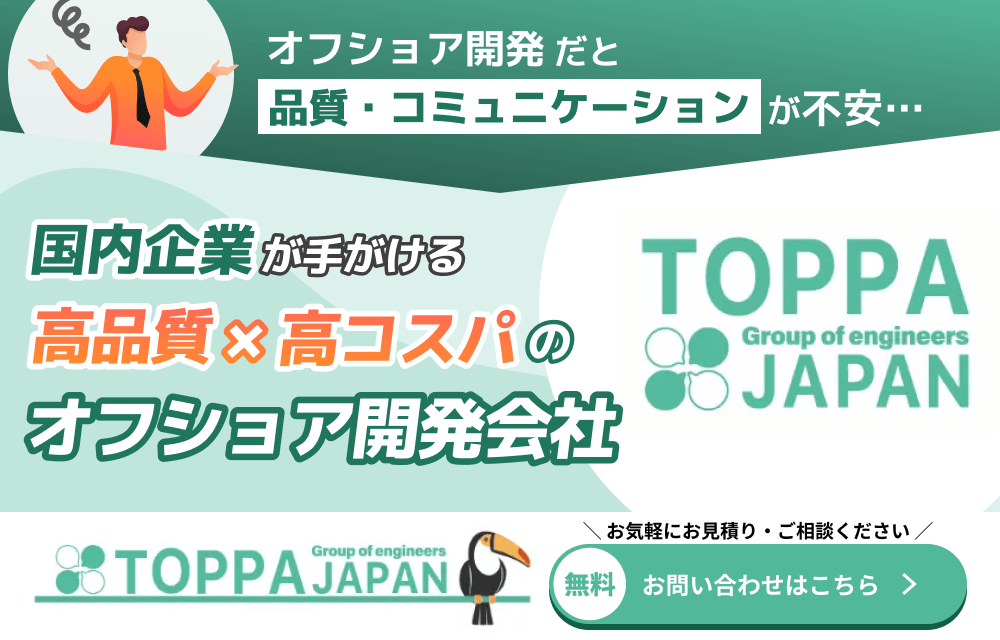生成AIは、テキストや画像、音声などのコンテンツを自動で作成できる革新的な技術です。近年は、業務に生成AIを導入する企業が増えています。
本記事では、生成AIの概要や種類、導入ステップを解説します。業務における生成AIの導入を検討している場合は、ぜひ最後までご覧ください。
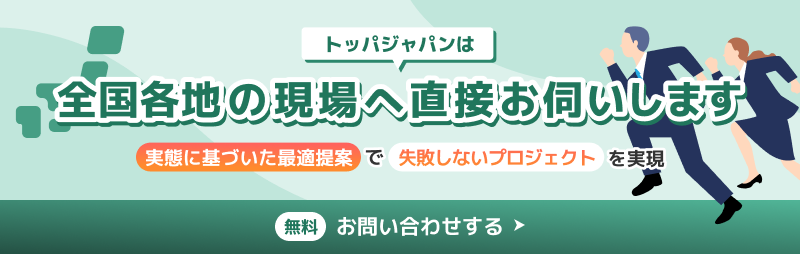
生成AIとは
生成AIとは、画像や文章、音声などのコンテンツを自動で生成するAI技術です。生成されるコンテンツの品質が非常に高く、人間が作成したような仕上がりとなることが特徴です。
従来のAIがデータの分類や予測といった分析的なタスクを得意としていたのに対し、生成AIは創造的なアウトプットに特化しています。
近年は、マーケティングやカスタマーサポート、商品企画など多様な業務への活用が進んでおり、企業活動における生産性向上やコスト削減に貢献する技術として注目を集めています。
生成AIの種類
生成AIは、用途や内容に応じて選定しましょう。主な生成AIの種類は以下の通りです。
| テキスト生成AI | ・プロンプトに基づいて、人間が書いたような自然な文章を自動で生成するAI・ChatGPTやClaude、Geminiが代表格 |
| 画像生成AI | ・プロンプトに基づいて、オリジナルの画像を生成するAI・MidjourneyやCanva AIが有名 |
| 音声・動画生成AI | ・プロンプトに基づいて、音声コンテンツや動画コンテンツを生成するAI・SynthesiaやElevenLabsが有名 |
| マルチモーダルAI | ・異なる種類の情報をまとめて扱うAI・テキスト・画像・音声を横断して理解・生成できる・GPT-4oやGemini 1.5が該当する |
これらのAIを業務に導入する際は、機能だけでなく、導入コストやセキュリティ対応、連携のしやすさも検討しましょう。
また、以下記事ではAI導入に強い開発会社やAIの導入事例について紹介しています。あわせてご覧ください。
→ AIシステム開発に強い会社5選!生成AIと従来のAIの違いや費用・導入事例も解説 – トッパジャパン株式会社
生成AIの導入ステップ
ビジネスにおける活用効果を最大化するには、適切な手順で導入することが重要です。以下では、生成AIの導入ステップを紹介します。
また、以下記事ではAIの開発手法や、AIを活用したシステム開発事例を紹介しています。あわせてご覧ください。
→ AI開発の主な手法とは?開発に必要な言語やAIを活用したシステム開発の事例も紹介 – トッパジャパン株式会社
ステップ1. 導入目的を明確にする
まずは、生成AIの導入目的を明確にしましょう。たとえば、業務の効率化や人的リソースの補完、顧客対応のスピードアップなど、生成AIを活用して解決したい課題をイメージします。
目的が不明確だと、効果を実感しにくく、無意味な導入に終わってしまう場合があります。社内の課題と照らし合わせながら、生成AIを取り入れる場面を見極めることが大切です。
ステップ2. 生成AIに任せる業務をリストアップする
生成AIに任せる業務を具体的に検討していきます。たとえば以下のような業務が候補になります。
- メールの作成や返信の自動化
- ブログ記事や商品説明文の生成
- FAQやチャットボットの自動応答
- 会議議事録の要約
- コードの自動生成やデバッグ支援
「すぐにAIで対応できる業務」と「将来的に対応できる可能性がある業務」に分けて整理することで、段階的な導入計画が立てやすくなります。
ステップ3. 業務内容に応じた生成AIを選定する
生成AIには、テキスト生成や画像生成などさまざまな種類があると既出の章で紹介しました。その中から、自社の業務に適した生成AIツールを選びましょう。生成AIは、それぞれに得意分野や機能の違いがあります。
たとえば、自然な文章生成に強みを持つChatGPTやClaude、画像生成に強いMidjourneyやStable Diffusionなど、目的に応じて選定することが重要です。また、業務システムとの連携性やAPIの有無、セキュリティ要件も選定の際の検討ポイントになります。
また、以下記事では生成AIのChatGPTを活用した業務効率化アイデアとプロンプトを紹介しています。あわせてご覧ください。
→ ChatGPTによる業務効率化のアイデアとプロンプト集!セキュリティ対策も解説 – トッパジャパン株式会社
ステップ4. 生成AIを導入する
社内データとの連携やカスタマイズが必要な場合は、IT部門や外部ベンダーとの連携が不可欠です。
また、導入と並行して、社内向けの利用ルールを決めておきましょう。生成AIは使い方次第で成果が大きく変わるため、社内全体で正しく活用できる体制を整えることが重要です。
ステップ5. 生成AIの導入効果を測定・改善する
導入後の運用状況をモニタリングし、当初設定した目的に対して効果が出ているかを継続的に評価します。以下のような観点をチェックしましょう。
- 業務時間の削減率
- エラーや修正の頻度
- 顧客対応の品質改善度
効果測定の結果をもとに、生成AIに任せる業務の見直しやツールの再選定、プロンプトの改善などを行い、PDCAサイクルを回すことで、生成AIの導入効果を最大化できます。
自社に最適な生成AIツールを見極めるポイント
生成AIツールを話題性や知名度だけで選ぶと、導入後にさまざまなトラブルが発生する場合があります。ここでは、自社に合う生成AIを見極めるポイントを紹介します。
1. セキュリティ・データ管理の安全性の高さ
業務に生成AIを導入するときは、セキュリティとデータ管理の安全性について確認しましょう。特に、業務で顧客情報や社外秘の文書を扱う場合、入力内容がAIの学習に利用されないか、クラウド環境の安全性は確保されているかなどをチェックする必要があります。
また、管理者による操作ログの記録や、アクセス権限の制御ができるかなど、運用面での体制も確認しておくと安心です。セキュリティが強化された企業向けプランを利用するのもおすすめです。
2. 操作性・ユーザーインターフェース
優れたAIツールを導入しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。画面の操作性や対応言語、プロンプト作成の手軽さなどを確認し、社内全体で活用できるかをチェックすることが大切です。
利用者のITスキルにばらつきがある場合は、研修コンテンツの利用も検討しましょう。
3. 連携・拡張性の高さ
生成AIを業務に導入するなら、既存の社内システムやクラウドと連携できるツールがおすすめです。たとえば、SlackやNotion、Google Workspaceなどのツールや、自社ツールと連動できるかなど、拡張性の高さによって業務に適用できる幅も大きく変わってきます。
業務に導入する生成AIは、将来的な活用拡大も見据えて選定しましょう。
4. 導入コストと運用コスト
生成AIツールには、さまざまな料金体系があります。月額固定料金、従量課金、トークン数による制限など、ツールごとにコストの仕組みが異なるため、導入前によく確認しましょう。
導入後の運用拡大によって予想外のコスト増につながるケースもあるため、長期的な利用を見据えたコストシミュレーションも行っておくと安心です。
また、以下の記事ではAI開発で利用可能な補助金や申請のポイントについて紹介しています。あわせてご覧ください。
→ AI開発で活用できる補助金4選|申請のコツと最新制度の探し方を解説 – トッパジャパン株式会社
5. サポート体制と運用支援
運用中にトラブルが発生したり、使い方がわからなくなった場合に、迅速にサポートが受けられるかどうかも確認すべきポイントです。サポート窓口の対応言語や時間帯、問い合わせ手段、導入時のオンボーディング支援の有無などを事前に確認しておきましょう。
手厚いサポート体制が整っているツールを選ぶことで、現場での定着をスムーズに進めやすくなります。
生成AIを導入する際の注意点
生成AIは業務効率化や生産性向上に大きく貢献する一方で、正しく運用しなければ思わぬトラブルを招くこともあります。特に、企業での導入にあたっては、セキュリティやコスト、情報の信頼性といった観点から慎重な対応が求められます。
ここでは、導入前に知っておくべき3つの注意点について解説します。
注意点1. セキュリティリスク対策が必要
生成AIを業務に導入する際、最も重視すべきなのがセキュリティ対策です。AIはユーザーが入力した情報をもとに回答を生成しますが、その過程で機密情報や顧客データが外部サーバーに送信されるリスクがあります。
たとえば、顧客リストや契約書の内容など、社外秘の情報を直接AIに入力するのは避けるべきです。また、利用するAIサービスがどのようにデータを扱っているのか、プライバシーポリシーや利用規約の確認も欠かせません。
企業向けプランを提供しているツールには、データを学習に利用しない設定や、暗号化通信・アクセス制御などの機能が備わっています。導入前に社内の情報セキュリティ部門と連携し、安全な運用ルールを明文化しておくことが大切です。
注意点2. 導入・運用のコストがかかる
生成AIの多くは無料プランが用意されていますが、実際に業務レベルで安定的に利用するためには、一定のコストが発生します。月額制・従量課金制・ユーザー単位課金など料金体系はツールによって異なり、利用頻度や用途によって費用が大きく変動します。
さらに、社内教育やプロンプト設計、運用体制の整備といった間接的なコストも無視できません。たとえば、社員全員が効果的にAIを使いこなすための研修や、ガイドライン策定の時間、人件費なども事前に考慮しておくべきです。
また、精度向上や自社データ連携を行う場合には、カスタマイズやAPI連携の追加費用が発生することもあります。
導入に踏み切る前に、初期費用だけでなく、長期的な運用コストとリターンを可視化しておくことが重要です。費用対効果を定期的に検証し、必要に応じて利用範囲やツールを見直すことで、無駄のない運用が実現できます。
また、以下記事ではAI開発の費用相場やコストを抑えるコツについて紹介しています。あわせてご覧ください。
→ AI開発の費用相場を解説!費用を抑えるコツやおすすめの開発企業も紹介 – トッパジャパン株式会社
注意点3. 誤情報を出力することがある
生成AIは、自然な文章を生成できる一方で、誤った情報を提示すること(ハルシネーション)があります。これはプロンプトのあいまいさや学習データの偏りなどが原因で発生します。
誤出力をそのまま業務に使うと、顧客や取引先への誤情報発信につながるため、非常に危険です。AIが生成した内容をそのまま採用するのではなく、必ず人間のチェックを挟む運用体制が求められます。
特に、社外への公開資料や公式発表、顧客対応などに利用する場合は、出力内容のファクトチェックを徹底しましょう。生成AIの出力は、一次情報ではなくたたき台として活用する前提での運用が重要です。
生成AIの導入メリット
生成AIは、単なる業務効率化のツールではありません。活用の仕方次第で、業務の質とスピードの向上、コスト削減、イノベーションの創出など、企業活動に多方面で貢献する可能性を秘めています。
ここでは、生成AIを導入することで得られる主なメリットを紹介します。
メリット1. 業務の効率化と生産性の向上
生成AIは、日々の業務で発生するルーティン作業やドキュメント作成を自動化・高速化できます。たとえば以下のような場面で力を発揮します。
- メールや議事録の自動生成
- 長文の要約・リライト
- よくある質問への自動応答(チャットボット)
- 商品説明文やブログ記事の作成支援
ルーティンワークを生成AIに任せることで、社員は本来注力すべき業務や戦略的なタスクに時間を割けるようになり、全体としての生産性が向上します。
メリット2. 創造性・アイデア発想の支援
生成AIは単なる作業代行にとどまらず、クリエイティブ領域のサポートにも優れています。たとえば、企画書のたたき台の作成や広告コピーの提案などの業務で活用可能です。
ただし、あくまでもAIが出力したものなので、コンテンツの重複や権利問題に関する確認は必須です。最後は必ず人間の目で確認しましょう。
メリット3. 人手不足への対応と教育コストの削減
少人数での業務運営を求められる中小企業やスタートアップでは、生成AIが業務を支援するツールとして機能します。たとえば、専門知識を持たないスタッフでも、AIの支援で一定レベルのアウトプットが可能になるため、教育期間の短縮や属人化の解消につながります。
そのためには、IT知識が乏しい人材でも手軽に活用できる生成AIの導入が望ましいです。
ビジネスにおける生成AIの導入事例
生成AIはすでに多くの企業で実用化が進んでおり、業種や部門を問わずさまざまな場面で活用されています。ここでは、代表的な導入事例をいくつかの分野に分けて紹介します。
【マーケティング・広告分野】コンテンツ制作の自動化とスピード向上
マーケティング業務では、広告コピーや記事作成、SNS投稿など、日々多くのコンテンツが必要です。文章生成AIや画像生成AIの活用によって、コンテンツ提案の負担軽減とスピード向上を実現できます。
たとえば、パルコでは生成AIが作成したリアルなビジュアルや音楽を活用して広告を作成し、制作プロセスを大幅に削減することに成功しています。
参考:「HAPPY HOLIDAYS広告」が、AMDアワードで「優秀賞」を受賞_PARCO
【カスタマーサポート分野】チャットボットによる自動対応の高度化
生成AIは、顧客対応業務にも大きな変化をもたらしています。従来のFAQ型チャットボットでは難しかった自然な会話対応が、生成AIの導入によって可能になりました。
生成AIがユーザーの質問意図を判断し自動で回答することで、対応精度の向上とオペレーターの負担軽減を実現しています。
イギリスの個人顧客および法人向けに銀行サービスを提供するNatWestグループは、IT大手のIBMと提携し、生成AI機能を搭載した仮想アシスタントを活用しています。これにより、従業員の業務負担を軽減しつつ、 顧客対応力を向上しました。
参考:NatWestとIBM、顧客体験向上のための生成AI計画を発表_AIBase
【人事・教育分野】社内研修やスキル育成への活用
人材育成や研修の分野でも、生成AIの導入が進んでいます。AIを活用して、社員の職種やスキルレベルに応じたパーソナライズドな学習コンテンツを自動生成したり、ロールプレイ形式の面接・営業トレーニングを行ったりする事例が増えています。
たとえば、日本精工(NSK)では、ベテラン社員のノウハウをAIでマニュアル化することで、後輩社員への知識継承を実現することに成功しました。細かなコツや手順もわかりやすく文章化され、多くの社員に共有されました。
参考:NSK、過去10年分の設備保全履歴をAIで伝承可能なノウハウに_DIGITAL X
また、以下記事ではAI開発に強い企業を26社厳選しています。あわせてご覧ください。
→ AI開発に強いおすすめの企業26選!依頼前のチェックポイントや相場費用も解説 – トッパジャパン株式会社
まとめ
生成AIは、業務の効率化や人手不足の解消、クリエイティブな発想支援まで、多くのメリットをもたらす新しい技術です。すでに多くの企業がその可能性を現場で実証しています。
一方で、セキュリティ対策や誤情報への注意、導入・運用にかかるコストなど、適切な導入と運用ルールの整備が不可欠であることも事実です。だからこそ、導入目的を明確にしたうえで業務に適したツールを選定すること、継続的に効果検証を行うことが重要です。
今後、生成AIは単なる業務支援ツールにとどまらず、企業の競争力そのものを左右する存在となっていくでしょう。自社にとって最適な活用方法を見つけ、未来に向けた一歩を踏み出すための判断材料として、本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
また、業務における生成AIの導入なら、トッパジャパンにお任せください。生成AIに関する豊富な知見をもとに、最適なサポートを提供いたします。
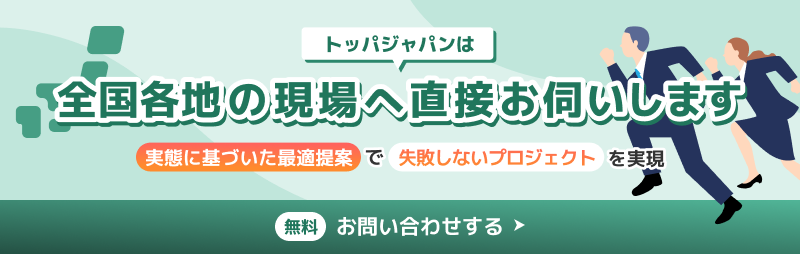
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説