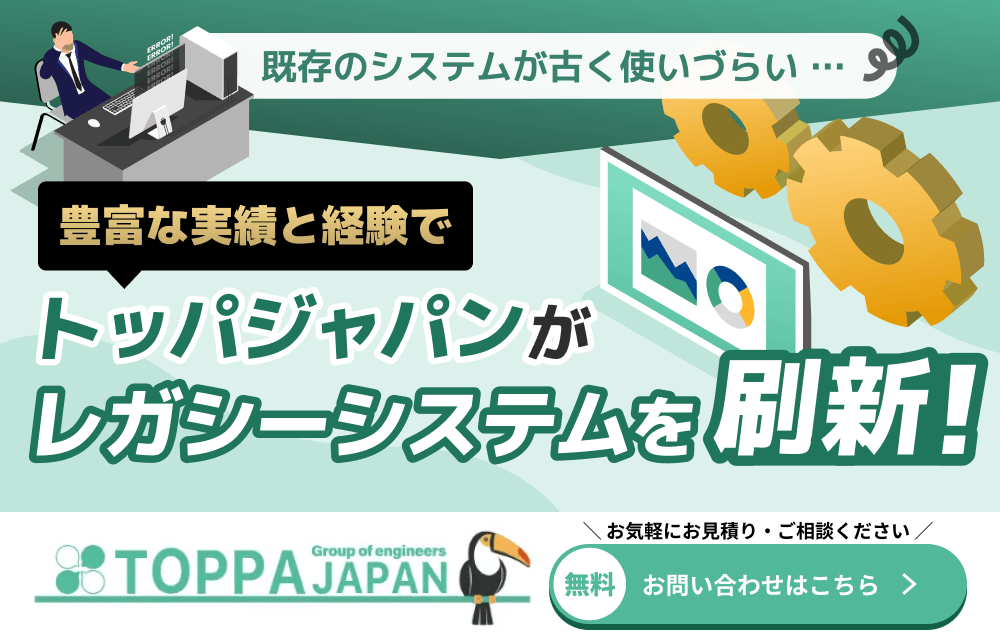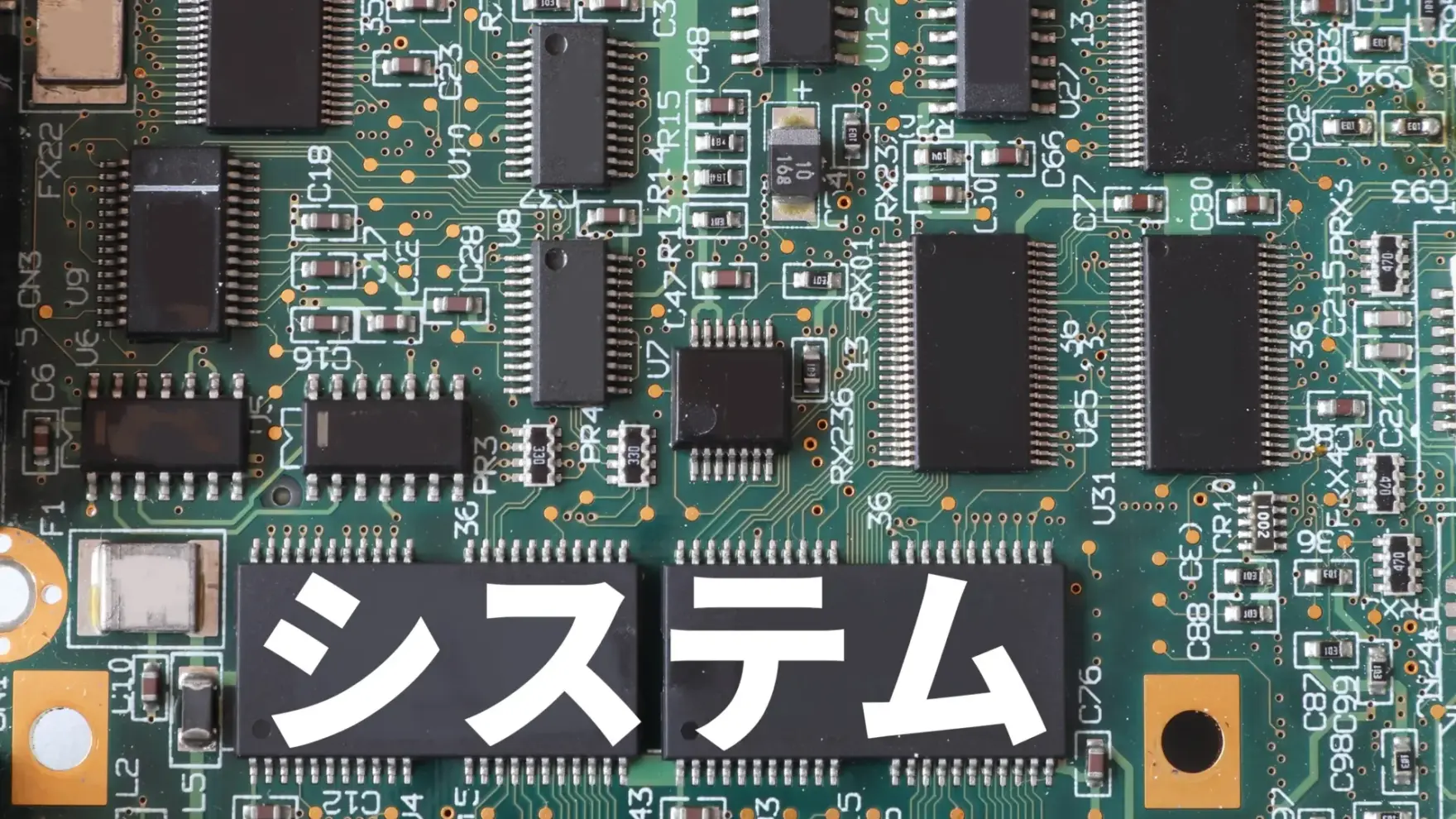
DX推進が叫ばれる一方、多くの企業で「レガシーシステム」がその足かせとなっています。
自社にも該当するシステムがあるかもしれないが、「具体的にどれが危険なのか」「放置するとどうなるのか」が分からず、対策に踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、まず「自社のシステムは大丈夫?」とチェックできるよう、7つの具体的なレガシーシステムの例と問題点を解説します。
さらに、刷新に成功した企業の事例や、失敗しないための最初の3ステップ、そして「モダナイゼーション」との違いといった基礎知識まで解説します。
自社のシステムの現状に少しでも不安を感じている情報システム担当者必見の内容です。
この記事を読み、リスクを自分ごととして捉え、レガシーシステム脱却に向けた最初の一歩を踏み出すきっかけにしてください。
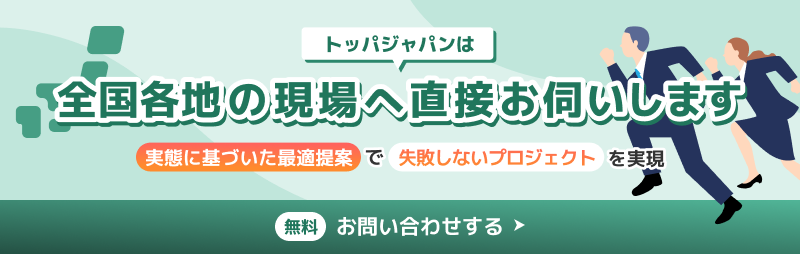
レガシーシステムの具体例と問題点7選
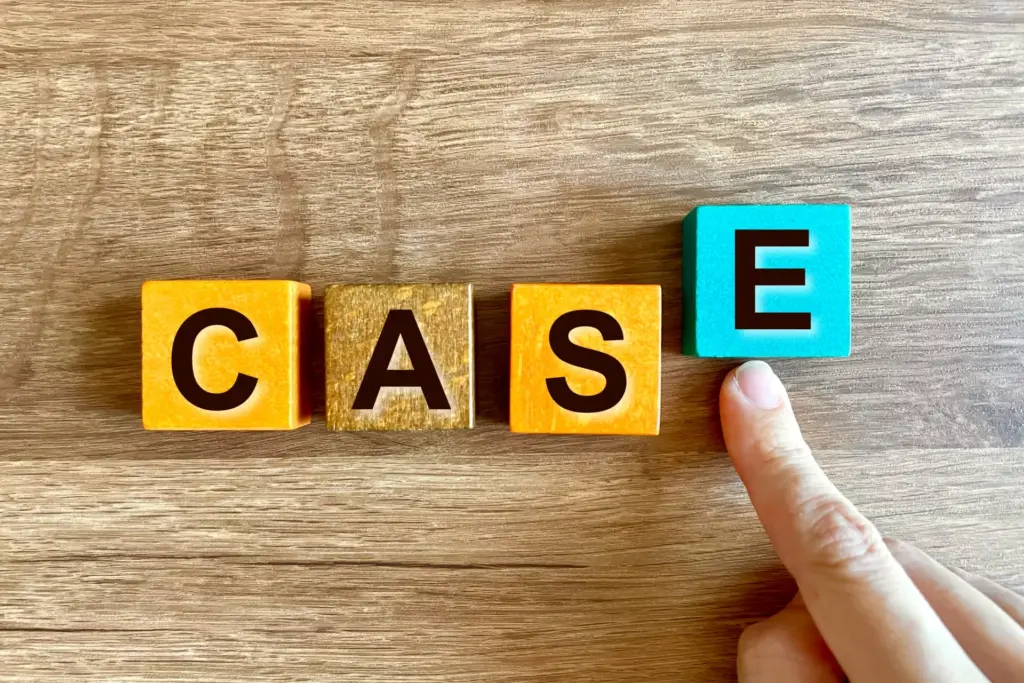
「レガシーシステム」と言われても、具体的にどのようなものが当てはまるのか、ピンとこない方も多いのではないでしょうか。
実は、多くの企業が知らず知らずのうちにレガシーシステムを使い続けており、それがDX推進の足かせとなっています。
本章では、自社の状況をチェックできるように、レガシーシステムの代表的な7つの例とその問題点を具体的に解説します。
一つでも当てはまるものがあれば、それはシステム刷新を検討するサインかもしれません。ぜひ、自社のシステムと照らし合わせながら読み進めてみてください。
例1:メインフレーム・オフコンで稼働する基幹システム
1つ目の例は、メインフレーム・オフコン(オフィスコンピューター)で稼働する基幹システムです。
【主な問題点】
- 最新技術との連携が難しい
- クラウド化に対応できない
- システムが肥大化・複雑化している
- メーカーのサポートが終了しつつある
1980年代以降に企業の基幹業務を支えてきた大型コンピュータは、レガシーシステムの典型例です。
最新のクラウドサービスなどとの連携が難しく、時代に合わせた柔軟なシステム変更が困難です。
主要メーカーのうち複数の企業が製造から撤退しており、今後ますます維持が難しくなるでしょう。
例2:COBOLで書かれた業務アプリケーション
2つ目の例として、COBOLで書かれた業務アプリケーションが挙げられます。
【主な問題点】
- 扱えるエンジニアが減少し、高齢化
- システムの保守・改修が困難
- 業務が特定の技術者に依存(属人化)
COBOLは非常に歴史の長い言語で、今も多くの企業の基幹システムで使われています。
しかし、COBOLを扱えるエンジニアの高齢化と減少が深刻で、システムの維持や改修ができる人材を確保すること自体が年々難しくなっています。
特定の担当者にしか分からない、といった属人化の温床にもなりがちです。
例3:サポートが終了したOSで動くサーバー
3つ目の例は、サポートが終了したOSで動くサーバーです。
【主な問題点】
- トラブル時にメーカーの支援がない
- 脆弱性が修正されず、非常に危険
- サイバー攻撃の標的になりやすい
サポートが切れた古いOSを使い続けることは、セキュリティ上、極めて危険です。
新たな脆弱性が発見されても修正プログラムが提供されないため、ウイルス感染や情報漏洩といったサイバー攻撃の標的になってしまいます。
例4:VB6などで作られたクライアントサーバーシステム
4つ目の例として、VB6などで作られたクライアントサーバーシステムが挙げられます。
【主な問題点】
- 開発環境のサポートが終了済み
- セキュリティ更新がなく危険
- 扱える技術者が減り、保守費用が高騰
1990年代後半から2000年代にかけて広く使われたVB6(Visual Basic 6.0)ですが、開発環境のサポートは2008年に終了しています。
セキュリティ上の問題が見つかっても修正されないため、使い続けるのは危険です。
また、COBOLと同様に扱える技術者が減っており、システムの維持管理コストが高くなっています。
例5:度重なる改修でブラックボックス化したシステム
5つ目の例は、度重なる改修でブラックボックス化したシステムです。
【主な問題点】
- システムの内部構造を把握している人がいない
- 設計書などのドキュメントがない
- 障害発生時の原因特定が困難
- 新たな改修がほぼ不可能
長い年月をかけて機能の追加や修正を繰り返した結果、内部が複雑になりすぎて、誰も全体像を把握できなくなったシステムのことです。
開発当時の担当者が退職し、設計書などの資料も残っていない場合、問題が発生しても手が出せない「アンタッチャブル」な存在になってしまいます。
ブラックボックス化したシステムが事業の足かせになることも少なくありません。
例6:他システムとデータ連携できず手入力が発生するシステム
6つ目の例は、他システムとデータ連携できず手入力が発生するシステムです。
【主な問題点】
- 最新のクラウドサービスなどと連携できない
- データの転記に手作業が発生
- 業務が非効率で、時間がかかる
- 手入力によるミス(ヒューマンエラー)が起こりやすい
古いシステムは、他のシステムとデータをやり取りすることを想定して作られていない場合があります。
その結果、あるシステムから出力したデータを、別のシステムに社員が手で入力し直す、といった非効率な作業が発生します。
こうした手作業は、時間と労力の無駄遣いになるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。
例7:マニュアルがないと操作不能な、古すぎる画面デザイン
7つ目の例は、マニュアルがないと操作不能な、古すぎる画面デザインです。
【主な問題点】
- 画面が見づらく、操作が分かりにくい
- 操作を覚えるのに時間がかかる
- 新人教育のコストが増大する
- 業務が属人化しやすい
黒い画面に文字が並ぶだけ、といった一昔前の画面デザインは、今の若い世代にとっては非常にとっつきにくいものです。
直感的な操作ができないため、新任の担当者はマニュアルとにらめっこしながら仕事を覚えることになるでしょう。
これは、教育コストの増大や業務の属人化につながります。
レガシーシステム刷新の成功事例3選
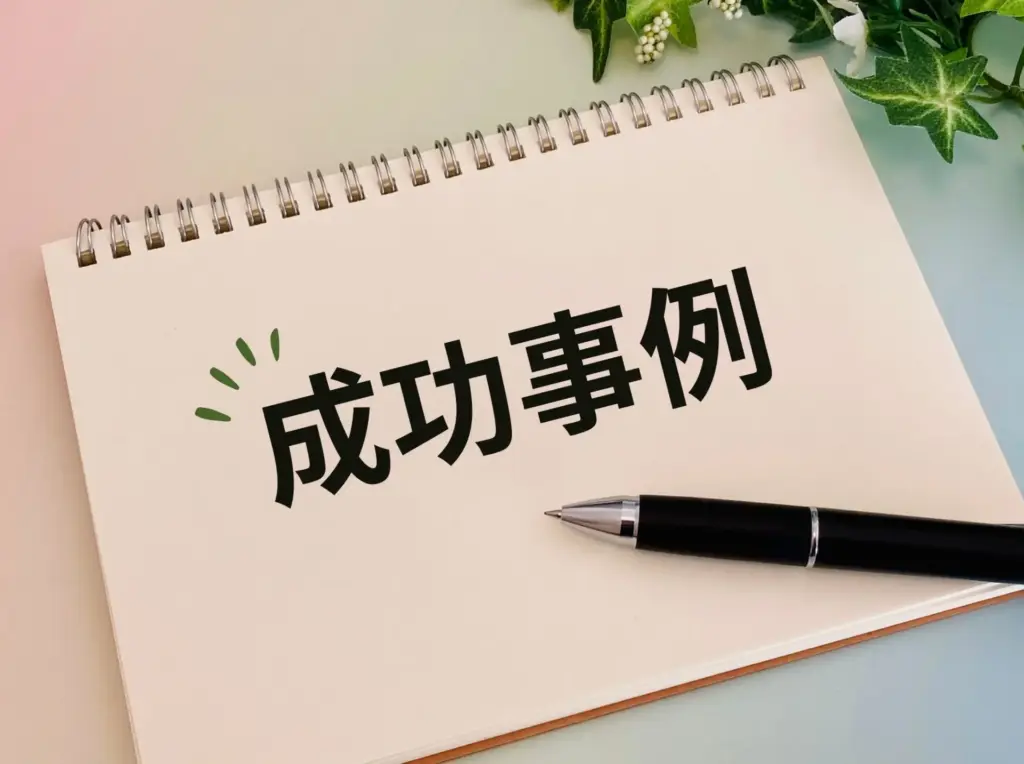
レガシーシステムの刷新には多大な労力がかかりますが、成功すれば大きな成果が期待できます。
とはいえ、他社がどのように成功したのか、具体的なイメージが湧きにくいかもしれません。
本章では、レガシーシステム刷新につながるDXに成功した3社の事例をピックアップしてご紹介します。
どのような課題を持ち、どう乗り越え、どんな成果を得たのか。自社の取り組みのヒントになるはずです。
①基幹システムの刷新により生産性が30%向上
物流業界の浜松倉庫株式会社は、時間をかけて丁寧に進めた基幹システムの刷新で、大きな成果を挙げています。
同社はまず、経営者が未来に向けた課題を提示し、従業員主体で徹底的に議論。その上で、2016年から3年がかりで基幹システムの刷新を実行しました。
結果、生産性は30%も向上し、新倉庫立ち上げに必要な人員10名を既存業務の中から捻出することに成功しています。
さらに、刷新したシステムで顧客に在庫情報をリアルタイム提供するなど、取引先の生産性向上にも貢献。経営者が短期的な成果を求めず、じっくりと現場の意見を取り入れながら改革を進めたことが成功の鍵となりました。
②モノづくりと事務のデジタル変革により年間売上が12.7億円飛躍
金属加工業の株式会社リノメタルは、「モノづくり」と「事務」の両面から会社全体のデジタル変革を行いました。
生産管理における「ミス・ムダ・属人化」を解消するため、補助金を活用しながら生産管理システムを導入。さらに、5年間で28ものクラウドサービスを導入し、事務作業も含めて徹底的に効率化を進めました。
業務効率化によって大手自動車部品メーカーからの大型受注に対応できるようになり、年間売上は12.7億円も飛躍。従業員の残業は8割減り、休日出勤はゼロになるなど、働き方改革にもつながっています。
経営トップの強いリーダーシップと、「70点で動き出す」というスピード感が成功をもたらしました。
③DXの推進により年間約8,800時間の工数削減
不動産業の株式会社トーシンパートナーズホールディングスは、現場主導のDX推進で大きな業務効率化を達成しています。
2021年に社内に「DX推進組織」を設置し、社員のデジタルスキル向上を支援。特筆すべきは、専門家でなくても業務アプリを開発できる「ノーコードツール」を全社員に展開したことです。
この取り組みにより、IT部門任せではなく、現場の従業員が自らの手で業務改善を進める文化が醸成されました。
結果として、グループ全体で年間約8,800時間もの工数削減に成功しています。
現場一人ひとりを巻き込み、ボトムアップでDXを進める体制を構築したことが、大きな成果につながったのです。
出典:PRTIMES「トーシンパートナーズホールディングスが「DXセレクション2024」において準グランプリを受賞」
レガシーシステム脱却に向けた失敗しないための最初の3ステップ

自社の古いシステムを何とかしたいと思っても、どこから手をつければ良いか分からず、途方に暮れていませんか。
レガシーシステムの刷新は、やみくもに進めると失敗するリスクが高いプロジェクトです。
本章では、失敗を避けるための「最初の3ステップ」を具体的に解説します。 このステップを踏むことで、プロジェクトの方向性が明確になり、着実にレガシーシステムからの脱却を進めることができるでしょう。
Step1:現状把握
最初のステップは、現状把握です。まずは自社がどのようなシステムを抱えているのかを正確に知ることから始めましょう。
【現状把握でやるべきこと】
- 社内の全システムをリストアップする
- 各システムの役割や関連性を整理
- 老朽度や重要度で優先順位をつける
どんなシステムが稼働しているのか、他のシステムとどう連携しているのか、まずは全体像を明らかにしましょう。
その上で、ビジネスへの影響度やシステムの古さなどを評価し、限られた予算の中でどこから手をつけるべきか、優先順位を決めることが重要です。
Step2:目的設定
次のステップは、目的設定です。「何のためにシステムを新しくするのか」というゴールを明確にします。
【目的設定で決めること】
- なぜシステムを刷新するのか
- 新しいシステムで何を実現したいか
- 理想の業務フロー(To-Be)を描く
単に古くなったから新しくする、では不十分です。
「処理速度を上げて業務を効率化したい」「運用コストを削減したい」など、具体的な改善目標を設定しましょう。
経営戦略とIT戦略を結びつけ、新しいシステムがビジネスにどう貢献するのかを明らかにすることが、社内の合意形成にもつながります。
Step3:情報収集
最後のステップとして、設定した目的を達成するための情報収集を行います。
【収集すべき情報】
- 経済産業省などの公的なガイドライン
- 最新の技術動向や刷新の手法
- 信頼できるベンダー企業の成功事例
社内の状況が整理できたら、次は外部の知見を活用しましょう。
レガシーシステムを刷新するには、クラウド移行や再構築など様々な手法があります。
他社の成功事例を参考にしたり、信頼できるベンダー企業に相談したりしながら、自社に最適なアプローチを見つけ出すことが成功への近道です。
そもそもレガシーシステムとは?わかりやすく解説

ここまでレガシーシステムの刷新について解説してきましたが、そもそも「レガシーシステム」とは具体的に何を指すのでしょうか。
一言で言えば、古い技術や仕組みで作られ、現代のビジネス環境に対応できなくなった既存システムのことです。
【レガシーシステムによくある特徴】
- 導入から長年が経過し、老朽化している
- 特定の担当者しか分からない(ブラックボックス化)
- 最新のIT技術や他システムと連携できない
- 維持・管理コストが高い
1980年代頃に導入されたメインフレームや、COBOLという古い言語で作られた基幹システムなどがレガシーシステムの典型例です。
長年の業務を支えてきた反面、度重なる改修で複雑化し、ビジネスの変化に柔軟に対応できなくなっています。
経済産業省も「2025年の崖」として、放置すれば大きな経済損失を生むと警鐘を鳴らしています。
モダナイゼーション・マイグレーションの違い
レガシーシステムから脱却する方法として、「マイグレーション」と「モダナイゼーション」という言葉がよく使われますが、両者はアプローチが異なります。
簡単に言えば、マイグレーションはシステムをそのまま新しい環境へ「引っ越し」させるイメージ。
一方、モダナイゼーションはシステムそのものを「リフォーム(改革)」するイメージです。
| 項目 | マイグレーション(移行) | モダナイゼーション(近代化) |
| アプローチ | 既存システムを活かし、実行基盤を新しくする | システムの構造や機能自体を見直し、再構築する |
| メリット | 短期間・低コストで実施可能 | ビジネスの変化に柔軟に対応できる |
| デメリット | システムの根本的な課題は残る | 時間とコストがかかる傾向 |
| 目的の例 | オンプレミスからクラウドへの移行 | DX推進、新サービスの創出 |
どちらが良いというわけではなく、自社の目的によって適切な手法を選ぶことが重要です。
例えば、まずはマイグレーションでインフラだけを新しくし、その後で段階的にモダナイゼーションを進める、といった戦略も考えられます。
まとめ
本記事では、メインフレームやCOBOLといった7つの具体例を挙げ、レガシーシステムが抱えるリスクを解説しました。
レガシーシステムの放置はDXを妨げるだけでなく、大きな経営リスクにつながります。
「2025年の崖」という言葉に代表されるように、レガシーシステムへの対応はもはや待ったなしの状況です。
この記事を参考に、まずは自社のシステムがレガシーシステムに該当しないか「現状把握」から始めてみましょう。
もし自社だけでの推進が難しいと感じたら、専門知識を持つパートナーに相談するのも有効です。
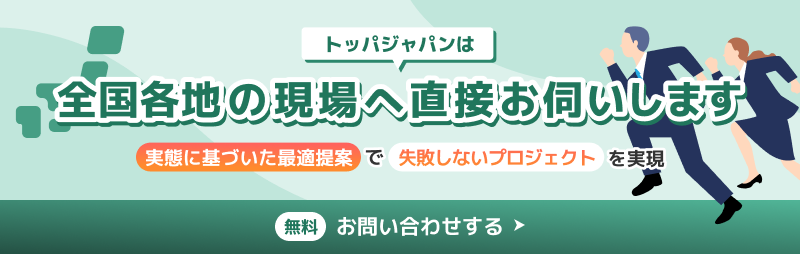
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説