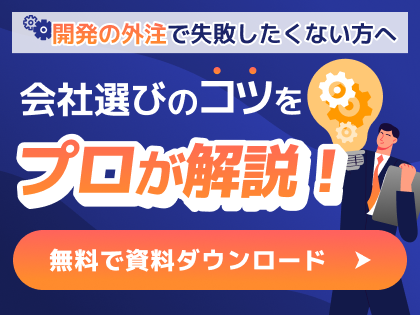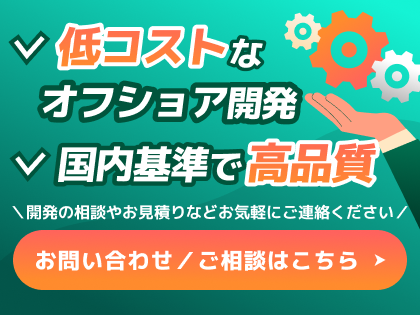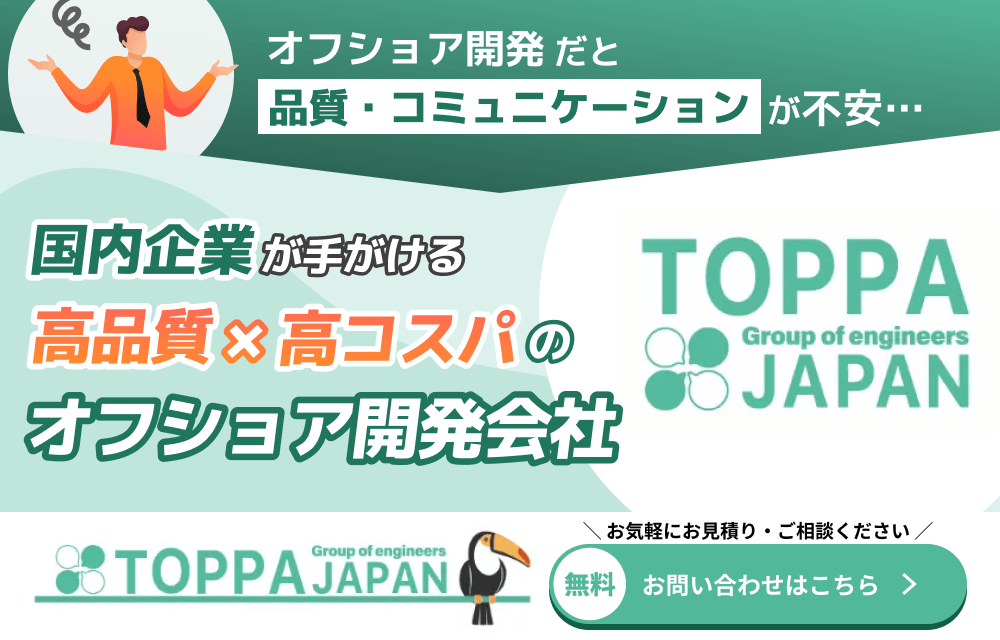人手不足や国際競争の激化に直面する日本の製造業にとって、DXは生産性を向上させ、競争力を維持するために不可欠な経営課題です。
しかし、多くの企業が「何から手をつければ良いのか分からない」「思うように進まない」といった悩みを抱えているのが現状ではないでしょうか。
本記事では、まず製造業のDXが進まない5つの根本的な課題を深掘りし、それを乗り越えた企業の成功事例を紹介します。
さらに、生産管理から製品開発まで、DX化できる業務と期待される効果、成功に導くためのポイントや具体的な5つのステップ、活用できる補助金制度まで解説します。
自社のDX推進に課題を感じている経営者や現場の担当者にこそ、ぜひお読みいただきたい内容です。
なぜ製造業のDXは進まないのか?製造業が直面する5つの課題
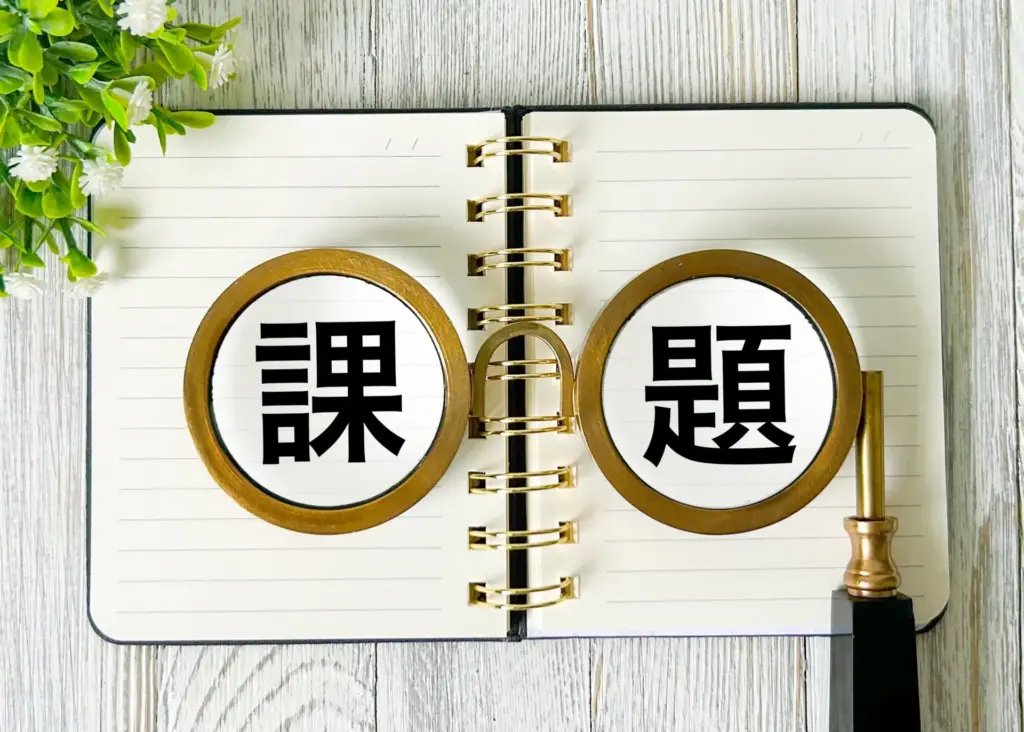
製造業のDX推進が、思うように進まないと感じていませんか。
その背景には、技術導入の問題だけではなく、組織の文化からシステム・人材に至るまで、製造業特有の課題があります。
- 現場の抵抗感
- IT人材の不足
- 経営層の理解不足
- 予算の制約
- 既存システムとの統合の難しさ
上記は、多くの製造業が直面するDX推進の壁です。本章では、この5つの壁について、その実態を解説していきます。
①現場の抵抗感
DX推進が難航する理由として、製造現場からの抵抗感が挙げられます。長年かけて築き上げてきた仕事のやり方を変えることへの反発が、ブレーキとなってしまうのです。
【現場の抵抗感が生じる理由】
- 伝統的な作業手法への強いこだわり
- 新しいやり方への漠然とした不安
- システム導入に伴う業務変化への戸惑い
このような反発を乗り越えるには、現場目線で効果を実感できる小さな成功体験を共有したり、説明会や研修で不安を解消したりといった地道なアプローチが欠かせないでしょう。
②IT人材の不足
IT人材の不足も、製造業のDX推進を妨げる要因といえるでしょう。DXを主導できる専門的なスキルを持つ人材が、量と質の両面で足りていないのが現状です。
【IT人材不足の現状】
- DXを計画・推進できる専門家がいない
- 現在の従業員のスキル育成が追いつかない
- 人材不足は将来さらに深刻化する見込み
社内での育成体制を強化したり、外部の専門家をうまく活用したりする柔軟な対策が求められます。
③経営層の理解不足
経営層のDXに対する理解不足が、推進の大きな壁となっているケースも少なくありません。トップの合意が得られなければ、全社的な改革は進まないからです。
【経営層の理解不足が招く問題】
- DXの真の価値や効果が伝わっていない
- 積極的な投資や組織的な支援が行われない
- 全社を動かすリーダーシップが発揮されない
経営者自らがDXの必要性を実感し、主体的に関与する必要があるでしょう。
④予算の制約
DX推進を阻む現実的な問題として、予算の制約が挙げられます。新しいシステム導入や人材育成には相応のコストがかかるため、多くの企業にとって高いハードルとなっています。
【予算の制約に関する課題】
- システム導入などに多額の初期費用がかかる
- IT予算の大半が既存システムの維持費に
- 費用対効果が見えにくく投資判断しにくい
成果が出るまでに時間がかかるDXへの投資は、短期的に費用対効果が見えにくく、経営者の決断を鈍らせる要因にもなっています。
国や自治体が提供する補助金制度を利用したり、小さな規模から始めて効果を検証したりする工夫が必要でしょう。
⑤既存システムとの統合の難しさ
多くの製造業では、長年使い続けてきた「レガシーシステム」と呼ばれる古い仕組みが、DX推進の足かせとなっています。この既存システムとの統合が、想像以上に難しいのです。
【既存システムが抱える問題点】
- 部門ごとにシステムが孤立している(サイロ化)
- 全社的なデータ連携や活用が困難
- システムの内部構造がブラックボックス化
製造現場では、生産や品質管理・在庫管理といった部門ごとに最適化された古いシステムが、今もそのまま稼働していることがあります。
システムの内部は複雑でブラックボックス化し、詳しい担当者も退職しているため、安易に手を加えることすらできません。
この深刻な問題は「2025年の崖」とも呼ばれ、このまま放置すれば将来、日本全体で莫大な経済損失を生むとまで警告されています。
古い仕組みから脱却し、新しい技術とつなぐための基盤を整備することが急務といえるでしょう。
出典:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」
製造業のDX成功例3選

DXというと少し難しく聞こえるかもしれませんが、実は身近な業務の改善からでも大きな成果が生まれています。
この章では、製造業におけるDXの具体的な成功例として、以下の3つをご紹介します。
- 生産管理システムの見える化
- 進捗状況の見える化
- データの一元管理
成功例を知ることで、自社でDXを進める際のヒントが見つかるはずです。
①生産管理システムの見える化
日東電機製作所の生産管理システムの見える化は、業務のムダを発見し、改善につなげるDXの代表的な成功例です。
【生産管理の見える化による効果】
- 工程のムダや問題点を発見できる
- 生産計画や不良品管理の精度や効率が向上する
- リアルタイムで進捗を把握しすぐ対処できる
生産に関する情報をデータとして客観的に見ることで、これまで気づかなかった課題が明らかになります。
②進捗状況の見える化
永井製作所の進捗状況の見える化は、トラブルへの迅速な対応や納期遅延の防止に直結する取り組みです。
【進捗状況の見える化がもたらす変化】
- トラブル発生時にすぐ対応できる
- 納期遅延のリスクを事前に察知できる
- 非効率な工程(ボトルネック)を特定できる
生産ラインの進み具合をリアルタイムで把握できれば、作業の遅れにもすぐ気づけます。
作業の遅れに応じて人員配置を柔軟に調整することで、効率的な作業体制を組むことも可能です。
③データの一元管理
NISSYOでは、データの一元管理によって、部門の壁を越えた情報活用と迅速な意思決定が実現しました。
【データ一元管理のメリット】
- 製造プロセス全体をまとめて分析可能
- 部門間のスムーズな情報連携
- 経営層から現場まで迅速な意思決定
工場の設備稼働状況から出荷までのデータを一つにまとめれば、プロセス全体を見渡した分析ができます。
製造業でDX化できる業務事例と効果

DXは、製造現場のさまざまな業務を効率化し、新たな価値を生み出す力を持っています。
ここでは、5つの業務領域でDXがどのように活用され、どのような効果を発揮するのかを具体的に見ていきましょう。
- 生産管理・効率化
- 品質管理
- 在庫・物流管理
- 技能伝承
- 製品設計・開発
自社の課題に近い事例を通じて、DX導入の具体的なイメージをつかんでみてください。
生産管理・効率化
生産管理の領域では、DXによって手作業を自動化し、生産性を大きく向上させます。
【生産管理DXの効果】
- 手作業の自動化で工数を大幅に削減
- 品質のばらつきや人為的ミスを防止
- 重要な業務へ人材を再配置できる
これまで人が行っていた作業をAIやIoTに置き換えることで品質は安定し、人件費の削減にもつながります。紙やExcelでの管理をやめて、データを自動で集める仕組みを作れば、ヒューマンエラーも減らせます。
品質管理
品質管理の分野において、DXは不良品の発生を未然に防ぎ、品質レベルの向上に貢献します。
【品質管理DXの効果】
- AIによる不良品の自動検査
- センサーで設備の不調を事前に予測
- 品質データを分析し継続的な改善へ
生産ラインをリアルタイムで監視し、問題が起こる前に検知して対処する、といった取り組みが進んでいます。蓄積された品質データを分析することで製造工程そのものを見直し、さらなる品質向上につなげることも可能です。
在庫・物流管理
在庫・物流管理にDXを導入すれば、ムダをなくし、業務効率を改善します。
【在庫・物流DXの効果】
- 部品の捜索や棚卸作業の時間を大幅短縮
- 過剰在庫や欠品による損失を防ぐ
- リアルタイムな情報共有で発注業務も効率化
RFIDタグ(無線通信でデータを読み取れる識別タグ)を使えば、入出庫の処理は自動化され、在庫状況はいつでも正確に把握できます。
技能伝承
技能伝承の領域では、DXが熟練者の貴重な技術をデータとして残し、人材育成を効率化します。
【技能伝承領域でのDXの効果】
- 技術を分かりやすく伝える動画マニュアル
- VR/AR技術で安全な実地訓練を実現
- 属人化していたノウハウを組織の財産に
紙の手順書を動画に変えるだけで、若手技術者は熟練の技を正確に学べます。
また、VR(仮想現実)を使えば、危険な現場に立ち会うことなく、安全な環境で作業の訓練ができます。
製品設計・開発
製品設計・開発の分野では、DXが開発サイクルの短縮と品質向上を両立させます。
【製品設計・開発DXの効果】
- AI活用で設計にかかる期間を大幅短縮
- 開発から生産までデータを連携し業務を効率化
- 仮想空間での事前検証でリスクを低減
仮想空間に工場を再現する「デジタルツイン」という技術で、新しい生産ラインを導入する前に問題点を確認する、といった活用も進んでいます。
製造業でDXを実現するためのポイント

DXを成功させるためには、やみくもに進めるのではなく、押さえるべきポイントがあります。 この章では、製造業でDXを実現するために欠かせない3つのポイントを解説します。
- ポイント1. 現状分析と課題の可視化
- ポイント2. 段階的な導入と小規模な試行
- ポイント3. 経営層と現場の連携
これらのポイントを意識し、DXプロジェクトが失敗するリスクを減らしましょう。
ポイント1. 現状分析と課題の可視化
DX成功のポイント、1つ目は「現状分析と課題の可視化」です。DXは、まず自社の現状を正しく知ることから始まります。
【現状分析と課題の可視化】
- 自社の業務プロセスを正確に分析する
- 解決すべき課題を洗い出し社内で共有する
- DXの目的と優先順位を明確にする
DXを始めるにあたり、まずは自社の業務や現場の問題点を洗い出すことが大切です。どこに課題があるのかを関係者全員で共有することで、「何のためにDXをやるのか」という目的がはっきりします。
ポイント2. 段階的な導入と小規模な試行
成功のポイント、2つ目は「段階的な導入と小規模な試行」です。いきなり全体に導入するのではなく、小さく始めるのが成功のコツです。
【段階的な導入と小規模な試行】
- まず特定の工程で試してみる(スモールスタート)
- 効果を確認してから全体に広げる
- 現場の反発や失敗のリスクを低くする
例えば、まずは一部の生産ラインだけで実証実験を行い、うまくいけば他のラインにも展開していく、という進め方が一般的です。スモールスタートで効果があるか検証してから全体へ導入する方が、失敗のリスクは小さく、現場の反発や不安感を徐々に取り払うことも可能です。
小さな成功体験を積み重ねることが、現場の協力を得てDXを定着させるポイントとなります。
ポイント3. 経営層と現場の連携
成功のポイント3つ目は「経営層と現場の連携」です。DXは、経営層と現場の共通認識がなければ決してうまくいきません。
【経営層と現場の連携】
- 経営層がリーダーシップを発揮する
- 現場の意見を吸い上げ、巻き込む
- 部門の垣根を越えたチームを作る
経営陣が旗を振り、現場のスタッフと一体となって進める体制が理想的です。
経営、IT、製造といった各部門からメンバーを集めた横断的なチームを作り、進捗をこまめに確認しながら進めていくことが重要です。
製造業におけるDXの進め方
DXを成功させるためのポイントを押さえたら、次はいよいよ具体的な進め方です。どのような手順でプロジェクトを動かしていけば良いのでしょうか。
ここでは、計画から実行、改善までの5つのステップを解説します。
| ステップ | 詳細 | ポイント |
| ①現状分析と課題の可視化 | 現在の業務プロセスやシステムを分析し、解決すべき課題を洗い出す | まずは自社の現在地を正確に把握する |
| ②目標設定とDX戦略の立案 | 「何を」「いつまでに」「どのレベルまで」達成するのかを具体的に決める | 具体的な目標(KPI)と計画を立てる |
| ③技術導入 | 課題解決に最適なデジタル技術やツールを選択し導入する | IT部門と現場担当者でチームを組むと、現場の声を反映しやすい |
| ④全体展開とプロセス最適化 | 小さな範囲で試行し、効果が確認できたら適用範囲を広げる | スモールスタートでリスクを抑える |
| ⑤評価と改善の継続 | 導入後も定期的に成果を評価し、改善を続ける | PDCAサイクルを回し続ける |
このステップに沿って進めることで、自社におけるDXプロジェクトを着実に推進することが可能になります。
製造業のDXで使える補助金
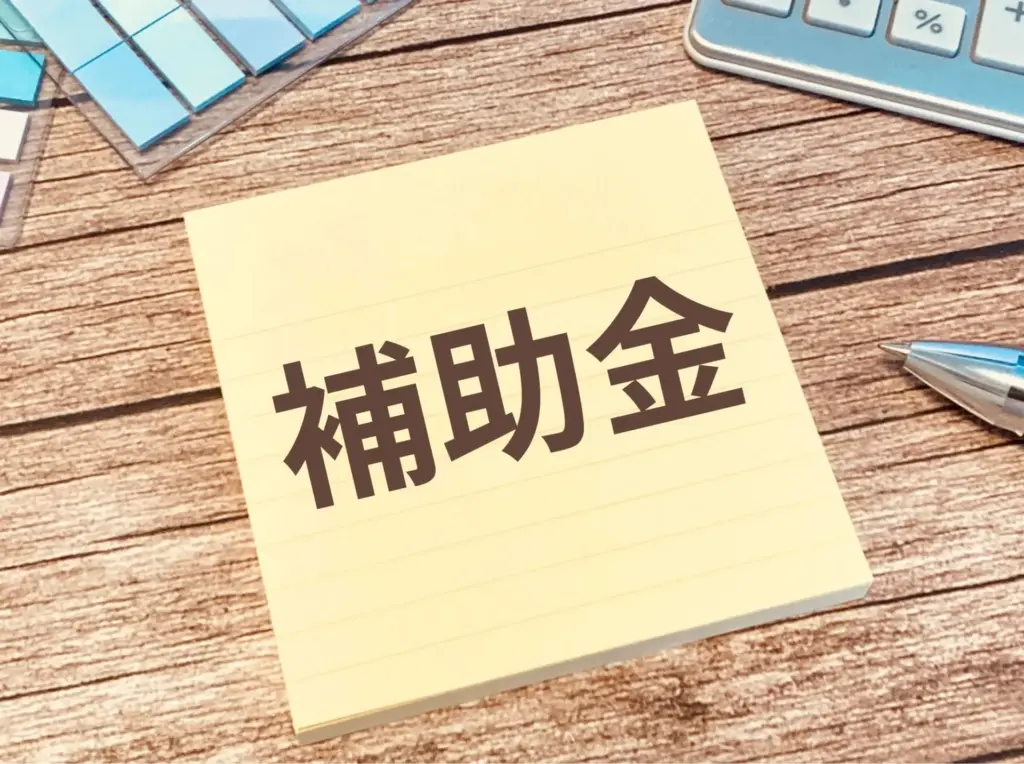
DXを進めたいけれど、やはり気になるのはコストの問題でしょう。
実は、国は中小企業のDXを後押しするため、さまざまな補助金制度を用意しています。
この章では、製造業がDXを推進する際に活用できる代表的な3つの補助金、「IT導入補助金」「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」について、それぞれの特徴や対象を解説します。
IT導入補助金
IT導入補助金は、業務効率化やDX推進のためにITツールを導入する際に、その費用の一部を支援してくれる制度です。
| 項目 | 内容 |
| 目的 | 業務効率化・DXのためのITツール導入 |
| 対象者 | 中小企業・小規模事業者など |
| 対象経費 | 会計ソフト、クラウドサービス、PC、レジなど |
| 補助上限額 | 最大450万円(通常枠の場合) |
| 補助率 | 原則1/2(特例あり) |
この補助金の特徴は、事務局に登録されたソフトウェアやクラウドサービスが対象となる点です。インボイス対応のための安価なツールの導入も支援しており、小規模事業者であれば最大で費用の4/5が補助される手厚い枠もあります。
出典:IT導入補助金2025
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、新しい製品やサービスの開発、生産性向上のための設備投資など、より踏み込んだ取り組みを後押ししてくれます。
| 項目 | 内容 |
| 目的 | 革新的な製品・サービス開発、設備投資など |
| 対象者 | 中小企業・小規模事業者など |
| 対象経費 | 設備投資、システム導入費用など |
| 補助上限額 | 最大2,500万円(枠や従業員数による) |
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模事業者2/3 |
積極的に従業員の賃上げに取り組む企業に対しては、補助の上限額が上乗せされるといった優遇措置も用意されています。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓など、事業を継続・発展させるための幅広い取り組みを支援する制度です。
| 項目 | 内容 |
| 目的 | 販路開拓、生産性向上 |
| 対象者 | 小規模事業者(製造業は従業員20人以下) |
| 対象経費 | 広告宣伝、ECサイト構築、機械設備導入など |
| 補助上限額 | 50万円(特例で最大250万円) |
| 補助率 | 原則2/3(特例あり) |
ECサイトの構築や業務効率化のための機械導入など、DXに関連する経費も対象になります。
申請にあたっては、商工会や商工会議所とともに経営計画書を作成する必要がある点も、この補助金の特徴です。
出典:小規模事業者持続化補助金
製造業のDX化ならトッパジャパンに相談を

製造業のDX推進で、「高度なスキルを持つIT人材がいない」「開発コストは抑えたい」「システムの保守まで手が回らない」といった課題はありませんか。
トッパジャパンは、ベトナムの優秀なエンジニアチームを活用した「ラボ型開発サービス」で、そうしたお悩みを解決します。AIやVRなど日本で確保が難しい専門家も、層の厚いベトナムならアサイン可能です。
お客様専任のチームが長期的にプロジェクトを支援するため、まるで自社の社員のようにノウハウを蓄積できます。月単位での柔軟な依頼や1名からのスモールスタートにも対応しており、長期であればあるほどオフショア開発のコストメリットが大きくなります。
オフショア開発に不安がある企業でも、日本人スタッフや日本語堪能なブリッジSEが円滑なコミュニケーションを徹底的にサポートできますので、お気軽にお問い合わせください。
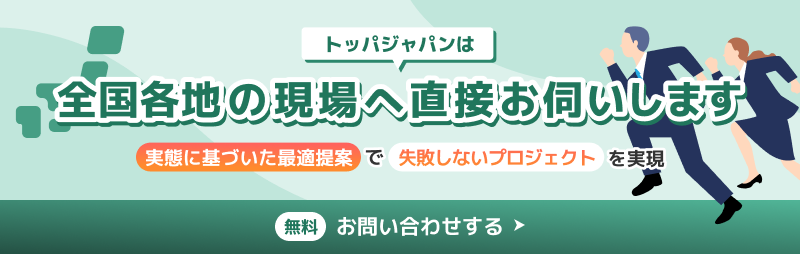
まとめ
DXは、もはや避けては通れない経営課題です。しかし、これらの課題を自社の人材だけで乗り越えるのは容易ではありません。
特に、DX推進のカギとなるIT人材の確保や、コストを抑えながら開発を進めるには、外部の専門家の力を借りることが有効です。
この記事で得た知識をもとに、まずは自社の課題を改めて整理し、具体的な計画を立ててみましょう。
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説