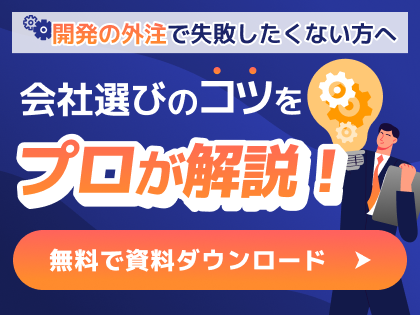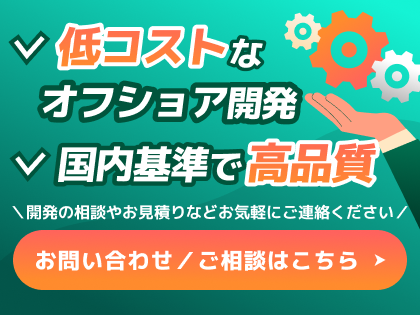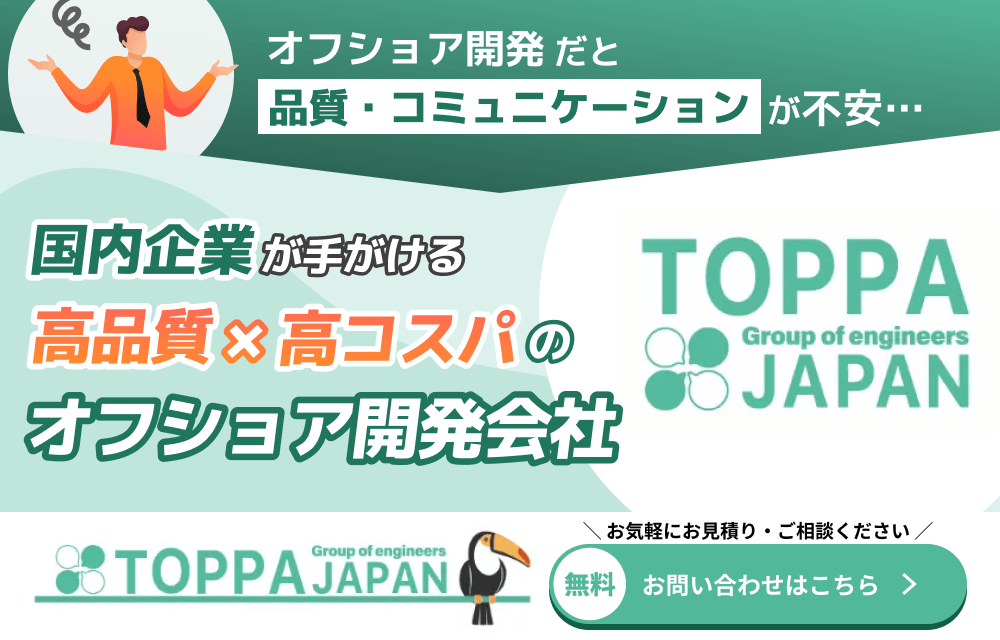システム開発における人材不足とコスト高騰が深刻化する中、その解決策としてオフショア開発が注目を集めています。
本記事では、オフショア開発の基本的な概念と、ラボ型・受託型の2つのサービス形態について解説します。さらに、おすすめのオフショア開発会社9社を、開発領域の幅広さ、日本企業との取引実績、エンジニアの能力、コミュニケーション体制などの観点から厳選して紹介します。
システム開発の外部委託を検討している企業の経営者や、開発担当の方々にぜひ参考にしていただき、自社に最適なオフショア開発会社の選定にお役立てください。
オフショア開発会社とは

オフショア開発会社とは、海外の開発拠点でシステム開発やITサービスを提供する企業です。主にコストの削減と開発リソースの確保を目的に、多くの企業が利用を始めています。
提供形態は主にラボ型と受託型の2つです。
- ラボ型:お客様専用の開発チームを編成し、お客様主導で開発を進める方式
- 受託型:要望に応じて開発を行い、成果物を納品する方式
自社で海外に開発拠点を設けることも可能ですが、拠点の構築や人材の採用・教育に多額の費用がかかります。そのため、すでに体制が整っているオフショア開発会社に委託するケースが増えています。
また、以下の記事ではオフショア開発について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発とは?メリット・デメリットや失敗例・おすすめの開発企業も紹介 – トッパジャパン株式会社
オフショア開発会社に依頼する前に自社で取り組むべきこと
プロジェクトの成功率を高めるには、オフショア開発会社への依頼前の準備が重要です。特に開発目的の明確化と具体的な依頼内容の決定は、期待通りの成果を得るための必須条件となります。
開発に関わる予算や機能要件、必要なサポート、納期などを具体的に定め、優先順位をつけることで、最適なオフショア開発会社の選定が可能です。
開発目的と目標を明確化する
開発目的とゴールの明確化は、プロジェクトの成否を分ける重要なポイントです。オフショア開発会社には、基幹システム開発に強みを持つ会社や、モバイルアプリ開発を得意とする会社など、それぞれ異なる専門性があります。
開発の目的やゴールが不明確なまま依頼すると、認識のズレが生じ、求めていた成果物が完成しないリスクがあります。会社選定の際は、目的に合った技術力や実績があるかを十分確認しましょう。
また、以下の記事では国別のオフショア開発の平均コストや開発力について比較・紹介しています。オフショア開発の依頼国で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社
依頼内容を具体的に決める
オフショア開発を成功に導くには、具体的な依頼内容を明確にすることが重要です。
| 項目 | 内容 | 確認ポイント |
| 予算 | 開発にかけられるコストを決める | 追加開発や運用サポートの必要性も考慮する |
| 必要な機能 | 実装したい機能や要件を明確にする | 最低限必要な機能と、追加可能な機能を整理する |
| 開発サポート | 開発後の保守・運用サポートの有無を決定 | 継続的なサポートが必要か確認する |
| 納期とスケジュール | リリース日や開発期間を決める | 短期間開発が必要な場合、対応可能かチェック |
| 要件の優先順位 | 「納期重視」「品質重視」「予算重視」か決める | 開発会社の強みと照らし合わせる |
| 契約形態 | 「ラボ型」または「受託型」を選択 | 継続開発なら「ラボ型」、成果物納品なら「受託型」 |
依頼内容を具体的に決めることで、開発の方向性が明確になり、スムーズな進行と高品質な成果物の実現につながります。
また、以下の記事ではオフショア開発におけるよくある悩みについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発でよくある悩みとは?悩み別の対処法や成功事例も紹介 – トッパジャパン株式会社
オフショア開発会社おすすめ9選
ここでは以下の選定基準で、おすすめのオフショア開発会社を9社ピックアップしました。
【選定基準】
- 開発領域が幅広い
- 日本企業との取引実績がある
- エンジニアの能力が高いことを強みとしている
- コミュニケーションの課題解決に向けた取り組みを行っている
日本語対応力や開発品質、コストパフォーマンスなど、さまざまな観点から評価した9社を紹介します。
トッパジャパン株式会社
出典:トッパジャパン株式会社
トッパジャパンは、日本法人として、開発担当部署も日本に持っていることが強みです。多くのベトナム企業が抱える日本法人特有のデメリットやトラブルを解消し、安心して開発を任せられる体制を構築しています。
日本円での決済が可能なため、為替リスクがないことや、SEを含めたスタッフが日本語で対応できるため、コミュニケーションもスムーズです。
開発サービスの幅広さも特徴で、システム開発だけでなく、ヘルプデスクやITコンサルティング、IT導入支援まで対応。国立大学や役所など、大規模開発の実績も豊富です。
トッパジャパンと長年取引のあるベトナムの優秀な開発者でチームを編成し、独立した品質検査チームによる厳格な品質管理も実施しています。お客様の困りごとに柔軟に対応し、リピート率は80%以上になっています。
株式会社コウェル
出典:株式会社コウェル
コウェルは、ベトナムの優秀なIT人材の採用と育成に強みを持つオフショア開発企業です。
社内には専任の日本語講師を置き、全社員が日本語でビジネスコミュニケーションを取れるよう徹底した教育を実施しています。
品質面では、ソフトウェアテストについての資格認定機関「ISTQB」で、全世界11社、日本では4社のみが認定される最上位資格「Global Partner」を取得している点も特徴です。
株式会社ブライセン
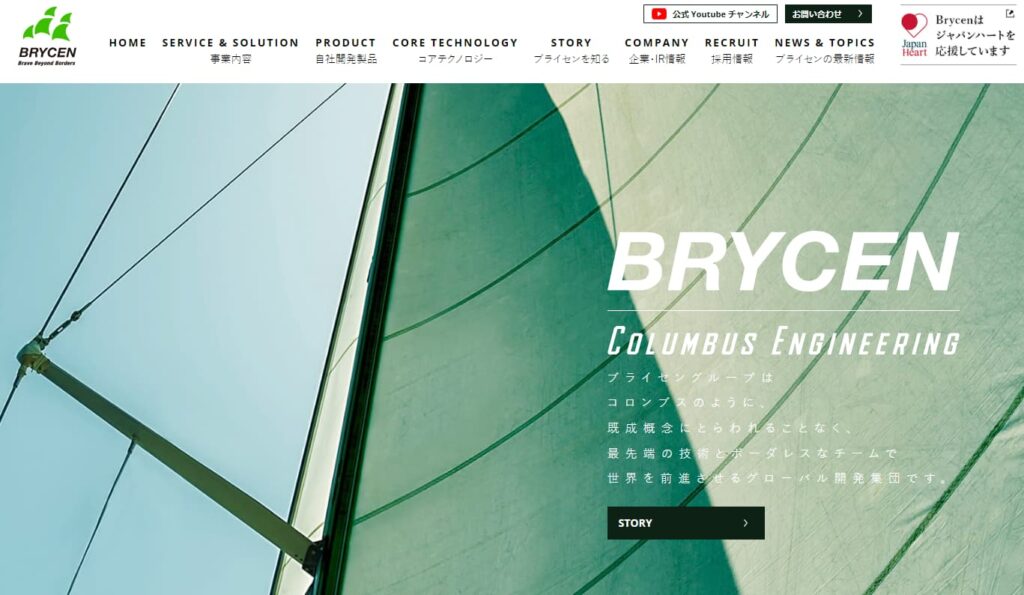
出典:株式会社ブライセン
ブライセンは1986年の設立以来、30年以上にわたりオフショア開発の経験を積み重ねてきた企業です。ベトナム・ミャンマー・韓国・カンボジアの4カ国に開発拠点を持ち、各拠点に日本品質を担保するコミュニケーターを配置しています。
特筆すべき強みは、97%という高い技術者の定着率です。これにより、開発プロジェクトの安定性と継続的なサポート体制を実現しています。また、日本と現地の両方にエンジニアを常駐させることで、高品質な開発と円滑なコミュニケーションを確保しています。
株式会社モンスターラボホールディングス

モンスターラボホールディングスは、世界20カ国・33都市にグローバル拠点を持ち、2006年の設立以来2,200件以上の開発実績を誇るデジタルコンサルティング企業です。UX/UIデザイン、システム開発、アプリ開発、ブランディングなど、企業のDXを幅広く支援しています。
オフショア開発では、日本語が話せる現地メンバーを中心に構成された開発チームが特徴です。これにより、クライアントとのコミュニケーションがスムーズで、プロジェクトを迅速に開始できる体制を整えています。
株式会社Sun Asterisk
Sun Asteriskは、日本・ベトナム・フィリピン・カンボジアの4カ国に拠点を持ち、1,000人以上のエンジニアを擁するグローバル企業です。システム開発やアプリケーション開発、UX/UIデザイン、DXコンサルティングなど、幅広いデジタルサービスを提供しています。
開発体制の特徴は、プロジェクトの初期段階から設計・開発・リリースまでをワンストップで提供する点です。日産レンタカーの公式アプリ開発や、シロカのECサイトおよびCRM構築など、多くの成功事例があります。
VNEXT JAPAN株式会社
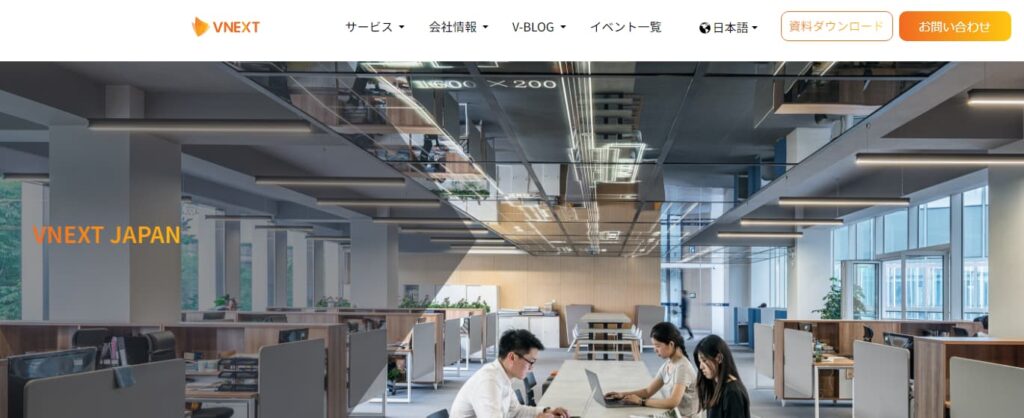
VNEXT JAPANは2017年に設立された、東京都千代田区に本社を、ベトナムに開発拠点を持つ企業です。創業以来、350社以上との取引実績を持ち、700件を超えるプロジェクトを手掛けています。
開発体制の特徴は、クライアント専用のチームを編成するラボ型オフショア開発を採用している点です。日本人のプロジェクトマネージャーが上流工程から関与し、日本国内と同等の品質を確保しつつ、コストを抑えた開発を実現しています。
サービスの幅が広く、特にAIやブロックチェーンなどの先端技術に早くから取り組み、自然言語処理やデータ解析分野で豊富な実績を持っています。
アロブリッジ有限責任会社

出典:アロブリッジ有限責任会社
アロブリッジは、ベトナム拠点の日系オフショア開発企業です。日本とベトナムの技術力を融合させ、特にスマートフォンアプリ、Webアプリ、クラウドシステムの開発に強みを持っています。
開発プロセスでは、日本基準の品質管理を徹底。プロジェクトマネージャーとブリッジエンジニアが常駐し、クライアントとの円滑なコミュニケーションを実現しています。これにより、言語や文化の違いによる誤解を最小限に抑えています。
オフショア開発が初めての企業向けにトライアルプランも用意しており、優秀なベトナム人エンジニアによる低コストで高品質な開発を、安心して依頼できる体制を整えています。
株式会社Core
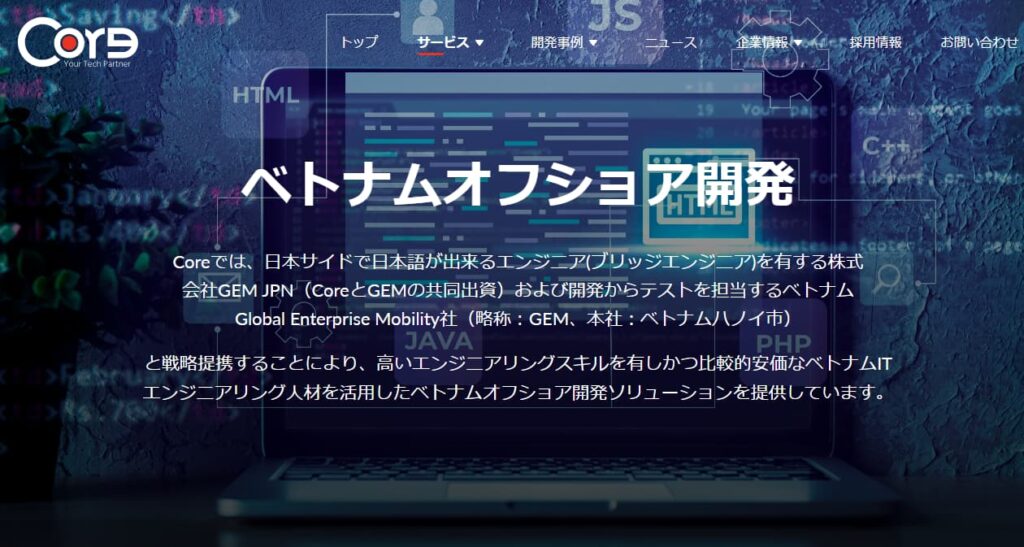
出典:株式会社Core
Coreは、ベトナムでのオフショア開発に特化したサービスを展開しています。
特徴は、国内比約1/3〜1/2のコストでありながら、日本クオリティを維持できる点です。日本側では日本語が堪能なブリッジエンジニアが常駐し、上流工程と日本語ドキュメントを担当。ベトナム側では、現地最高峰の大学と提携し、最新のOSS技術に精通したエンジニアが開発を担当します。
導入時には、まず日本常駐での有償トライアルから始め、段階的に本格的なオフショア開発へ移行する方式を採用。また、アジャイル開発手法を用いることで、コストパフォーマンスとスピード開発の両立を実現しています。
株式会社ハイブリッドテクノロジーズ
ハイブリッドテクノロジーズは、日本とベトナムで500名以上の従業員を擁し、26,000名以上の開発エンジニアリストを活用できる体制を構築。290社以上のプロジェクトサポート実績を持つオフショア開発企業です。
品質面では、ISO9001、ISO27001の認証を取得し、ISTQBプラチナパートナーの資格も保持。独自の品質マネジメントシステムでバグの発生を抑制し、ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターと連携したセキュリティ監視も提供しています。
オフショア開発会社の選び方
オフショア開発の成否は、パートナーとなる開発会社の選定で大きく変わります。選び方のポイントは、以下の3つです。
- 開発したい製品が得意領域に入っているか
- 契約形態が希望に合っているか
- 日本企業との取引実績
上記の基準に基づいて選定することで、プロジェクトの成功確率を高められます。
開発したい製品が得意領域に入っているか確認する
開発会社の選定では、まず開発したい製品が相手の得意領域に含まれているかを確認します。基幹システム開発を得意とする会社もあれば、モバイルアプリ開発やWebサイト開発に強みを持つ会社もあります。
【確認すべきポイント】
得意分野の確認
- 企業のホームページや見積もり時に、得意分野を確認する
- 自社の開発目的と合致しているか見極める
開発実績のチェック
過去の開発実績が複数ある場合、プロジェクトの規模・開発期間・投入人数を確認する
問題発生時の対応力
過去のトラブル対応事例を聞き、実践的な開発力を評価する
契約形態が希望に合っているか確認する
オフショア開発の契約形態は、請負契約と準委任契約の2種類です。それぞれ特徴が異なるため、自社のニーズに合った形態を選ぶ必要があります。
| 契約形態 | 特徴 |
| 準委任契約(開発チームの労働力提供) | 仕様変更に柔軟に対応できる。成果物の品質保証は発注側が管理する必要がある。 |
| 請負契約(成果物の納品を目的とする) | 品質保証はオフショア開発会社が担う。事前に決めた仕様に基づき開発が進むため、柔軟な変更は難しい場合がある。 |
開発手法や期間、予算に応じて、適切な契約形態を選択しましょう。特に品質保証の範囲や責任の所在は、慎重に確認する必要があります。
日本企業との取引実績を確認する
コミュニケーションの質は、プロジェクトの成否を左右する重要なポイントです。日本語が得意でないエンジニアとの協業は、要望が正確に伝わらないリスクがあります。
日本特有の言い回しやビジネス慣習への理解も必要です。日本企業との取引実績が豊富な開発会社であれば、これらの課題に対する解決策を持っている可能性が高くなります。
特に、日本語でのコミュニケーションが可能なブリッジエンジニアの存在は、スムーズな開発進行の鍵となるでしょう。取引実績と合わせて、コミュニケーション体制の確認も重要です。
オフショア開発の基礎知識
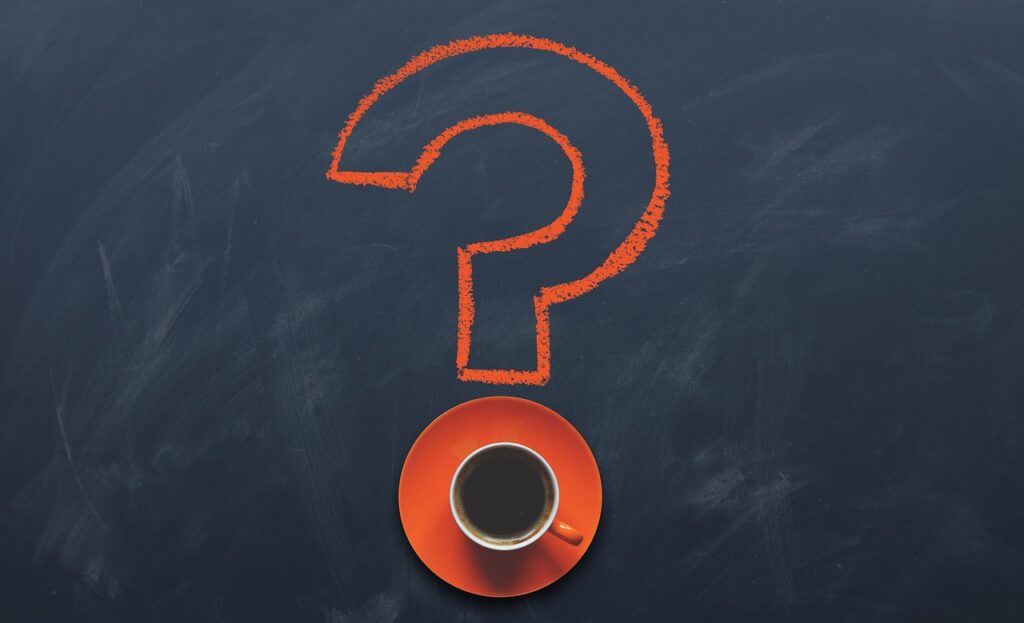
システム開発におけるコスト削減と人材確保の解決策として注目されているのが、オフショア開発です。海外企業に開発を委託するこの手法は、特にアジア諸国との取引を中心に拡大しています。
ここでは、オフショア開発が選ばれる背景や、国内開発との違いについて解説します。
利用が進む目的と背景
オフショア開発が広がる最大の理由は、深刻化する国内のIT人材不足です。経済産業省は、2030年に約79万人のIT人材が不足すると予測しています。
一方、ベトナムやインドなどの国々では、優秀なIT人材が豊富に存在し、日本と比べて人件費が低く抑えられるため、コスト面でも大きなメリットがあります。
実際に、多くの企業が開発リソースの確保とコスト削減を目的にオフショア開発を活用し始めており、特に新規開発や大規模なシステム更新では、この傾向が顕著です。
また、以下の記事ではベトナムでのオフショア開発について解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発にはベトナムが最適!おすすめの開発会社や失敗しないポイントも
ニアショア開発との違い
国内の地方都市で開発を進めるニアショア開発と比べると、オフショア開発には明確な特徴があります。
| オフショア開発のメリット | オフショア開発のデメリット |
| コスト削減効果が大きい→人件費の安い国での開発により、国内よりも大幅なコスト削減が可能。 | コミュニケーションの課題→言語や文化の違いにより、意思疎通が難しくなる可能性がある。 |
| 豊富な人材を確保しやすい→海外のIT人材を活用できるため、リソースの確保がしやすい。 | 情勢や為替のリスク→海外の政治・経済状況や為替の変動によって、開発コストや進行に影響を受ける可能性がある。 |
ニアショア開発なら、オフショア開発で起こりうる問題は最小限に抑えられます。
ただし、ニアショア開発では地方でもIT人材の確保が難しく、オフショアほどのコスト削減は見込めません。開発手法の選択は、自社の状況や優先順位に応じて判断する必要があります。
オフショア開発に取り組むメリット
オフショア開発には、次の3つのメリットがあります。
- 開発コストの削減が期待できる
- 開発力・競争力強化につながる
- 対応可能な業務の幅が広がる
以下では、各メリットの詳細と具体的な活用方法について解説します。
開発コストの削減が期待できる
システム開発費の大部分を占めるのが人件費です。オフショア開発では、この人件費を大幅に削減できます。
【オフショア開発のコスト削減要因】
人件費の低さ
中国、インド、ベトナムなどのオフショア開発先では、日本の半分以下の人件費でエンジニアを確保できるケースもある。
大規模開発ほど効果が高い
新規開発や大規模なシステム更新では、削減効果がより顕著になる。
仕様変更やメンテナンスなど、オフショア開発特有のコストは発生するものの、トータルでみれば大幅な開発コストの削減が可能です。
また、コストダウンによって生まれた余剰資金は、他の重要な事業活動への投資や、新規プロジェクトの立ち上げに活用可能です。これにより、企業全体の競争力向上と成長促進につながります。さらに、価格競争が激しい市場において、より競争力のある価格設定が可能になるというメリットもあります。
また、以下の記事ではオフショア開発において実績が豊富な会社や選び方のポイントについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ 実績豊富なオフショア開発会社5選!国別の費用相場や失敗事例も解説 – トッパジャパン株式会社
開発力・競争力強化につながる
経済産業省の調査によると、2030年には最大約79万人のIT人材が不足すると予測されています。この「ITの2030年問題」に対し、オフショア開発は有効な解決策となります。特にグローバル化や情報化が急速に進む中、国内だけでIT人材を確保することは極めて難しい状況です。
【オフショア開発のメリット】
優秀なIT技術者の確保
多くのオフショア開発先では、IT技術者の育成を国策として推進しており、高度な技術力を持つエンジニアを効率的に確保できる。
最新技術・グローバルな視点の導入
海外の開発チームと協業することで、最新の技術トレンドやグローバルな視点を取り入れやすくなる。
さらに、オフショア開発を通じて構築した海外の優秀なIT企業や人材とのネットワークは、将来的な事業展開においても大きな資産となります。技術者の採用や育成に時間とコストがかかる中、即戦力となる人材を柔軟に確保できる点も、企業の競争力強化につながります。
対応可能な業務の幅が広がる
オフショア開発の活用により、自社だけでは手が届かなかった開発分野にも挑戦できます。基幹システムやWebシステム、IoT開発、AI、Webサイト制作、スマートフォンアプリなど、幅広い分野の専門家との協業が可能です。
最新技術を利用した新規ビジネスの立ち上げ時にも、必要な技術力をスピーディーに確保できます。
さらに、英語や中国語など、外国語対応が必要なシステム開発も可能になり、グローバル市場への参入機会が広がります。このように業務範囲を拡大できることは、新たな収益機会の創出にもつながります。自社内では対応が困難だったプロジェクトにもチャレンジできるようになり、事業成長の推進力となるでしょう。
オフショア開発のデメリット
コスト削減や開発力強化といったメリットがある一方で、オフショア開発には次のような注意すべき課題もあります。
- コミュニケーションコストがかかる
- 品質・進捗管理が難しい
- 為替相場や情勢により継続が難しくなるケースがある
上記の課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑えられます。
コミュニケーションコストがかかる
オフショア開発における最大の課題は、コミュニケーションの難しさです。
【コミュニケーションに関する主な課題】
時差の影響
- リアルタイムでの打ち合わせが制限される。
- 素早い意思決定やトラブル対応が難しくなる。
言語の問題
- 曖昧な表現(例:「できれば」「なるべく」)が正確に伝わらない。
- 開発チームの英語力・日本語力によっては、基本的な意思疎通も困難になる。
コミュニケーションの問題を解決するには、ブリッジエンジニアの配置や定期的なオンライン会議の設定など、追加のコストと時間が必要です。プロジェクト計画時には、これらのコミュニケーションコストも考慮する必要があります。
品質・進捗管理が難しい
オフショア開発では物理的な距離があるため、開発の品質や進捗を直接確認することが難しいというデメリットもあります。文化の違いにより、日本的な仕事の進め方が通用しないケースも見られます。
【報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の習慣の違い】
- 日本では当たり前のこまめな報告が、海外では必ずしも徹底されていない
- 進捗報告では「順調」と言われていたのに、実際には大幅な遅延が発生していたという事例もある
【品質管理における課題】
- 日本では細部へのこだわりが重視されるが、海外では過剰品質と判断されることがある
- 期待する品質水準を共有しないと、完成後の修正コストが増える可能性がある
このギャップを埋めるには、詳細な品質基準の設定と、継続的なレビュープロセスの確立が必要です。
為替相場や情勢により継続が難しくなるケースがある
海外との取引には、為替変動のリスクが付きまといます。円安が進行すると、当初の想定よりも開発コストが大幅に膨らむ可能性があり、特に長期プロジェクトでは、この影響が無視できないものとなります。
さらに深刻なのが、開発先国の政治情勢の不安定さです。例えば、2021年にミャンマーで発生したクーデターのように、突発的な政変によってプロジェクトの継続が困難になるケースもあります。
リスクを軽減するには、複数の国に開発拠点を分散させたり、為替予約を活用したりするなどの対策が必要です。ただし、これらの施策も追加のコストとなることを念頭に置く必要があります。
また、以下の記事ではオフショア開発の失敗例について解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発の失敗事例4選!成功させるポイントや代替案も紹介 – トッパジャパン株式会社
オフショア開発で失敗しないための7つのポイント

オフショア開発には、コスト削減や開発リソース確保など多くのメリットがある一方で、失敗するリスクも潜んでいます。成功させるためには、準備段階から運用まで、さまざまな面での注意が必要です。
ここでは、プロジェクトを成功に導くための以下7つのポイントを解説します。
- 仕様・要件は明確にして伝える
- 開発先とのコミュニケーションを積極的に取る
- 格安の見積もりに注意する
- 実績のある開発先を選ぶ
- 国民性が近い国を選ぶ
- 担当メンバーを固定する
- コストの計算は継続的に行う
仕様・要件は明確にして伝える
オフショア開発で最も重要なのが、仕様や要件の明確な伝達です。日本人同士なら暗黙の了解で済むことでも、海外のメンバーには具体的な指示が必要になります。
特に日本語特有のニュアンスは正確に伝わりにくく、期待する成果物が得られない原因になることもあります。
【仕様・要件の伝え方のポイント】
| ポイント | 詳細 |
| 詳細設計は日本側で決定し、ドキュメント化する | ・仕様を文章だけでなく、具体的なサンプルや図を用いて視覚的に示す。・認識のズレを防ぐため、開発前に内容をしっかり共有する。 |
| 品質基準を明確に定義する | ・「良いコード」「適切なデザイン」といった曖昧な表現は避ける。・具体的なチェックリストや品質基準を作成し、開発チームと共有する。 |
| 簡単な表現で直接的に伝える | ・海外メンバーには、簡潔な言葉で明確に指示する。・コード規約や細かなルールも文書化し、統一したルールのもとで開発を進める。 |
これにより、プロジェクト全体の認識を統一し、スムーズな開発進行が期待できます。
開発先とのコミュニケーションを積極的に取る
コミュニケーションの活性化は、オフショア開発の成否を分ける重要なポイントです。言語の壁を乗り越え、確実な意思疎通を図るには、複数のコミュニケーション手段を活用する必要があります。
【適切なコミュニケーション手段の活用】
チャットツール・ビデオ会議ツール・クラウドツールを併用する
状況に応じて適切な手段を選択し、スムーズな情報共有を行う。
報告・連絡・相談(ホウレンソウ)の徹底
- 週に1度のビデオ会議を開催し、進捗状況を確認する。
- チャットの返信は当日中にするなど、具体的なルールを設定する。
プロジェクト開始時には、可能であれば現地に赴いてキックオフミーティングを実施します。オンラインでの開催でも、開発の目的や期待することを明確に伝え、チーム全体の方向性を合わせることが重要です。
また、文章でのやり取りで内容が伝わっていないと感じた場合は、ビデオミーティングを活用して相手の理解度を確認し、必要な補足説明を行います。説明後は、内容を文章化して残すことで、認識の食い違いを防げます。
格安の見積もりに注意する
相場よりも大幅に安い見積もりには注意しましょう。多くの場合、インターン生や経験の浅いエンジニアで構成されていたり、テスト工程が不十分だったりと、安い理由が必ずあります。
【格安見積もりのリスク】
経験の浅いエンジニアが担当する可能性が高い
インターン生や未経験者が開発を担当し、期待する技術レベルに達しないことがある。
テスト工程が不十分
品質保証の体制が整っておらず、バグの多い成果物が納品されるリスクがある。
追加コストの発生
品質不足により、後から修正や再開発が必要になり、結果的にコストが膨らむ。
見積もりの金額が安い場合には、その理由を詳しく確認することが重要です。また、適切な判断のために、必ず複数社から見積もりを取得し、相場観を把握しましょう。安さだけを追求すると、後で大きなトラブルに発展する可能性が高いです。
開発の規模や期間・人数なども確認し、問題が発生した場合のトラブルシューティングについても、事前にチェックしておくことが必要です。
実績のある開発先を選ぶ
開発先の選定では、まず得意分野と実績の確認が重要です。特に依頼したいプロジェクトと似た実績を持つ会社であれば、技術も確立されており、開発も問題なく進められる可能性が高いでしょう。
選定時には、過去の案件について具体的な内容を確認しましょう。工程や期間など、詳細を聞くことで開発先の実力が見えてきます。
また、実績が豊富な企業であれば、プロジェクトで発生しがちな問題への対処方法も確立されているはずです。開発の規模や期間、投入したエンジニアの人数なども含めて確認し、トラブル対応の実績についても把握しておくことが重要です。
国民性が近い国を選ぶ
オフショア開発は、相手国との文化や国民性の違いも重要なポイントです。日本と国民性が近い国を選ぶことで、スムーズな開発進行が期待できます。
例えば、自分の意見が強く失敗を認めない人が多い国もあり、日本の国民性と相性が良くない国とのビジネスでは、トラブルが発生するリスクが高まります。
一方、ベトナムやミャンマーは、勤勉で真面目な国民性が日本人との相性が良いとされています。日本と国民性が比較的近い国の中から開発パートナーを選定することで、円滑なプロジェクト進行が可能です。
相手の文化や国民性を理解し、パートナーとしてプロジェクトを進めていく意識を持ちましょう。
また、以下の記事ではベトナムオフショアアプリ開発で失敗しないためのポイントについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ ベトナムオフショアのアプリ開発におけるメリット・デメリット|失敗しないためのポイントも解説 – トッパジャパン株式会社
担当メンバーを固定する
オフショア開発会社では、担当者やメンバーが入れ替わる場合もあります。しかし、メンバーが頻繁に変更されると、以下のようなリスクがあります。
プロジェクトの知識が引き継がれにくい
メンバーが変わるたびに仕様の理解が必要になり、開発スピードが低下する。
引き継ぎが不十分だと品質が低下する
過去の仕様変更や注意点が伝わらず、バグの増加や仕様漏れが発生する可能性がある。
納期の遅延につながる
新メンバーがキャッチアップする期間が必要となり、プロジェクト全体の進行に影響を及ぼす。
そのため、人員体制の変更は極力避け、変更する場合は事前に協議した上で、しっかりとした引き継ぎをしてもらいましょう。また、開発前の段階で、メンバーの変更が発生した場合の引き継ぎに関するマニュアルを定めるなど、対策をしておくことで、トラブルを防ぐことができます。
チーム内での情報共有を徹底し、メンバーの入れ替わりが発生しても、フォローし合える体制を整えておくことが重要です。
コストの計算は継続的に行う
オフショア開発では、予想外のコストが発生するリスクがあるため、内製した場合と外注した場合のコスト計算を継続的に行う必要があります。
すべてを外注することがベストとは限らず、内製を取り入れた方がコストを抑えられるケースもあります。定期的なコスト分析を行い、必要に応じて開発方針を見直すことで、予算超過を防ぐことが可能です。
また、コストの計算では、開発費用だけでなく、コミュニケーションツールの導入費用やブリッジエンジニアの人件費なども含めた総合的な評価が必要です。
まとめ
オフショア開発は、開発コストの削減と人材確保の両面で有効な手段です。ただし、成功させるためには、開発会社の選定から運用まで慎重な準備と対策が必要です。
特に重要なのは、開発目的と要件の明確化です。基幹システム開発やモバイルアプリ開発など、得意分野は会社によって異なります。自社のニーズに合った開発会社を選ぶことが、プロジェクト成功の第一歩となります。
また、コミュニケーションの課題を克服するには、日本語対応力や開発実績の確認が欠かせません。ブリッジエンジニアの存在や品質管理体制なども、選定の重要な基準となるでしょう。
本記事で紹介した9社は、いずれも豊富な実績と信頼性を備えています。各社の特徴を参考に、自社の状況や優先順位に応じて最適なパートナーを選定し、効率的な開発体制の構築を目指しましょう。
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説