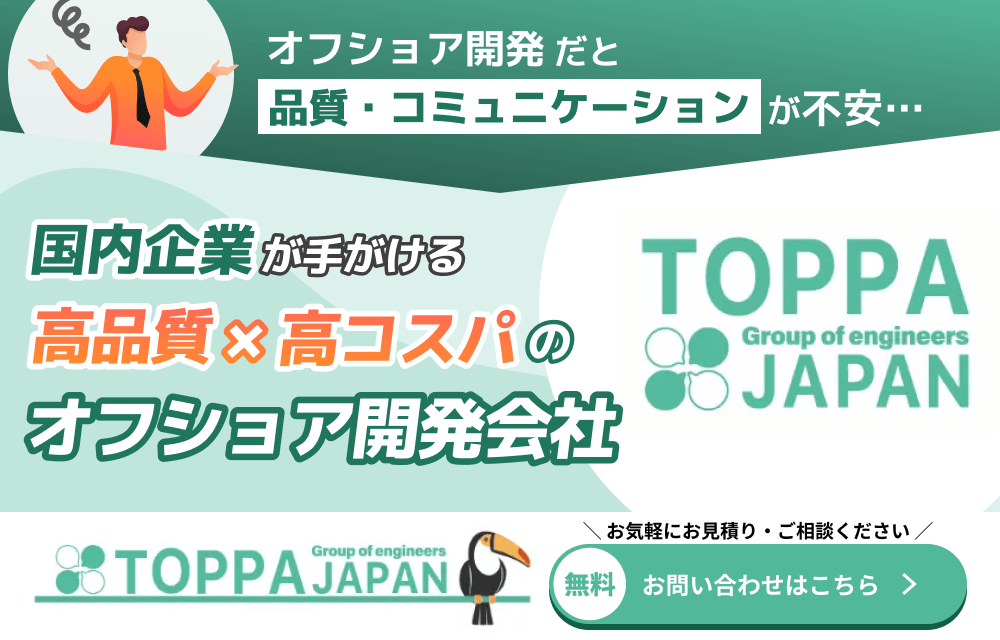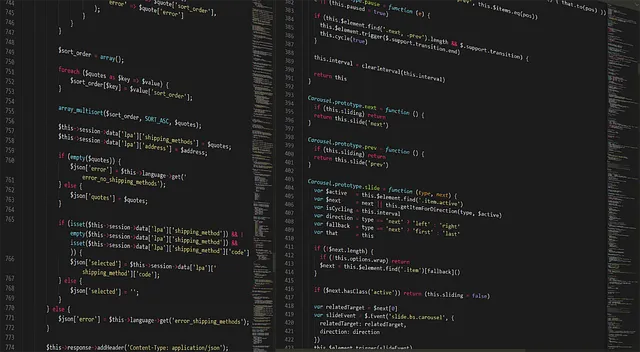
オフショア開発は、コストを抑えながら優秀な海外エンジニアを登用できる手段として注目されています。エンジニア不足などの課題を抱える企業にとって、海外開発拠点の活用は有効な選択肢の一つです。
本記事では、オフショア開発体制を比較し、それぞれのメリット・デメリットや、失敗しないためのポイントについて詳しく解説します。オフショア開発の活用を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。
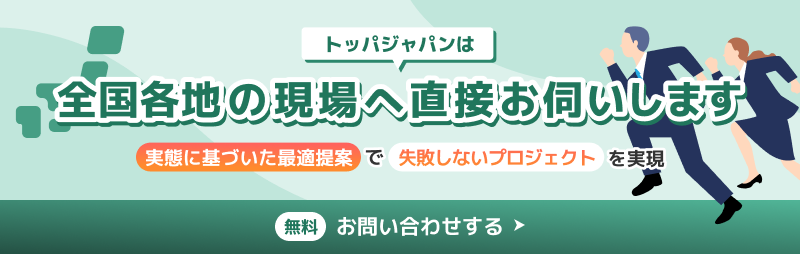
オフショア開発とは?
オフショア開発とは、システム開発やアプリ開発などの業務を、海外の開発拠点に委託することです。企業が海外の開発会社と直接契約するケースのほか、日本国内のIT企業を経由して海外拠点を活用するケースもあります。開発拠点を自国内ではなく、ベトナムやフィリピンなどのアジア諸国に置くことで、人件費を抑えながら高い技術力を活用できます。
近年は、単なるコスト削減にとどまらず、専門スキルの獲得やチーム体制の拡張、グローバル展開を見据えた開発体制の構築などの戦略的な目的で導入するケースも少なくありません。
ただし、言語や文化の違い、時差によるコミュニケーションの課題も存在するため、適切な体制選定とパートナー企業の見極めが重要です。
以下の記事ではオフショア開発におけるおすすめ企業について解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発会社おすすめ9選|失敗しないためのポイントや活用のメリット・デメリットも – トッパジャパン株式会社
オフショア開発の開発体制
オフショア開発では、依頼先との契約形態やプロジェクトの運用方法によっていくつかの開発体制に分かれます。それぞれに特徴と向いている企業像があります。
開発体制の選定は、プロジェクト進行のスピード・柔軟性・管理コスト・品質などに大きく影響するため、自社のリソース状況や開発目的に応じて最適な体制を選ぶことが重要です。以下で各体制の概要を解説します。
ラボ型開発
ラボ型開発とは、クライアント企業専属の開発チームをオフショア側に組成し、継続的に開発業務を行う体制です。契約は月額制が多く、一定の人員を期間中に確保できるため、柔軟なタスクアサインや機能追加、仕様変更への対応がしやすいのが特徴です。
また、チームが長期的にプロジェクトに関わるため、業務理解が深まり、密に連携できる点も魅力の一つです。プロダクトの内製化を目指す企業や、アジャイル開発を採用している企業に適しています。
ただし、進捗管理や品質管理はクライアント側の責任が大きくなるため、開発マネジメントスキルやエンジニアとの連携体制を持っている企業に向いています。
また、以下の記事ではオフショア開発について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発とは?メリット・デメリットや失敗例・おすすめの開発企業も紹介 – トッパジャパン株式会社
受託開発型
受託開発型は、仕様書や要件定義に基づいて成果物単位で開発を外注する体制です。ウォーターフォール型の進行が一般的で、契約時に納期・仕様・費用を明確に定めてから開発をスタートします。
クライアント側は要件を固めれば、その後の進行や管理はベンダーに任せられるため、比較的負担が少ない点がメリットです。一方で、仕様変更には追加費用や納期調整が必要となり、柔軟な対応が難しいというデメリットもあります。
単発の開発案件や、すでに仕様が明確に決まっているプロジェクト、社内にエンジニアが少ない企業に向いています。
また、以下の記事ではオフショア開発におけるよくある悩みについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発でよくある悩みとは?悩み別の対処法や成功事例も紹介 – トッパジャパン株式会社
ブリッジSE型
ブリッジSE型は、日本語が堪能なSEが日本企業とオフショア開発チームの間に立ち、橋渡しを行う体制です。コミュニケーションの齟齬を防ぎ、日本企業の文化や開発フローを理解した上で、現地エンジニアに正確な指示を伝えてくれます。
特に、日本語での細やかなやり取りが求められる場面や、非エンジニアが開発の窓口を担う場合に大きな効果を発揮します。
ただし、ブリッジSE人材は希少かつ高コストな場合もあるため、品質や進行管理の精度を重視する企業向けです。
また、以下の記事ではベトナムでのオフショア開発について解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発にはベトナムが最適!おすすめの開発会社や失敗しないポイントも – トッパジャパン株式会社
ハイブリッド型
ハイブリッド型は企業によって定義が異なります。
ラボ型と受託(請負)を組み合わせ、フェーズや領域ごとに最適化する体制のことを指す場合と、国内のチームと海外のオフショアチームが役割を分担して連携する体制を指す場合があります。
ラボ型と受託(請負)を組み合わせる場合、初期の要件固めや基盤構築は受託で品質と見積りの明確性を担保し、以降の継続開発・改善はラボで柔軟に進めるなど、コスト・スピード・品質のバランスを取りやすいのが特長です。
国内チームと海外のオフショアチームが連携する場合、国内の企業が強みを持つ高品質な要件定義やプロジェクトマネジメント能力を活かしつつ、オフショア開発のコストメリットを最大限に享受できます。
オフショア開発体制の比較
オフショア開発を成功させるうえで重要なのが、自社に合った「開発体制」の選定です。開発の目的や体制によって、コスト・柔軟性・進行管理のしやすさ・リスクの大きさが大きく変わってきます。
ここでは、主な開発体制である「ラボ型」「受託開発型」「ブリッジSE型」「ハイブリッド型」について、特徴やメリット・デメリットを一覧で比較し、それぞれどのような企業に適しているかを解説します。
| ラボ型開発 | 受託開発型 | ブリッジSE型 | ハイブリッド型(国内外のチームが連携する場合) | |
|---|---|---|---|---|
| 契約形態 | 月額固定(人月契約) | 成果物単位の契約(請負) | 月額制+成果物契約など混合形式 | 国内側と海外側の複合契約(準委任+請負など) |
| 主な特徴 | 専属チームによる継続開発 | 仕様に基づく一括開発 | 日本語SEが現地と橋渡し | 国内チームが上流・品質管理、海外チームが実装・開発を担当 |
| 柔軟性 | 高い(仕様変更しやすい) | 低い(仕様凍結後の変更が困難) | 中程度(SEの調整力に依存) | 高い(国内で方向性を調整しつつ開発を進行) |
| コミュニケーション | 頻繁・密な連携が必要 | 最小限でも可能 | 日本語対応で比較的スムーズ | 国内窓口を通してスムーズ |
| 開発責任の所在 | クライアント側に主体あり | ベンダーに一任 | SEとベンダーが分担 | 国内チームが管理主体、海外チームが実装責任 |
| メリット | 長期的な体制構築が可能 | 明確な成果物納品 | コミュニケーションの精度が高い | 品質とスピードの両立 |
| デメリット | 管理工数がかかる | 柔軟な変更対応が困難 | 人材コストが高くなることがある | 調整コスト増/マネジメント力が必要/文化・時差の影響 |
| 向いている企業 | 自社で開発管理が可能な企業 | 単発の開発案件や要件が明確な企業 | 開発経験が浅い、要件伝達が不安な企業 | 大規模・長期案件/品質を担保しつつスピードを重視する企業 |
それぞれの体制にメリット・デメリットがあるため、自社の技術力や管理の容易さなど、多角的な観点から、プロジェクトの性質に応じた体制を選ぶことが重要です。
また、以下の記事ではオフショア開発において実績が豊富な会社や選び方のポイントについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ 実績豊富なオフショア開発会社5選!国別の費用相場や失敗事例も解説 – トッパジャパン株式会社
自社に合った開発体制の選び方
オフショア開発の成功率は、開発体制の選定に大きく左右されます。理想的なコストや品質、スピード感を実現するために、自社の状況やプロジェクトの特性を正しく見極めることが不可欠です。
ここでは、体制選びにおける代表的な判断軸を4つ紹介します。自社の課題や目的を明確にしながら、最適な体制を検討しましょう。
1. プロジェクトの規模や期間
開発体制を選ぶ際、まず考慮したいのがプロジェクトの規模感や開発期間です。たとえば、開発ボリュームが比較的小さく、明確な納品物が決まっている短期プロジェクトであれば、進行管理をベンダーに任せられる受託開発型が相性の良い選択肢となります。
一方で、長期間にわたるサービス開発や、継続的な機能追加・改善が求められるようなプロジェクトの場合は、ラボ型などの柔軟性の高い体制が望ましいでしょう。ラボ型開発は、要件の変更や優先順位の調整にも対応しやすく、開発を内製化に近い形で進められる利点があります。
プロジェクトの規模や期間によって、選ぶべき体制は大きく変わります。
また、以下の記事ではベトナムオフショアのアプリ開発についてメリット・デメリットを解説しています。あわせてご覧ください。
→ ベトナムオフショアのアプリ開発におけるメリット・デメリット|失敗しないためのポイントも解説 – トッパジャパン株式会社
2. 社内の開発リソースとマネジメント力
社内にどの程度の開発人材やプロジェクトマネジメント体制が整っているかによって、選ぶべき開発体制が変わります。
自社にエンジニアが在籍しており、コードレビューや進行管理が可能であれば、ラボ型のような体制でも問題なく運用できるでしょう。専属チームを確保しながら、自社主導で開発を進められるため、スピードと柔軟性を両立できます。
一方で、社内に開発のノウハウがあまりなく、リソースが不足している場合は、受託開発型やブリッジSE型のように、管理を外部に委ねられる体制が適しています。ブリッジSE型では、日本語対応が可能なエンジニアにやりとりを任せられるため、開発経験が浅い企業でも安心できます。
3. コミュニケーション体制
オフショア開発では、言語の壁や時差、文化の違いといったコミュニケーション上の課題が避けられません。
たとえば、英語での会話やドキュメントのやり取りに慣れているチームであれば、ラボ型やハイブリッド型でも十分に対応できます。オンラインでのやりとりで対応できるなら、問題なく開発を進められます。
反対に、コミュニケーションの基盤が日本語である場合や、海外チームとのやりとりに不安がある場合は、ブリッジSE型が最適です。日本語が通じるエンジニアが仲介者となり、コミュニケーションの課題を解決します。
自社の語学力や対応体制を正直に評価し、それに見合った仕組みを選ぶことが重要です。
4. セキュリティや品質保証の方針
セキュリティや品質保証についても十分に検討しましょう。特に、機密性の高い情報を扱うプロジェクトでは、開発パートナーの情報管理体制や国際認証(ISMS認証など)の有無が、重要な選定基準となります。
受託開発型のように、契約上で成果物・納期・管理責任を明確に設定できる体制であれば、品質とセキュリティの担保がしやすくなります。一方で、ラボ型のように柔軟性に富んだ体制では、開発チームの内部管理ルールやセキュリティポリシーの確認が必要です。
自社が求めるセキュリティ基準やレビュー体制を明文化できるか、またそれにパートナーが対応できる体制かどうかを見極めることで、リスクを抑えつつ安心して開発を委託することができます。
オフショア開発の開発体制選びに失敗しないためのポイント
オフショア開発において、開発体制の選択は非常に重要です。選択を誤ると、期待していたコスト削減が実現できなかったり、納期遅延や品質トラブルに発展することも少なくありません。
ここでは、開発体制選びで失敗を防ぐために、特に注意しておきたい2つのポイントを紹介します。
金額の安さで選ばない
コスト削減はオフショア開発を検討する大きな動機の一つですが、金額の安さだけを基準に委託先や体制を決めることは非常にリスクが高いです。実際に、単価が安い企業に依頼した結果、仕様の理解不足や品質のばらつきなどのトラブルが原因で、何度も修正が発生し、最終的にコストも工数も大幅に膨らんでしまうケースがあります。
特に、受託開発型で格安の見積もりを提示された場合は注意が必要です。一見、コストパフォーマンスが高いようでも、仕様変更への対応が有償で都度発生するなど、追加費用が積み上がる構造になっていることもあります。
金額の安さに目を奪われるのではなく、成果物の品質・対応スピード・継続性などを含めた総合的な価値で判断することが重要です。
また、以下の記事ではオフショア開発の国別の価格帯について解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社
委託先の技量を確認する
開発体制を選ぶ際には、表面的な実績や営業資料だけではなく、実際にその体制を担うエンジニアやプロジェクトマネージャーの技量をしっかり見極めることが欠かせません。特にラボ型やブリッジSE型のように、特定メンバーが継続的にプロジェクトに関与する体制では、担当者のスキルや経験が成果に直結します。
たとえば、現地メンバーのスキルや過去の実績は、必ず確認しておくべきです。また、ブリッジSEが関与する場合には、その人材が技術とビジネス両方の橋渡しができるだけの知見を持っているかどうかも評価ポイントになります。
開発会社の中には、商談段階では経験豊富なマネージャーが前面に出て、契約後に別の若手チームが実務を担当するケースもあります。こうしたギャップを防ぐためには、開発体制に実際に参加するメンバーのスキルや体制構成を事前に開示してもらい、技量を確認するプロセスを設けることが大切です。
また、以下の記事ではオフショア開発の失敗例について解説しています。あわせてご覧ください。
→ オフショア開発の失敗事例4選!成功させるポイントや代替案も紹介 – トッパジャパン株式会社
まとめ
オフショア開発は、コスト削減だけでなく、開発体制の拡張やスキル確保、グローバル化を視野に入れた戦略的な手段としても有効です。ただし、開発体制の選択を誤れば、希望通りの開発を実現できない場合があります。
オフショア開発の開発体制には、それぞれ異なる特性やリスクがあるため、自社のリソースやプロジェクトの性質、コミュニケーション体制などを総合的に考慮したうえで判断することが重要です。金額の安さだけにとらわれず、委託先の技量や連携力までを見極めたパートナー選びを行うことで、オフショア開発を成功に導くことができるでしょう。
オフショア開発の導入なら実績豊富なトッパジャパンにお任せください。トッパジャパンは、ベトナム開発チームによるオフショア開発サービスを提供します。
高品質で安心な開発サービスを柔軟かつコストパフォーマンス良く提供可能です。トッパジャパンへのご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
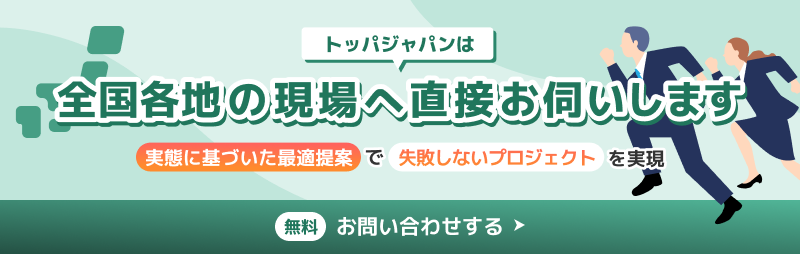
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説