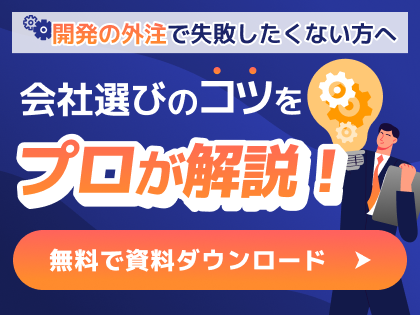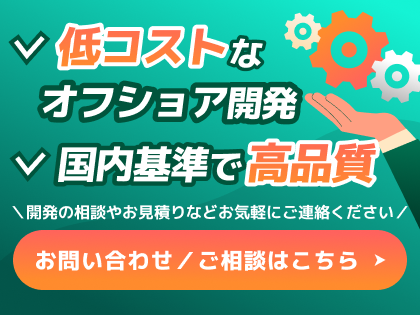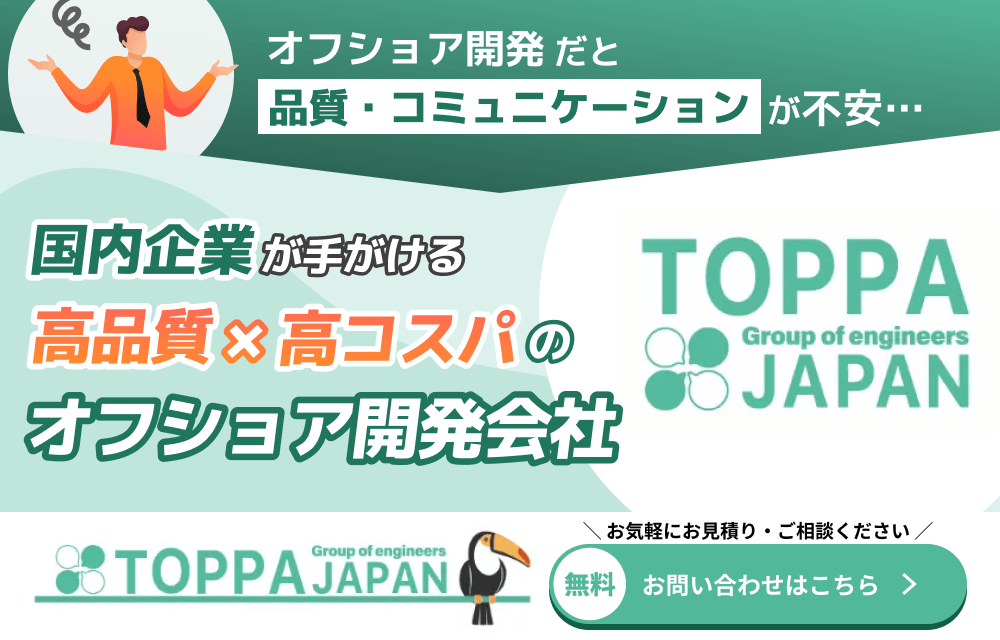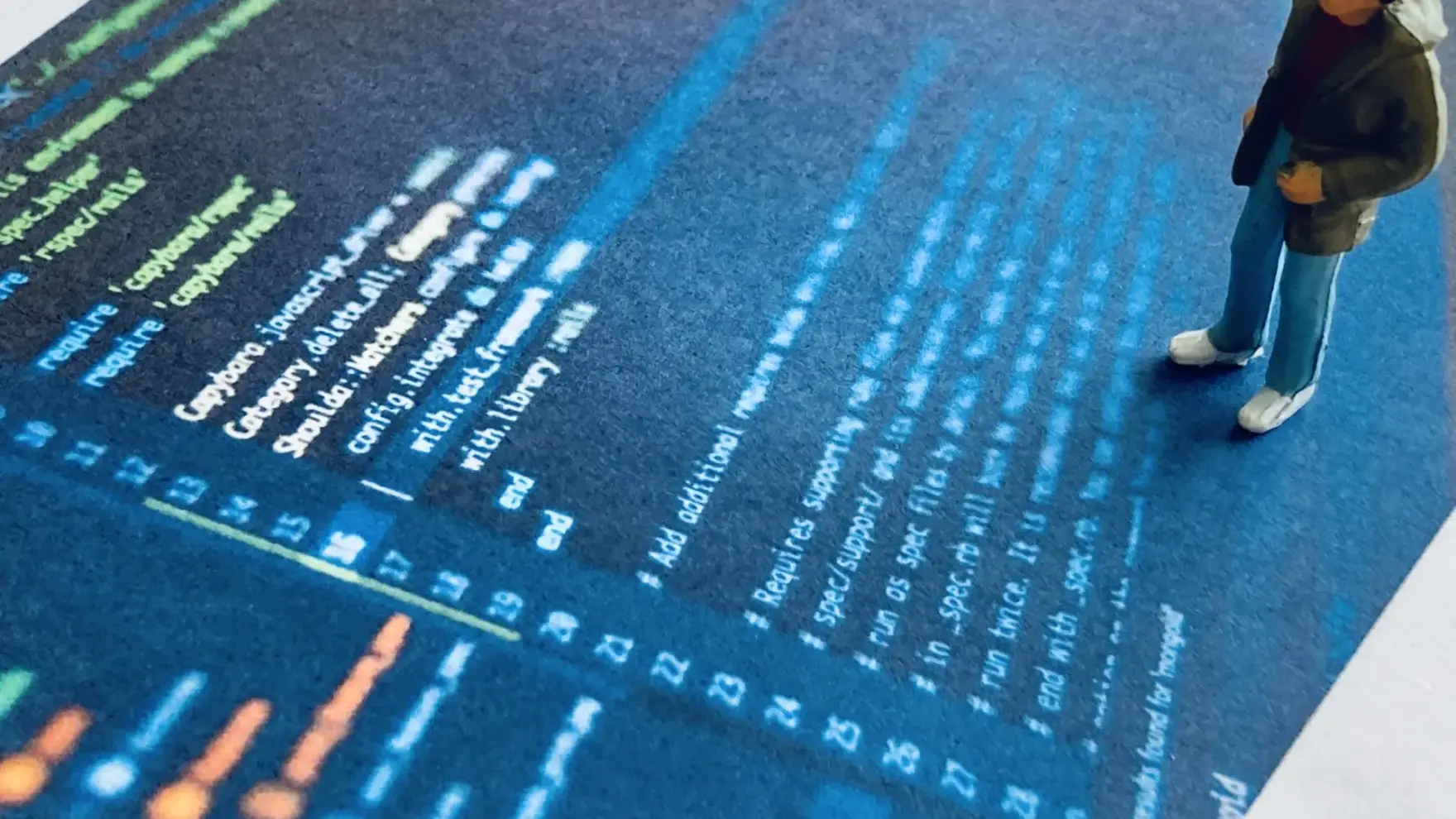
自社サービスや新規事業の立ち上げを検討しているIT担当者の方々にとって、仕様変更への対応力や長期的な開発体制の確保は切実な問題です。そこで注目されているのが「ラボ型開発」と「アジャイル開発」の組み合わせです。
本記事では、ラボ型開発の基本概念や特徴から、国内・海外での展開の違い、他の契約形態(請負契約・SES)との比較、そしてアジャイル開発との親和性について詳しく解説します。さらに、この組み合わせが特に効果を発揮するケースや、代表的な対応企業も紹介します。
ラボ型開発とは?

ラボ型開発は、企業が社外に専門の開発チームを構築し、一定期間にわたって開発業務を委託する契約形態です。一般的に「ラボ契約」とも呼ばれるこの方式は、柔軟な開発体制と継続的なリソース確保を実現します。
【ラボ型開発の特徴】
- 期間は通常6ヶ月〜1年の中長期契約
- 専任エンジニア(4〜5名程度)による専属チーム編成
- 契約期間中は依頼元の案件のみに注力
- 準委任契約の一種として位置づけられる
- オフショアやニアショアで多く採用される形態
ラボ型開発では、契約期間中、依頼元企業の指示を受けながら開発業務が進行します。依頼元はPMやブリッジSEを通じて開発指示を行い、チーム全体をマネジメントします。
ラボ型開発の大きな特徴は、「業務の遂行」を約束する準委任契約である点で、成果物の完成そのものは契約の必須条件ではありません。
このような特性から、「継続的に案件が発生するが自社内のリソースが不足している」といった状況において、外部に優秀なエンジニアリソースを確保する手段として活用されています。
また、以下の記事ではシステム開発を外注・内製するメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発を外注・内製するメリット・デメリットを解説!判断基準や開発費用も紹介
「国内ラボ型開発」と「海外ラボ型開発」の違い
ラボ型開発は大きく「国内」と「海外」の二つに分類でき、それぞれ異なる特性と利点があります。
【国内と海外のラボ型開発の違い】
| 比較項目 | 国内ラボ型開発(ニアショア) | 海外ラボ型開発(オフショア) |
| コミュニケーション | 言語・文化の壁がなくスムーズ | 言語や時差、文化の違いによる課題あり |
| コスト | 比較的高め | 大幅な削減が可能 |
| 人材確保 | IT人材不足の影響あり | 優秀な人材の確保が容易 |
| 主な開発地域 | 地方都市 | ベトナムなどの東南アジア諸国 |
| 特徴 | 細かな調整が必要なプロジェクトに適する | 長期的な開発で費用対効果が高い |
国内ラボ型開発の最大の強みは、コミュニケーションのとりやすさです。言語の壁や文化の違いを気にせず、スムーズな意思疎通が可能です。急な仕様変更や複雑な要件についても正確に伝わりやすく、細かい調整が必要なプロジェクトに適しています。
一方、海外ラボ型開発は「オフショア開発センター(ODC)」とも呼ばれ、コスト面での優位性が最大の魅力です。特に長期的な開発プロジェクトでは、その差が大きく表れます。また、国によっては日本より豊富なIT人材を確保できる可能性もあります。
また、以下の記事ではベトナムでラボ型開発を行うメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ ベトナムでラボ型開発を行うメリットは?注意点やおすすめの会社も紹介
ラボ契約とほかの契約形態との違い

システム開発を外部に委託する際、どのような契約形態を選ぶかはプロジェクトの成否を左右する重要な決断です。
一般的な契約形態として「ラボ契約」「請負契約」「SES(常駐型開発)」の3つがよく知られていますが、それぞれに特徴や向いているプロジェクトが異なります。
ここでは、それぞれの契約形態の特徴と違いを明確にし、どのようなケースに適しているかを解説します。
準委任契約とは
準委任契約は、「仕事の完成」ではなく「業務の遂行」を目的とした契約形態です。システム開発においては、開発作業自体の実施を約束するもので、最終的な成果物の完成や品質を保証するものではありません。
【準委任契約の主な特徴】
- 人月単位や期間をベースとした契約
- 業務の遂行そのものが契約の目的
- 成果物の納品義務はない(契約書に特記がない限り)
- アジャイル型開発など柔軟な開発に適している
- 契約期間中は仕様変更に柔軟に対応可能
ラボ契約はこの準委任契約の一種で、専属の開発チームを一定期間確保して開発を進める形態です。開発者は契約期間中、発注者のための業務に従事しますが、直接の指揮命令関係は生じません。これにより、発注者は社員に近い形で外部エンジニアを活用できますが、法的には雇用関係にはならない点が特徴です。
請負契約とは
請負契約は、「仕事の完成」を目的とした契約形態で、システム開発においては成果物(ソフトウェアやシステム)の納品をゴールとします。民法第632条に基づくこの契約形態は、従来のシステム開発で広く採用されてきました。
【請負契約の主な特徴】
- 納品物の完成がベース
- 受託者は契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を負う
- 基本的にウォーターフォール型開発に適合
- 初期段階での要件・仕様の明確化が必須
- 仕様変更には追加費用が発生する場合が多い
請負契約では、発注者が要件を明確に定義し、それに基づいて受託者が設計、開発、実装、テストまでを行い、期日までに成果物を納品します。報酬は完成した成果物に対して支払われ、受託者は納品後も一定期間、システムに不具合があった場合の責任を負います。
この契約形態の最大の利点は、成果物の完成が契約上保証される点です。また、開発の管理も含めて受託者に一任できるため、発注者側の管理工数を抑えられます。プロジェクト単位で契約するため、開発コストを事前に把握しやすい点も魅力です。
SES(常駐型開発)とは
SES(System Engineering Service)は、発注元の指揮監督下でエンジニアが常駐して業務を行う契約形態です。準委任契約の一種でありながら、ラボ契約とは異なる特徴を持っています。
【SES(常駐型開発)の主な特徴】
- 発注元のオフィスに常駐して業務を行う
- 発注元の指示に基づいて日々の業務を遂行
- 人月単位での契約が一般的
- 保守運用など長期的な業務に適している
- 発注元の既存チームと密に連携する必要がある案件に向く
ラボ契約と同様に準委任契約の一種ですが、作業場所や業務の性質に大きな違いがあります。ラボ型が委託先のオフィスでチームとして業務を行うのに対し、SESは発注元のオフィスで発注元の直接指示を受けながら業務を行います。
SESは特に、既存システムの保守運用や拡張開発、社内システムの開発など、発注元の業務環境や既存システムへの深い理解が必要な案件に適しています。また、発注元の開発チームに一時的な人員補強が必要な場合や、特定のスキルを持つエンジニアを確保したい場合にも有効です。
また、以下の記事ではシステム開発の見積もりについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の見積もりの見方を解説!見積書の項目や見積もり手法・算出方法も紹介
アジャイル開発とは?

アジャイル開発は、変化の激しいビジネス環境に適応するための有効な手段となっています。「アジャイル」という言葉自体が「素早い」「機敏な」という意味を持つように、短期間で価値あるシステムを継続的に提供することを目指します。
ここでは、アジャイル開発の基本的な考え方から特徴、従来型開発との違いまでを解説します。
アジャイル開発の特徴
アジャイル開発は、機能単位の小さなサイクルで開発工程を繰り返し、変化に柔軟に対応しながらプロダクトの価値を最大化する開発手法です。従来型の開発手法と比較して、市場投入までの時間短縮や顧客ニーズへの迅速な対応が可能になります。
【アジャイル開発の主な特徴】
- 小さな機能単位で「計画・設計・実装・テスト」のサイクルを繰り返す
- 優先度の高い要件から順に開発を進める段階的アプローチ
- 頻繁な顧客フィードバックを取り入れた反復的改善
- 変化を前提とした柔軟な計画変更
- チーム間の密なコミュニケーション
アジャイル開発の大きな利点は、優先度の高い機能から着手できる点です。最も価値のある機能を最初に開発することで、早期にサービスをリリースし、市場からのフィードバックを得ながら改善を続けられます。ビジネス環境の変化に応じて要件や優先順位を変更できるため、最終的に本当に必要とされる製品を作り上げることが可能です。
ウォーターフォール型開発との違い
アジャイル開発とウォーターフォール型開発は、システム開発の代表的なアプローチであり、プロジェクトの進め方や価値観に大きな違いがあります。
【アジャイル開発とウォーターフォール型開発の違い】
| 比較項目 | アジャイル開発 | ウォーターフォール型開発 |
| 開発プロセス | 機能単位の小さなサイクルで繰り返し開発 | 要件定義→設計→実装→テスト→運用と順次進行 |
| 要件定義 | 大枠を決めて開発中に詳細化 | 開発前に詳細まで固める |
| リリースタイミング | 優先度の高い機能から段階的にリリース | 全機能完成後に一斉リリース |
| 仕様変更への対応 | 柔軟に対応可能(前提として想定) | 困難(追加コスト・納期遅延の原因) |
| 成果物の可視化 | 各イテレーションで動作確認可能 | 全工程完了後に初めて確認 |
| 予算・期間の見積もり | 比較的難しい | 立てやすい |
| 適したプロジェクト | 要件変更が予想される案件新規サービス | 要件が明確な大規模プロジェクト |
| 相性の良い契約形態 | ラボ契約(準委任契約) | 請負契約 |
これらの違いから、要件が明確で変更が少ない大規模プロジェクトにはウォーターフォール型が、要件の変化が予想される新規サービス開発や市場環境の変化が激しい領域ではアジャイル開発が適しているといえるでしょう。
契約形態との親和性も重要で、ウォーターフォール型は請負契約と、アジャイル開発はラボ契約(準委任契約)と相性が良いとされています。
また、以下の記事ではシステム開発の費用相場について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の費用相場は?コスト内訳や費用を安く抑えるコツも解説
「ラボ型開発」かつ「アジャイル」の進め方がおすすめな方

ラボ型開発とアジャイル開発の組み合わせは、専任チームによる一貫した開発体制と、柔軟な進行管理を両立させることで、特定のケースにおいて大きな効果を発揮します。
ここでは、ラボ型×アジャイルの開発手法が特に効果を発揮する3つのケースについて詳しく解説します。
要件や仕様が明確に固まっていないプロジェクトを検討中の方
要件や仕様が流動的なプロジェクトでは、ラボ型開発とアジャイル開発の組み合わせが大きな効果を発揮します。
【ラボ型×アジャイルの利点】
- 小規模な開発サイクルを繰り返しながら要件を明確化できる
- 専任チームが継続的に関わることで知識やノウハウが蓄積される
- 仕様変更に柔軟に対応できるため、試行錯誤のプロセスに最適
- 短期間でプロトタイプを作成し、フィードバックを即時反映
ラボ型開発では専任チームが中長期でプロジェクトにコミットするため、要件や仕様の変化にも対応しやすく、アジャイル開発の「設計・開発・テスト」というサイクルを短期間で繰り返すことで、素早くプロトタイプを作成し、実際に動くシステムを確認しながら要件を具体化できます。
特にスタートアップやDX推進中の企業において、「こんなサービスがあったら便利」という漠然としたアイデアから具体的な製品に落とし込む際に有効です。初期段階では核となる機能に集中し、ユーザーからのフィードバックを得ながら徐々に機能を拡充していけるため、市場のニーズに合致したサービスを効率的に開発できます。
開発コストを抑えつつ、スピード勝負のプロジェクトを検討中の方
市場競争の激化により、システム開発においても「早く」「安く」が求められる時代となっています。
【コスト・スピード面での利点】
- 海外開発拠点の活用による人件費削減
- 大規模な仕様書作成工程の省略によるスピードアップ
- 優先度の高い機能から順次リリースによる早期サービスイン
- 仕様変更時の追加費用リスク軽減
ラボ型開発では、ベトナムやインドなど人件費の安い地域で専任チームを固定化することで、日本国内でシステム開発を行う場合と比較して大幅なコスト削減が可能です。
さらに、アジャイル開発手法を採用することで、詳細な仕様書作成に時間をかけず、実装フェーズを前倒しできるため、市場投入スピードを加速できることもあります。特に競合他社との差別化や、時期を逃さないサービスローンチが求められるプロジェクトにおいて、この時間的優位性は大きな強みとなるでしょう。
また、以下の記事ではシステム開発のコスト削減策について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発のコスト削減策6選!コストが高騰する原因や成功事例も紹介
長期的なシステム運用・保守を見据えた開発を検討中の方
システム開発は完成がゴールではなく、むしろ運用開始が新たなスタートラインとも言えます。長期的な運用・保守を見据えた場合、ラボ型とアジャイルの組み合わせは特に有効な選択肢です。
【長期運用・保守面での利点】
- 開発から保守まで同一チームが一貫して担当できる継続性
- システム内部構造を熟知したエンジニアによる効率的なメンテナンス
- 定期的な機能アップデートやセキュリティ対応の円滑な実施
- 障害発生時の迅速な対応と復旧時間短縮
ラボ型開発の最大の強みは、中長期にわたって同一のチームが一貫してプロジェクトに関わることができる点です。開発段階からシステムの内部構造を熟知したエンジニアがそのまま保守フェーズも担当することで、問題発生時の原因究明や修正が迅速に行え、障害復旧時間を大幅に短縮できます。
また、アジャイル開発の「継続的改善」の考え方と組み合わせることで、システムローンチ後も市場ニーズや技術トレンドに応じた定期的な機能アップデートやセキュリティパッチの適用を円滑に実施できます。特に長期運用が想定される基幹系システムや、継続的な機能追加が必要なSaaSプロダクトなどでは、この継続的な改善体制が競争力維持に大きく貢献するでしょう。
また、以下の記事では教育業界におけるシステム開発について解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育業界で求められるシステム開発とは?おすすめの開発会社も紹介
ラボ型開発×アジャイルの開発事例
株式会社ベクティスが手掛けた「石垣島のアクティビティショップ予約サイト」は、定額制のアジャイル開発を採用したラボ型開発の事例です。
LeaLea合同会社は、大手ポータルサイトでは表現できないショップの個性や多様なユーザーニーズに応えるマッチングプラットフォームの構築を目指していました。しかし、IT知識が十分でなく、企画・仕様が明確に固まっていない状態でのプロジェクト開始に不安を抱えていました。
そこで定額制のアジャイル開発を提案し、優先度の高い機能から順次開発を進める手法を採用。従来の成果物請負型では仕様変更の度に追加コストや納期遅延のリスクがありましたが、定額制のアジャイル開発では柔軟に対応が可能でした。
IT知識が不十分なクライアントでも、開発会社とともに考え、提案を受けながら進められる点が大きなメリットとなりました。初期開発は4ヶ月で完了。この事例は、要件が流動的な新規サービス開発におけるラボ型×アジャイル開発の有効性を示しています。
参考:株式会社ベクティス|アジャイル開発事例(アクティビティープラットフォーム開発事例)
ラボ型開発×アジャイル開発に対応している企業
システム開発の成功には、信頼できるパートナー企業の選定が重要です。ここでは、ラボ型開発とアジャイル開発の両方に対応している企業を紹介します。それぞれの企業の特徴や強みを理解し、自社のプロジェクトに最適なパートナーを選定する参考にしてください。
トッパジャパン株式会社

出典:トッパジャパン株式会社
トッパジャパンは、ベトナムの優秀な開発チームと連携し、高品質なオフショア開発サービスを提供する企業です。ラボ型開発サービスは、長期的な開発パートナーシップを重視し、顧客ニーズに合わせた柔軟な対応力が特徴となっています。
【トッパジャパンの強み】
- 品質とコストの両立:ベトナム有数の開発チームによる高品質な開発を低コストで実現
- 幅広い技術スキル:エンタープライズシステムからAI、ロボット技術まで最新技術に対応
- 柔軟な対応力:顧客の課題解決に向けた柔軟なアプローチとサポート体制
- 高スキル人材の確保:日本では不足している専門性の高いエンジニアの提供
アジャイル開発においても、専任チームが顧客の要望に応じて柔軟に対応し、仕様変更や優先順位の変更にも迅速に対応できる体制を整えています。「オフショア開発であればあるほど、メリットが増大する」というスタンスで、長期的なパートナーシップによる価値創出を重視しているのが特徴です。
保守業務においても経験豊富なエンジニアをアサインし、日常的な保守作業から緊急対応まで幅広いニーズに対応しています。
株式会社モンスターラボホールディングス

モンスターラボホールディングスは、グローバルに展開するデジタルコンサルティング企業です。
【モンスターラボの特徴】
- 専用チームによる長期的な開発体制「直ラボ」の提供
- 世界各国の拠点を活用したグローバルな開発リソース
- アジャイル開発手法とDevOpsの積極的な導入
- 戦略コンサルティングからデザイン、開発、運用までの一気通貫サービス
ラボ型開発については、クライアント専属の開発チームを組成し、同じメンバーが長期的にプロジェクトに携わる「直ラボ」というサービスを提供しています。日本と海外拠点の混合チームや、海外拠点のみのオフショア型など、ニーズに応じた柔軟な体制構築が可能です。
アジャイル開発においては、2週間程度のスプリント単位で「計画→実装→振り返り」のサイクルを繰り返すスクラム手法を採用し、仕様変更に柔軟に対応できる開発スタイルを実践しています。
オルグローラボ株式会社
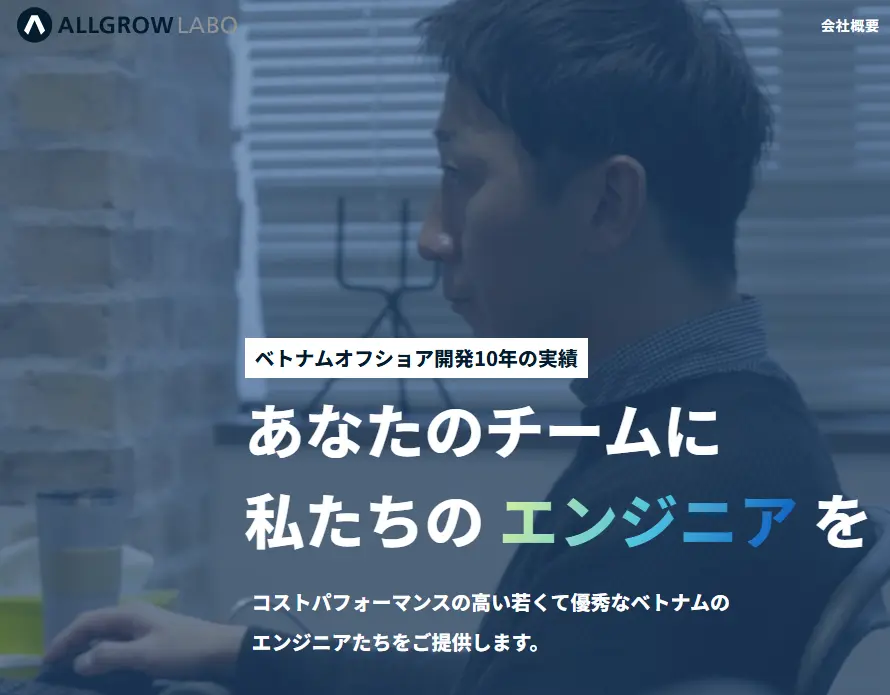
出典:オルグローラボ株式会社
オルグローラボ株式会社は、日系オフショア開発企業として10年の実績を持ち、ラボ型開発と柔軟なアジャイル手法を組み合わせた開発体制が特徴です。
【オルグローラボの特徴】
- 100名超の貸出エンジニア数と95%以上の契約更新率
- 累計2,000件以上のプロジェクト実績
- 合格率3%の厳選された優秀なベトナム人材
- 日本語対応スペシャリストによるスムーズなコミュニケーション
- ISO27001認証取得の万全のセキュリティ対策
ラボ型とアジャイル開発の組み合わせにより、プロジェクトの柔軟性と効率性を最大化。企画から保守運用まで全工程に対応可能で、顧客固有のニーズに応じたカスタマイズも得意としています。
また、以下の記事ではシステム開発が安い会社について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発が安い会社4選!費用相場や開発費用を安く済ませるポイントも紹介
まとめ
ラボ型開発とアジャイル開発の組み合わせは、変化の激しい現代のビジネス環境に適応するための効果的なアプローチです。
ラボ型開発により専任の開発チームを中長期的に確保しつつ、アジャイル手法で柔軟かつスピーディーに開発を進めることで、要件が流動的なプロジェクトや、コスト効率とスピードの両立が求められる案件、長期的な運用・保守を見据えた開発において大きな効果を発揮します。
実施にあたっては、トッパジャパン、モンスターラボホールディングス、サテライトオフィスなど、実績豊富な企業の中から自社のニーズに合ったパートナーを選定することが成功の鍵です。
海外拠点の活用によるコスト削減と、アジャイル手法による柔軟な開発プロセスを両立させることで、競争力のあるシステム開発を実現しましょう。
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説