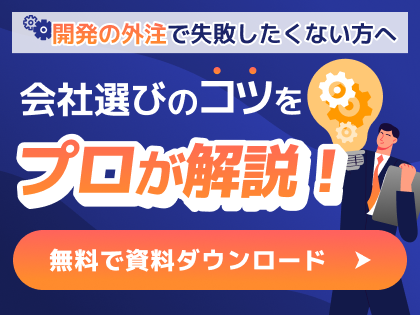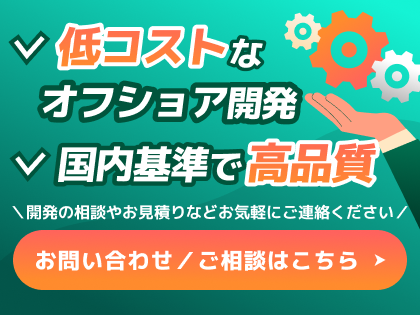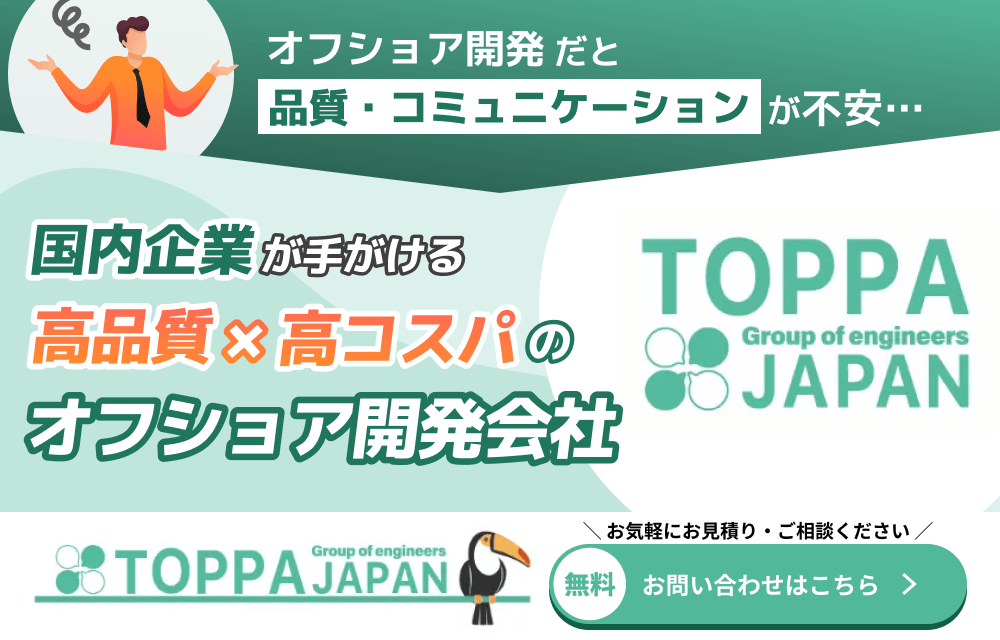企業のデジタル化が加速する中、システム開発は事業競争力を高める重要な投資となっています。しかし、多くの企業が開発コストの高騰や予算超過に悩まされており、「必要なシステムを構築したいが費用対効果が見合わない」というジレンマに直面しています。
本記事では、システム開発の主要コスト項目を整理し、コスト高騰の3つの要因を分析します。その上で、品質を犠牲にすることなくコストを削減する3つの方法と成功事例を紹介します。
システム開発を検討中の方、また進行中のプロジェクトでコスト課題に直面している方々は、本記事の内容を参考に、予算制約の中でも最大の効果を得られる開発戦略の立案にお役立てください。
システム開発における主なコスト項目

システム開発を検討する際、どのような費用が発生するのか全体像を把握することが重要です。
- 人件費(外注費)
- 設備費(サーバ・クラウド利用料など)
- プロジェクト管理費(PM・ディレクション費用)
- その他間接費(オフィス・光熱費・ツール利用料など)
本章では、システム開発における4つの主要コスト項目について詳しく解説します。
人件費(外注費)
システム開発費用の中で最も大きな割合を占めるのが人件費です。主にエンジニアやプログラマーの人件費からなり、プロジェクト全体の約8割を占めることも珍しくありません。
【開発費の主な内訳】
- エンジニアの人件費
- 外部委託先への開発費
- オフショア開発要員のコスト
- フリーランス技術者への報酬
開発費は「人月単価 × 人数 × 期間」で算出されるのが一般的です。人月単価はスキルレベルによって異なり、シニアエンジニアでは月100〜200万円、経験の少ないエンジニアなら月60〜100万円程度が相場です。
ただし、開発費は単に人数×単価だけではなく、プロジェクトの難易度や規模によっても変動します。高度な専門知識が必要なシステムや大規模プロジェクトでは、より多くの人員と時間が必要になり、結果的に総コストが増加します。
また、以下の記事ではオフショア開発の平均コストを国別に比較・紹介しています。オフショア開発を検討している場合は、あわせてご覧ください。
→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社
設備費(サーバ・クラウド利用料など)
設備費は開発に必要なハードウェアやインフラにかかる費用で、人件費に次いで大きなコスト項目となります。
【設備費の主な内訳】
- 開発用PC・周辺機器の購入費
- サーバー機器の調達コスト
- データセンター利用料
- クラウドサービス利用料金
- ネットワーク機器・回線費用
開発環境の設備費には、エンジニアが使用するコンピュータや開発ツール、テスト機器などの費用が含まれます。
完成したシステムを稼働させるための運用環境では、サーバ購入費やデータセンター利用料が主な費用となります。近年はクラウドサービスの利用が一般的になっており、初期投資を抑えられる反面、利用量に応じた月額料金が継続的に発生します。
設備費はプロジェクトの性質によって大きく異なります。小規模なWebアプリケーション開発では既存PCとクラウド環境だけで済むため設備費は最小限で済みますが、高い信頼性や処理能力が求められる金融系システムでは、冗長化された高性能サーバ(※)が必要となり設備投資額が膨らむ傾向にあります。
※サーバを二重化して、万が一どれかが故障してもシステムを止めずに稼働し続けられる仕組みのこと
また、以下の記事ではシステム開発を外注・内製するメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発を外注・内製するメリット・デメリットを解説!判断基準や開発費用も紹介
プロジェクト管理費(PM・ディレクション費用)
プロジェクト管理費はシステム開発を計画通りに進め、品質を確保するための管理業務にかかる費用です。
【プロジェクト管理費の主な内訳】
- プロジェクトマネージャーの人件費
- ディレクターやブリッジSEの人件費
- 品質管理・品質保証の費用
- 進捗管理・リスク管理に関わるコスト
- 顧客とのコミュニケーション費用
一般的に、プロジェクト全体に対する管理費の割合は10〜20%程度が適切とされています。ただし、オフショア開発のように言語や文化の違いがある場合や、複雑なプロジェクトでは管理工数が増え、全体の30%近くになることもあります。
その他間接費(オフィス・光熱費・ツール利用料など)
その他間接費は、直接的な開発作業以外に発生する様々な経費の総称です。一見すると目立たないものの、プロジェクト全体では無視できない割合を占めることがあります。
【間接費の主な内訳】
- オフィスの賃料・光熱費
- 通信費(インターネット回線、電話代)
- 交通費・渡航費・宿泊費
- 開発ツール・ソフトウェアのライセンス料
- 予備費・リスク対応費
オフィス関連の費用は、開発チームが作業するための物理的なスペースや設備に関するコストです。リモート開発でも各開発者の作業環境維持費が間接的に発生しています。
通信費や交通費は、チーム内および顧客とのコミュニケーションに必要な費用です。オフショア開発では特に、現地との調整のための渡航費や通訳費用などが発生することがあります。これらの費用はプロジェクトの進行状況によって変動します。
開発ツールやソフトウェアのライセンス費も重要な間接費です。プロジェクト専用にツールを導入する場合はその費用も計上されます。
また、以下の記事ではシステム開発の費用相場について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の費用相場は?コスト内訳や費用を安く抑えるコツも解説
システム開発のコストが上がってしまう3つの原因

システム開発プロジェクトにおいて、当初の見積もりよりも費用が膨らんでしまう状況は珍しくありません。コスト増加の原因を理解することは、予算管理の第一歩です。本章では、システム開発費用が予想以上に膨らんでしまう3つの要因について解説します。
- 原因1:開発期間の延長
- 原因2:コミュニケーション不足
- 原因3:円相場の変動でコストが増加
これらの原因を事前に認識し、適切な対策を講じることで、プロジェクトの予算超過リスクを軽減できるでしょう。
原因1:開発期間の延長
システム開発において、最も一般的なコスト増加要因が開発期間の延長です。
【開発期間延長の主な理由】
- 仕様変更や機能追加の繰り返し
- 不十分な要件定義による手戻り
- 技術的課題の解決に予想以上の時間がかかる
- リソース不足やチーム内の調整不備
- テスト工程での不具合発見と修正
システム開発費用は「人月単価×人数×期間」で計算されるため、期間が1ヶ月延びるだけでも大きなコスト増につながります。
問題なのは、開発の後半になるほど修正コストが高くなる点です。基本設計段階での変更なら影響範囲が限定的ですが、結合テスト段階での仕様変更は関連する多くのモジュールに波及し、テストのやり直しも必要になります。そのため、同じ変更でも後工程での実施は数倍のコストがかかる傾向があります。
また、以下の記事ではラボ型開発について解説しています。あわせてご覧ください。
→ ラボ型開発とは?アジャイル開発や他の契約形態の違いやおすすめの事例も紹介
原因2:コミュニケーション不足
システム開発におけるコスト増加要因の二つ目は、発注側と開発側のコミュニケーション不足です。
【コミュニケーション不足がもたらす影響】
- 認識のズレによる仕様解釈の相違
- 曖昧な要件定義から生じる実装ミス
- 開発途中での頻繁な仕様変更
- 暗黙の了解が伝わらないことによる機能不足
- ステークホルダー間の合意形成の遅れ
特に問題となるのが「手戻り」です。これは一度開発したものを作り直す作業を指し、最も非効率な状況の一つです。
例えば、顧客が「シンプルな検索機能」を求めていたのに対し、開発側が「高度なフィルタリング機能つき」と解釈して実装した場合、不要な機能開発に時間を費やすだけでなく、後から作り直す二重の工数が発生します。
原因3:円相場の変動でコストが増加
コスト上昇の要因の一つが円相場の変動です。特に円安傾向の場合、さまざまな経路を通じてプロジェクト予算に影響を与えます。
まず、海外調達に依存するハードウェア・クラウドサービス・開発ツールのコストが直接的に上昇します。日本企業が必要とするITインフラの多くが輸入に頼っているため、円安はシステム開発の基盤コストを押し上げる要因となっています。
これらの課題に対し、オフショア開発は効果的な解決策となります。現地通貨建ての契約により円相場変動の影響を軽減でき、東南アジアなど為替が比較的安定した地域を選ぶことでコスト予測の精度も向上します。
また、以下の記事ではシステム開発の見積もりについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発の見積もりの見方を解説!見積書の項目や見積もり手法・算出方法も紹介
システム開発のコストを削減する3つの方法

システム開発はビジネス成長に欠かせない投資である一方で、予算制約の中で最大の効果を得ることが課題となっています。しかし、適切な方法を選べば、品質を犠牲にすることなくコスト削減が可能です。
- 要件定義を細かく設定する
- オフショア開発を活用する
- 補助金や助成金を活用する
本章では、システム開発コストを効果的に削減する3つの方法を解説します。これらの手法を組み合わせることで、限られた予算内でも高品質なシステム開発を実現し、ビジネスの成長を加速させることができるでしょう。
要件定義を細かく設定する
システム開発コスト削減の第一歩は、徹底的な要件定義にあります。多くのプロジェクトでは、曖昧な要件定義が手戻りや追加開発を招き、結果的にコスト増加を引き起こしています。
【要件定義で明確にすべき項目】
- 具体的なシステム目的と期待される効果
- 必須機能と優先順位
- ユーザーのワークフローや使用シーン
- 既存システムとの連携ポイント
- 非機能要件(性能、セキュリティ、運用・保守条件)
要件定義の詳細化・明確化がコスト削減に効果的な理由は、開発の初期段階での変更コストが最も低いためです。
設計段階での修正は数時間で済むことが、開発後半での修正では数日、リリース後なら数週間かかるケースも珍しくありません。そのため、開発前に十分な時間をかけて要件を固めることが、結果的にはコスト削減につながります。
オフショア開発を活用する
人件費が開発コストの大部分を占めるシステム開発において、オフショア開発は効果的なコスト削減策です。海外の技術者を活用することで、国内開発に比べて大幅な人件費削減が可能になります。
【オフショア開発のメリット】
- 人件費の大幅削減(国内の1/2〜1/3程度)
- 豊富な人材プールによる適材適所の配置
- 国内では不足しがちな専門技術者の確保
- スケールアップ・ダウンの柔軟性
オフショア開発を成功させるには適切な進め方が重要です。言語や文化の違いを踏まえたコミュニケーション体制の構築・詳細な仕様書の作成・適切な品質管理プロセスの導入などが不可欠です。
これらの対策なしにオフショアを導入すると、コミュニケーションコストや品質問題による手戻りで、結果的にコスト増になるリスクもあります。
また、以下の記事ではベトナムでラボ型開発を行うメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ ベトナムでラボ型開発を行うメリットは?注意点やおすすめの会社も紹介
補助金や助成金を活用する
システム開発コストの実質的な削減方法として、国や自治体が提供する補助金・助成金の活用があります。特にDXやIT化を促進する目的で様々な支援制度が用意されており、これらを上手く利用することで開発予算を大幅に拡大できる可能性があります。
【主な補助金・助成金の種類】
以下に、中小企業向けの主要なIT関連補助金・支援制度3種類について、「対象者」「補助対象」「補助率・上限額」の観点で比較した表を示します。
| 制度 | 補助対象 | 補助率・上限額 |
| IT導入補助金 | 業務効率化・生産性向上につながるITツール導入費用 | 補助率: 通常1/2(小規模事業者等は条件により3/4~4/5まで引上げ特例あり)上限額: 最大450万円まで補助 |
| ものづくり補助金 | 革新的な製品・サービス開発等のための経費 | 補助率: 1/2(小規模事業者等は2/3)上限額:最大2,500万円 |
| 持続化補助金 | 小規模事業者の販路開拓や業務効率化を支援 | 補助率:2/3上限額:通常枠で最大50万円 |
各制度とも公募時期や詳細要件が更新される場合があるため、申請時には最新の公式情報を確認するようにしてください。
システム開発のコスト削減についてよくある質問

ここでは、システム開発のコスト削減についてよくある質問に回答していきます。
削減してはいけないコストはありますか?
品質保証と上流工程に関わるコストは削減すべきではありません。
特にテスト工程の簡略化は危険です。短期的には費用削減に見えても、リリース後の不具合発見や緊急修正のコストは開発段階の数倍になることもあります。
また、要件定義や基本設計などの上流工程への投資も重要です。ここでの検討不足は後工程での大幅な手戻りを引き起こし、結果的にコスト増加につながる可能性が高いからです。さらに、プロジェクト管理やコミュニケーションに関するコストも必要な投資です。
適切な経験・スキルを持つ人材の確保も安易に削るべきではありません。短期的には高コストに見えても、品質向上や生産性向上により総コストを抑制できることが多いです。
コスト削減は必要ですが、将来大きなリスクと損失を招く可能性がある部分は、コストを削るべきではないでしょう。
開発途中で追加機能が必要になった場合はどうすればいいですか?
開発途中での機能追加は「変更管理」の手順に従って対応すべきです。
まず、追加機能の必要性と優先度を関係者で確認し、変更内容と影響範囲を明確化します。次に「変更管理書」を作成し、変更内容・追加コスト・スケジュールへの影響を文書化して合意を得ます。
この正式な手続きは、曖昧な口頭ベースの合意が後々のトラブルに発展するのを防ぐために非常に有効です。特に追加費用の根拠を示す証拠となるため、双方の認識の相違を防止できます。
もし現行予算や期間内での対応が難しい場合は、以下の選択肢を検討しましょう。
- 優先度の低い既存機能と入れ替える
- 次期開発フェーズに回す
- プロジェクトスコープを拡大して予算・期間を再設定する
また、以下の記事では教育業界におけるシステム開発について解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育業界で求められるシステム開発とは?おすすめの開発会社も紹介
実際にコスト削減を実現した企業の成功事例
ある国立大学が実施した、オンプレミス環境からクラウドへの移行プロジェクトは、コスト削減の優れた事例です。
この大学ではIT運用コスト削減を目的に、既存のオンプレミス環境を複数のクラウドサービスへ移行するプロジェクトを計画。
セキュリティ要件から国内外のクラウドサービスを併用する必要があったため、クラウド移行の豊富な経験を持つトッパジャパンに依頼しました。
3ヵ月という短期間でプロジェクトは完了し、設計・移行・構築・保守のみならず、情報共有や業務自動化のためのツール開発も同時に行われたことが特徴です。
当初の予想を上回る経費削減を実現し、削減できた予算は学生募集戦略に振り向けられ、本来の学術活動強化にも貢献しました。
また、以下の記事ではシステム開発が安い会社について解説しています。あわせてご覧ください。
→ システム開発が安い会社4選!費用相場や開発費用を安く済ませるポイントも紹介
まとめ
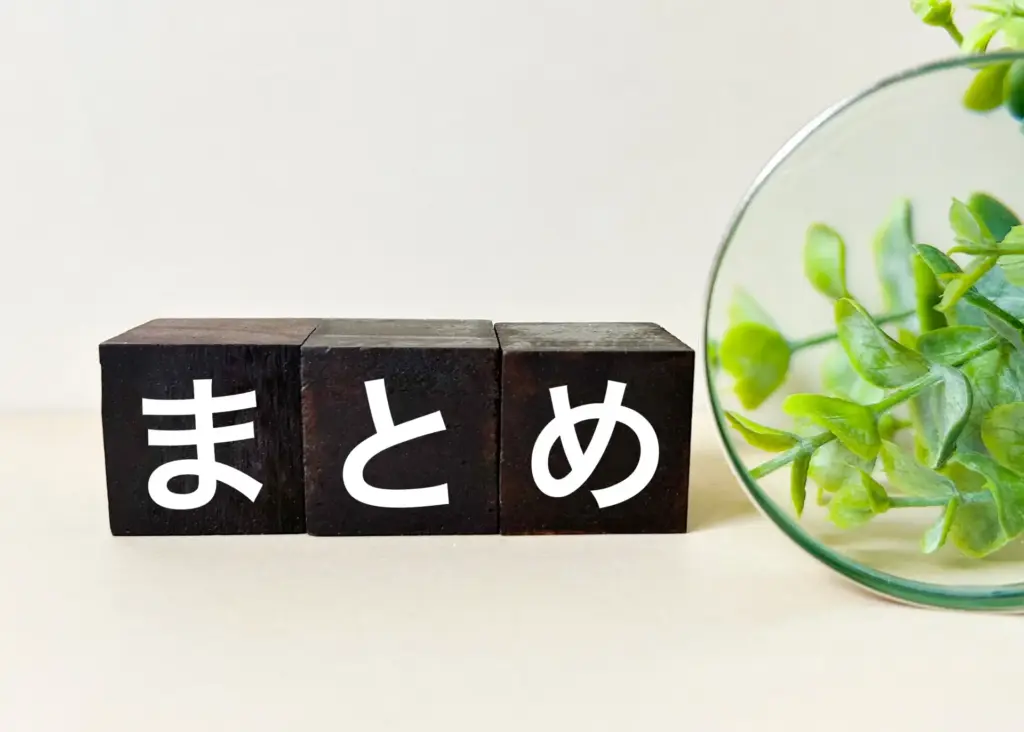
システム開発コストの適切な管理は、IT投資効果を最大化するための重要なポイントです。
本記事では、開発費用の内訳とコスト増加要因を明らかにした上で、効果的な削減策を紹介しました。特に重要なのは、コスト削減と品質確保のバランスを取ることです。
要件定義の詳細化・明確化は初期工数が増えても後工程での手戻りを防ぎ、オフショア開発は適切な管理体制があれば国内開発の1/2〜1/3のコストで同等品質を実現できます。
また、IT導入補助金などの公的支援制度を活用すれば、実質的な負担を大幅に軽減できる可能性もあります。コストを削るべき部分と投資すべき部分を見極め、長期的な視点で総コストの最適化を図ることが成功の鍵です。
まずは自社の開発プロジェクトのコスト構造を見直し、どの削減策が適用可能か検討してみましょう。
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説