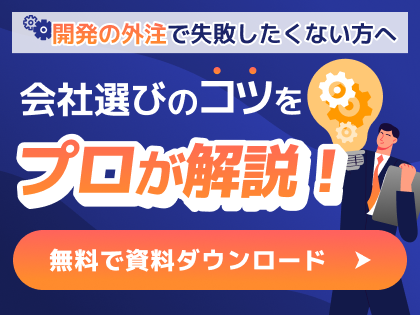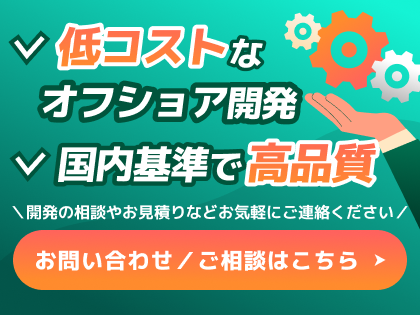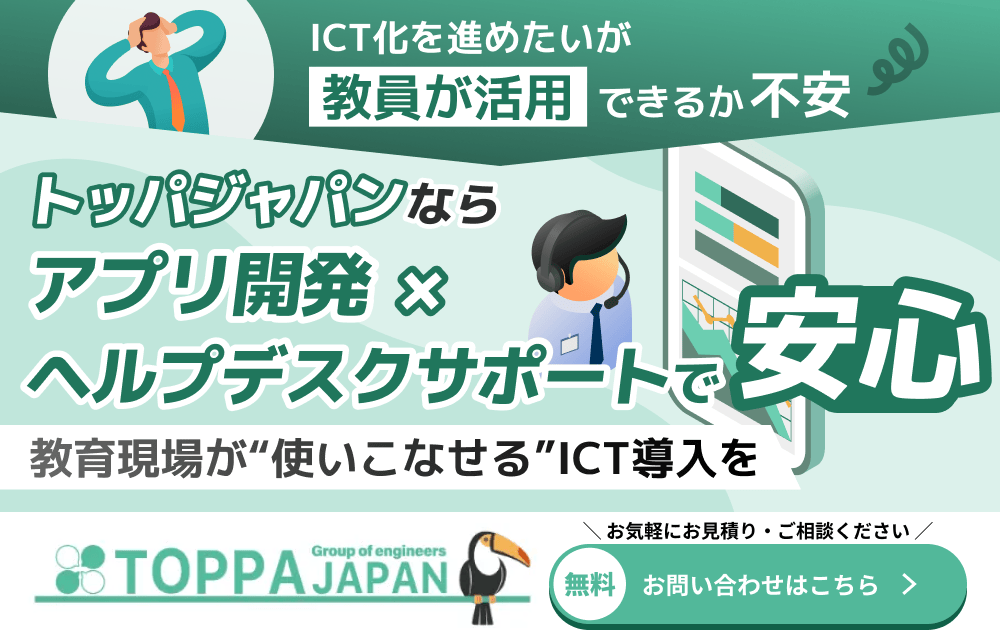近年、教育現場においてもDXの波が押し寄せ、中でもAIの活用に注目が集まっています。
AIは授業の質の向上・教員の業務負担軽減、そして生徒一人ひとりに最適化された学びの提供といった、教育現場が抱える多くの課題を解決することが期待されています。
しかし「具体的に何から始めれば良いのか」「自校の課題にどう活かせるのか」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「教育DX」の基本的な考え方と、AIを活用した事例や教育現場で利用できるAIの種類、AIがもたらすメリットと注意すべき点を解説します。
AI活用の具体的なイメージを掴むため、ぜひ参考にしてください。
「教育DX」とは

教育DXとは、デジタル技術を効果的に活用することで「新しい学びの形」を実現し、同時に「持続可能な教育環境」を築き上げていくことを目指す取り組みです。
主な目的は、以下の3つです。
- 個別最適化学習:データで一人ひとりに合う教育
- STEAM教育:先端技術で教科横断的な学び
- 教員の働き方改革:校務DXで本来業務へ集中
この章では、教育DXが具体的にどのような変革をもたらし、私たちの教育現場がどう変わっていくのかを解説します。
教育現場でAI活用が急速に進んでいる理由
教育現場でAI活用が進む背景には、GIGAスクール構想によるICT環境の整備があります。全国の公立学校に高速ネットワークと1人1台の学習端末が配備され、オンライン教材やクラウドサービスの活用が可能となりました。
次に、AI技術の飛躍的な進化があります。近年はChatGPTなどの生成AIをはじめ機械学習の性能が向上し、教材作成や学習サポートを自動化できるようになっています。
政府も教育DXロードマップで「生成AIを教員の働き方改革や学びの充実に活用する方針」を明記し、実証事業や予算措置で支援を進めています。
さらに、都道府県・市区町村レベルでも導入事例が増えており、東京都では全都立学校(256校)で生成AIを活用した学習を開始するなど、官民が連携してAI活用を推進しています。
また、以下の記事ではeラーニングについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ eラーニングとは?基礎知識や導入するメリット・デメリットを解説
出典:東京都教育委員会「全都立学校で生成AIを活用した学習が始まります!」
文部科学省の「生成AI活用ガイドライン」の概要
文部科学省は、2023年7月に「初等中等教育向けの生成AI利活用ガイドライン(暫定版)」を公表し、2024年12月に改訂版をまとめました。
このガイドラインでは、生成AIを「有用な道具」と位置付け、出力結果をあくまで参考情報の一つとし、最終的な判断・責任は教員など人間が負うことを強調しています。
生徒の情報活用能力を育成する重要性も指摘し、生成AIを学びに活かす視点を教育に組み込むよう求めています。
具体的には、教員が校務文書の自動作成やテスト採点の効率化に活用して働き方改革を進めること、生徒は発達段階や学習目標に応じて生成AIを活用・検証することが示されました。
出典:文部科学省「初等中等教育段階における 生成AIの利活用に関するガイドライン」
AIを活用した授業の事例

本章では、AIが実際の教育現場でどのように活用され、どのような成果を上げているのか、具体的な事例をご紹介します。
- 事例1:生成AIを活用した校務の実践
- 事例2:生成AIによる授業プランの作成
- 事例3:画像生成AIを用いた表現力向上
事例をご覧いただくことで、学校や授業でAIを活用する際の具体的なイメージが湧くでしょう。
事例1:生成AIを活用した校務の実践
札幌市立発寒東小学校では、生成AIを校務のさまざまな場面で取り入れ、業務の効率化と教育の質の向上を図る試みが行われています。。
主な活用例
- 学力向上策に関するアイデアの創出
- 通知表の所見文案の作成
- 問題行動が見られる児童への指導に関する助言
- 保護者向けアンケート結果の整理・分析
- 長文資料の内容把握や要点の抽出
- 授業中の発問に対する応答シミュレーション
- 説明用パワーポイント資料の骨子作成
ChatGPTのような対話型のAIはもとより、既存の文書データを読み込ませることで、その内容に関する質問応答システムを構築できるAIや、パワーポイント資料を自動で形にするAIツールまで、多岐にわたる技術が活用されています。
参考:生成AI(ChatGPTなど)を活用した校務の実践事例
事例2:生成AIによる授業プランの作成
仙台市教育委員会、西多賀中学校および金剛沢小学校では、「高度情報社会の一員として大切なことについて考えよう」というテーマで、2時限構成の学習指導案がAIを活用して作成され、市内の学校へ共有されました。
指導案の工夫
- 授業を進めるうえでのポイントを吹き出し形式でわかりやすく提示
- 生成AIの具体的な使用例や生徒の思考を促すためのツールを共有
- 教員が発問などを柔軟に調整できるよう具体的な発問例を盛り込む
実際に授業を行った教員方からは、「指導の要点が明確に示されていて、授業に取り組みやすかった」「授業の準備作業がスムーズに進み、ICTの操作に不慣れな教員でも容易に扱えた」といった肯定的な意見が寄せられました。
参考:生成AI授業プランの作成
事例3:画像生成AIを用いた表現力向上
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校の英語科では、画像生成AI「DALL·E」をライティングの授業へ導入しました。
生徒たちは「近未来都市」をテーマに、英語で自身が思い描く都市のイメージをAIに伝えるための指示文(プロンプト)を作成・入力します。
AIは与えられた指示に基づいて画像を生成するため、生徒はより的確な語彙や表現を考え、自身の意図を正確に伝える必要性を体験的に学びました。
授業を受けた生徒たちからは、「自分が考えた通りにAIにイラストを生成させるために、どのように具体的な言葉で伝えれば良いかを考えるのが面白かった」 といった感想が寄せられています。
また、以下の記事ではeラーニングのおすすめ開発会社について解説しています。あわせてご覧ください。
→ eラーニングシステムのおすすめの開発会社13選!選び方や費用相場も解説
参考:Writingの授業における画像生成AI(DALL.E)を用いた表現力向上(英語科)
教育現場で活用できるAIの種類

AIと一口に言っても、その種類や得意分野は多岐にわたります。AIの能力を最大限に引き出すためには、どのような種類のAIが存在し、それぞれが何を得意としているのかを理解することが大切です。
- 認識系AI
- 予測系AI
- 実行系AI ・最適化AI
- 生成系AI
この章では、教育現場での活用が期待される代表的なAIの種類を、それぞれの特性や具体的な活用イメージとともに解説していきます。
認識系AI
認識系AIは、まるで人間の目や耳のように、与えられたデータが「何であるか」を識別し理解する能力に長けたAIです。画像、音声、あるいはテキストなどの情報を分析し、内容やパターンを的確に捉えることを得意としています。
教育現場での活用イメージ
- 画像認識: 手書き文字のデジタル化、実験結果の画像分析
- 音声認識: 外国語の発音評価、議事録作成の自動化
- 文字認識: 提出レポートのテキストデータ化
例えば生徒が書いた答案用紙の手書き文字をAIが読み取ってデジタル化したり、外国語学習において生徒の発話をAIが認識し、発音の正確さについてフィードバックを行ったりといった活用が考えられるでしょう。
これにより、採点業務の効率化や、より個別化された言語学習支援が期待できます。
また、以下の記事ではオフショア開発の国別平均コストや国内開発との違いを比較・解説しています。教育系AIの開発を検討している場合は、あわせてご覧ください。
→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社
予測系AI
予測系AIは、過去に蓄積された膨大なデータの中から特定のパターンや傾向を学習し、未来に起こりうる出来事や数値を推測する能力を持つAIです。過去の情報を整理するだけでなく、そこから未来への洞察を得ることを目指します。
教育現場での活用イメージ
- 学習分析: 生徒の成績推移予測、つまずき箇所の早期発見
- 進路・キャリア予測: 適性や興味に合う進路選択のサポート
- 中退予防: リスクのある生徒の早期特定と介入
生徒一人ひとりの学習履歴やテストの成績といったデータをAIが分析することで、将来的な成績の伸びを予測したり、特定の単元でつまずきやすい生徒を早期に発見したりすることが可能になるかもしれません。
さらには、個々の生徒の興味や適性に合った進路選択を支援するための情報を提供するなど、よりきめ細やかな個別指導やキャリア教育の実現に貢献する可能性があります。
実行系AI ・最適化AI
実行系AIや最適化AIは、あらかじめ設定された目標に対して最も効果的な行動計画を自ら考え出して実行したり、あるいは複雑な条件が絡み合う中で最良の解決策を見つけ出したりする能力に秀でたAIです。
作業を自動化するだけでなく、そのプロセス全体をより効率的に、そしてより良い結果へと導くことを得意としています。
教育現場での活用イメージ
- アダプティブラーニング: 個々の理解度に応じた教材提供
- 時間割作成の最適化: 教員や教室の条件を考慮し自動作成
- 人員配置の最適化: 学校行事等の効率的なスタッフ配置
教育分野における代表的な例としては、生徒一人ひとりの理解度や学習の進捗状況に合わせて、問題の難易度や提示する教材の内容をAIがリアルタイムで調整する「アダプティブラーニング(適応学習)」システムが挙げられます。
また、教員や教室の利用状況・各教科の必要コマ数といった複雑な条件を考慮しながら、最適な時間割案をAIが瞬時に作成する実証研究も進められており、教員の負担を軽減できると期待されています。
生成系AI
生成系AIは、既存のデータを学習することで、これまで世の中になかった新しいオリジナルのコンテンツを創り出す力を持つ、今最も注目されているAIの一つと言えるでしょう。
テキストの作成、画像やイラストの描画、さらには音楽や音声、動画、そしてプログラムコードに至るまで、多様な形式のデータを新たに生成する能力を持っています。
教育現場での活用イメージ
- テキスト生成: 授業用資料の草案作成、読解問題の作成
- 画像生成: 授業で使うオリジナルイラストの作成
- 音声合成: 教材用ナレーション作成、外国語学習支援
- 動画生成: 学習内容を解説するショート動画の作成
人間と自然な会話を行うChatGPTのような対話型AIや、入力したキーワードや簡単な指示から写真のようにリアルな画像を生成するAI、あるいは人間の声を模倣して滑らかに文章を読み上げる音声合成技術などが挙げられます。
また、以下の記事では教育アプリをオフショア開発するメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育アプリをオフショア開発するメリットは?費用相場やおすすめの開発会社も紹介
AIが教育現場にもたらす4つのメリット

AIが教育現場にもたらす恩恵は多岐にわたりますが、ここでは特に注目すべき4つのメリットに焦点を当てて解説します。
- 教員の業務負担の軽減
- 生徒一人ひとりに合わせた個別最適化学習の提供
- 生徒の学習意欲・探求心の向上
- データに基づいた客観的な教育効果の測定と改善
一つひとつのメリットを詳しく見ていきましょう。
教員の業務負担の軽減
授業準備やテスト作成、成績処理といった多岐にわたる校務をAIが自動化・効率化することで、教員の業務負担を軽減し、その分時間を生み出すことが期待されています。
このようにして生まれた時間は、生徒一人ひとりと向き合うための個別指導や教材研究、新しい教育手法の導入検討など、教育の質を高めるための活動に充てられるでしょう。
生徒一人ひとりに合わせた個別最適化学習の提供
AIが学習データをきめ細かく分析し、それぞれの特性に応じた最適な学習カリキュラムや教材を自動で生成することで、生徒一人ひとりの学習進度や理解度、興味・関心に合わせた「個別最適化学習」を実現できます。
文部科学省も、これからの教育のあり方として「個別最適化学習」の重要性を強調しており、生徒の多様な個性や能力に応じた柔軟な学習提供体制の構築を目指しています。
従来の一律的な授業形態では、全ての生徒のニーズに完全に応えることは難しい側面がありました。
しかし、AIを活用すれば、それぞれの生徒が抱える弱点の克服や、特に興味を持つ分野の深掘りといった、よりパーソナルな指導が可能となり、学習効率の向上が期待できるのです。
生徒の学習意欲・探求心の向上
生成AIの活用は生徒の知的好奇心を刺激し、創造性を育むことで、学習への意欲や探求心を高める効果が期待されます。
AIが生徒それぞれの興味関心に寄り添った教材を提示したり、これまでにない発想を促すような創造的な課題を設定したりすることが、そのきっかけとなるでしょう。
プロジェクト型の学習や、「学びを遊びに変える」ような体験を通して、生徒たちはより主体的に、そして積極的に学習に取り組むようになることが期待されます。
データに基づいた客観的な教育効果の測定と改善
テストの結果や日々の学習履歴といった膨大な量の学習データをAIが収集・分析することで、これまで見えにくかった生徒たちの学習状況を可視化できるようになります。
教員はダッシュボードでクラス全体や個々の理解度をリアルタイムに把握し、どこでつまずいているかを瞬時に特定できます。
さらに、個々の学習ログと成績などの成果を結び付けて分析すれば、AIが学習成果の指標を示し、授業や指導方法の改善に役立てることが可能です。
AI導入の前に知っておきたい注意点・デメリット
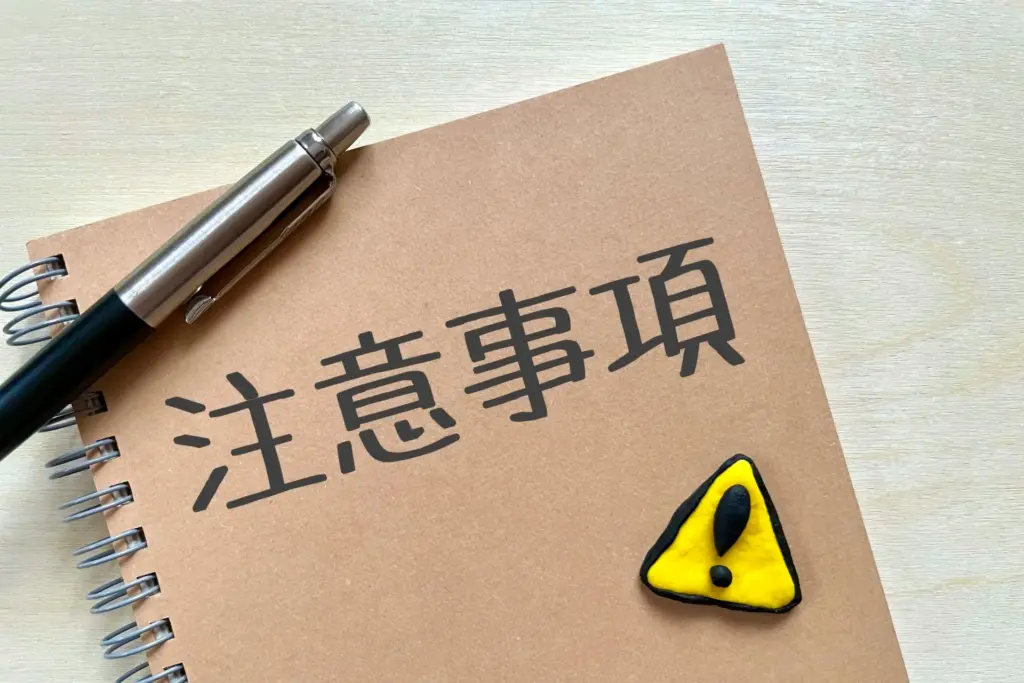
AI導入はさまざまなメリットが期待できますが、導入する前に把握しておくべき注意点やデメリットもあります。
- データプライバシーとセキュリティの問題
- 生徒の思考力や自律性の低下
- 初期コストとインフラ整備の負担
それぞれ詳しくみていきましょう。
データプライバシーとセキュリティの問題
AIを教育現場で活用する際には、生徒の個人情報や学習データを扱うことになるため、これらの情報をいかに安全に管理し、プライバシーを保護するかが重要な課題となります。
万が一にも情報が外部に漏洩するようなことがあれば、その影響は計り知れません。
文部科学省が示すガイドラインにおいても、生成AIを利用する際には個人情報保護法をはじめとする関連法令を遵守することが求められています。
具体的には、生徒の氏名や顔写真といった、個人を特定できる情報をAIシステムに直接入力しないよう、現場での指導徹底が求められています。
出典:文部科学省「「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」公表について」
生徒の思考力や自律性の低下
AIは便利なツールですが過度に依存してしまうと、生徒自身が課題解決に向けて試行錯誤したり、深く思考を巡らせたりする貴重な機会が失われてしまうのではないか、という懸念があります。
特に、AIを使えば簡単に正解にたどり着けるような課題ばかりに取り組んでいると、授業中に生徒たちが自力で考えたり、仲間と意見を交わしたりするような、本質的な学びのプロセスが促されにくくなるかもしれません。
文部科学省のガイドラインでも、AIの出力を鵜呑みにするのではなく、それをたたき台として生徒自身の思考力をさらに伸ばしていくようなAIとの付き合い方を指導することが強調されています。
初期コストとインフラ整備の負担
AI導入を進めるうえで、初期投資と継続的な運用コストは避けて通れない課題です。
機材の購入やネットワーク環境の整備、そして教員向けの研修などにまとまった初期費用がかかります。さらに、システム導入後も機能を維持するための管理費用や、必要に応じたアップデート、消耗品の交換といったランニングコストが継続的に発生します。
そのため、目先の導入費用だけでなく、長期的な視点で費用対効果を検討し、計画的な予算確保とコスト管理を行っていくことが大切です。
また、以下の記事では教育アプリの開発費用相場について解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育アプリの開発費用相場を解説!見積り前にやるべきことも紹介
教育DX・AI活用を成功に導く5ステップ

教育DXやAI活用を成功させるためには、やみくもに進めるのではなく、計画的に進めることが大切です。
この章では、以下の5つのステップに分けて解説していきます。
- Step1: 目的設定と現状課題の洗い出し
- Step2: 適切なパートナーの選定と情報セキュリティ対策
- Step3: 教職員への研修と情報共有
- Step4: スモールスタートで効果検証
- Step5: 継続的な評価・改善と成功事例の横展開
導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
Step1: 目的設定と現状課題の洗い出し
教育DXやAI活用を成功させるための最初のステップは、「何のために導入するのか」という目的を明確に定め、「現状、どのような課題があるのか」を徹底的に洗い出すことです。
例えば、「生徒一人ひとりに合わせた学習支援を実現したい」「教員の事務作業の負担を軽減したい」といった具体的な目的を設定します。
その上で現状を調査し、現場が直面している課題を具体的に把握することが重要です。
Step2: 適切なパートナーの選定と情報セキュリティ対策
教育DXをスムーズに進めるためには、信頼できる外部のパートナーを選定することと、情報セキュリティ対策に万全を期すことが重要です。
DXの実施にあたっては、教育現場の視点を持ち、真摯に課題解決に取り組んでくれる事業者をパートナーとして選ぶことが求められます。
利益を追求するあまり現場のニーズを軽視するのではなく、生徒や教員の立場を深く理解し、共に問題解決を目指す姿勢のある企業を選ぶべきでしょう。
同時に、情報セキュリティ対策の構築は最優先事項です。教育現場は、子どもたちや保護者に関する機微な情報を取り扱う特殊性があるため、文部科学省は学校や教育委員会を対象とした専用のセキュリティガイドラインを策定しています。
Step3: 教職員への研修と情報共有
新たな技術やシステムを導入したとしても、実際に活用する教員のスキルが伴わなければ意味がありません。したがって、教員一人ひとりの育成と、組織全体での情報共有体制の構築が必要です。
そのため、ICTスキルやAIリテラシー向上のための研修を積極的に実施していく必要があります。
また、AIを活用した授業改善のアイデアや成功事例などをリアルタイムで共有する体制も必要でしょう。
Step4: スモールスタートで効果検証
新しい技術やシステムを導入する際は大規模に一斉展開するのではなく、まず小規模な範囲で試行し、その効果を慎重に検証する「スモールスタート」のアプローチが有効です。
教育DXのような変革を伴う取り組みでは、初期段階で予期せぬ課題や改善点が見つかることも少なくありません。
小さく始めることで万が一のリスクを最小限に抑えつつ、実際の運用を通じて具体的な効果や問題点を早期に把握できます。
この検証結果をもとに計画を見直し、改善を重ねながら段階的に本格的な展開へと繋げていくことが、最終的な成功の確率を高めるのです。
Step5: 継続的な評価・改善と成功事例の横展開
新しい取り組みを導入した後は、効果を継続的に評価し改善を重ねる「PDCAサイクル」の実践と、そこで得られた成功体験や有益な知識を組織内外で積極的に共有する「横展開」が重要です。
一度導入して終わりにするのではなく、常に現状をより良くしようと改善を続けることで、取り組みの効果は最大限に高められます。
また、一部で生まれた成功事例やノウハウを組織全体で共有することで、他の部署や担当者もその恩恵を受けられ、全体のレベルアップに繋がります。
また、以下の記事では教育アプリの開発会社について解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育アプリの開発会社おすすめランキング19選!選び方や費用相場も解説
トッパジャパンが実現する教育現場のDXとAIソリューション

教育現場のDXやAIの導入や運用には「教員がICTを使いこなせるだろうか」「トラブル対応はどうしよう」「何から手を付ければ良いのか」といったさまざまな課題や不安が伴うでしょう。
トッパジャパンは教育現場特有の悩みに寄り添い、ICT活用に関するあらゆる不安を解消するためのソリューションを提供しています。
主なサポート内容
| 課題 | 主なサポート内容 | 2024年度支援実績 |
| ICT活用の不安 | 「ICT支援・ヘルプデスク」教員のICTスキル向上を操作研修や日々のサポートで支援 | 48校 |
| 機器トラブル対応 | 「保守・メンテナンス」故障やサーバートラブル時、経験豊富な技術者が迅速に対応 | 61校 |
| ICT環境の整備・DX推進 | 「教育ICT・DXコンサルティング」「何から始めれば?」というお悩みに最適なICT環境設計やセキュリティ対策を具体的に提案 | 48校 |
| GIGA端末の導入 | 「GIGA端末・教育IT機器の導入支援」セキュリティを考慮したGIGA端末の導入・活用をサポート | 48校 |
| その他 | 専門的なニーズにも幅広く対応特別支援教育の現場で求められる個別のニーズに応じたアプリ開発文部科学省の基準に準拠したネットワークインフラの設計・実装 | ― |
以下は、トッパジャパンが教育機関向けに開発した、AIを使った迷惑メール判別ツールのプロジェクト事例です。
| お客様 | プロジェクトの概要 | 開発期間 | 課題 |
| 大学 | 迷惑メール判別ツール開発プロジェクト | 2ヵ月 | 学生や職員宛に届くメールについての問い合わせが多くあり、特に海外からのメールが、迷惑メールか問題のないメールなのかの判断に時間を取られていた |
上記課題に対し、メールを自動で迷惑メールか判断するAIツールを作成し、担当者の負担を軽減することができました。軽減した分は、他のセキュリティ強化の時間に使うことができるようになりました。
教育現場のDX推進、そしてAI活用に関するあらゆる課題に対し、トッパジャパンは確かな技術と教育現場での豊富な実績をもって、新しい教育の実現を全力でサポートいたします。どのようなお悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
AI活用は、教員の業務負担軽減、生徒一人ひとりに合わせた個別最適化学習の提供、学習意欲・探求心の向上、データに基づいた教育効果の測定と改善といったメリットをもたらす一方で、データプライバシーやセキュリティ、生徒の思考力低下への懸念、初期コストといったデメリットも存在します。
これらの課題を乗り越え、AI活用を成功させるためには、目的設定と現状課題の洗い出しから始まり、適切なパートナー選定、教職員研修、スモールスタートでの効果検証、そして継続的な評価・改善と成功事例の横展開という5つのステップを着実に進めることが重要です。
AIは教育の未来を大きく変える可能性を秘めています。本記事を参考に、まずは情報収集や小さな試みから、AI活用の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説