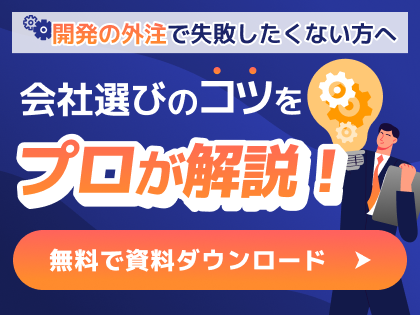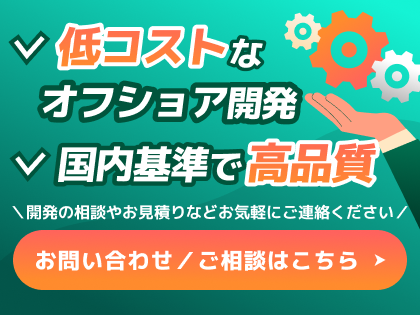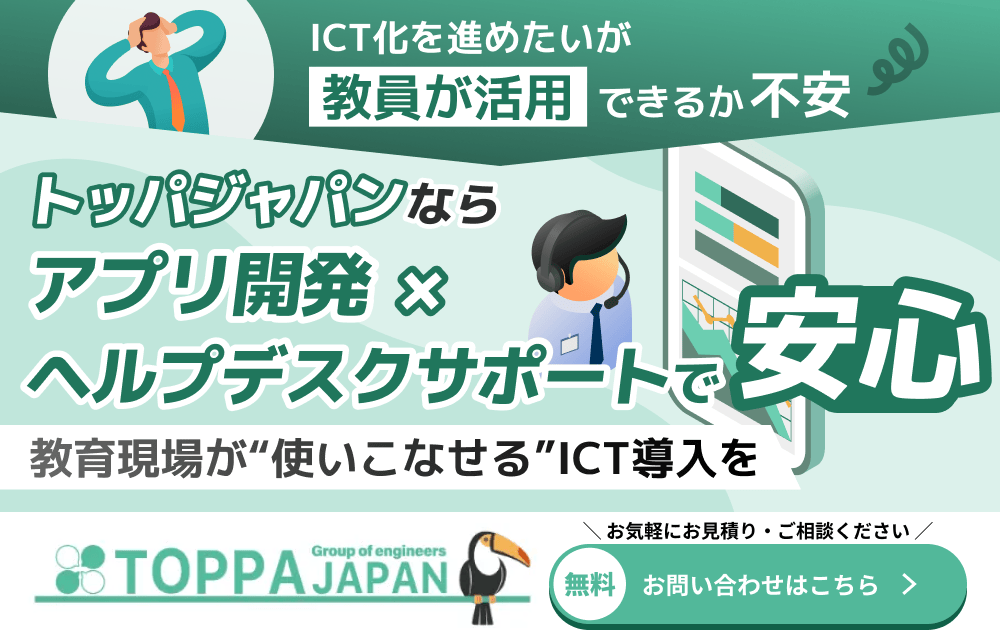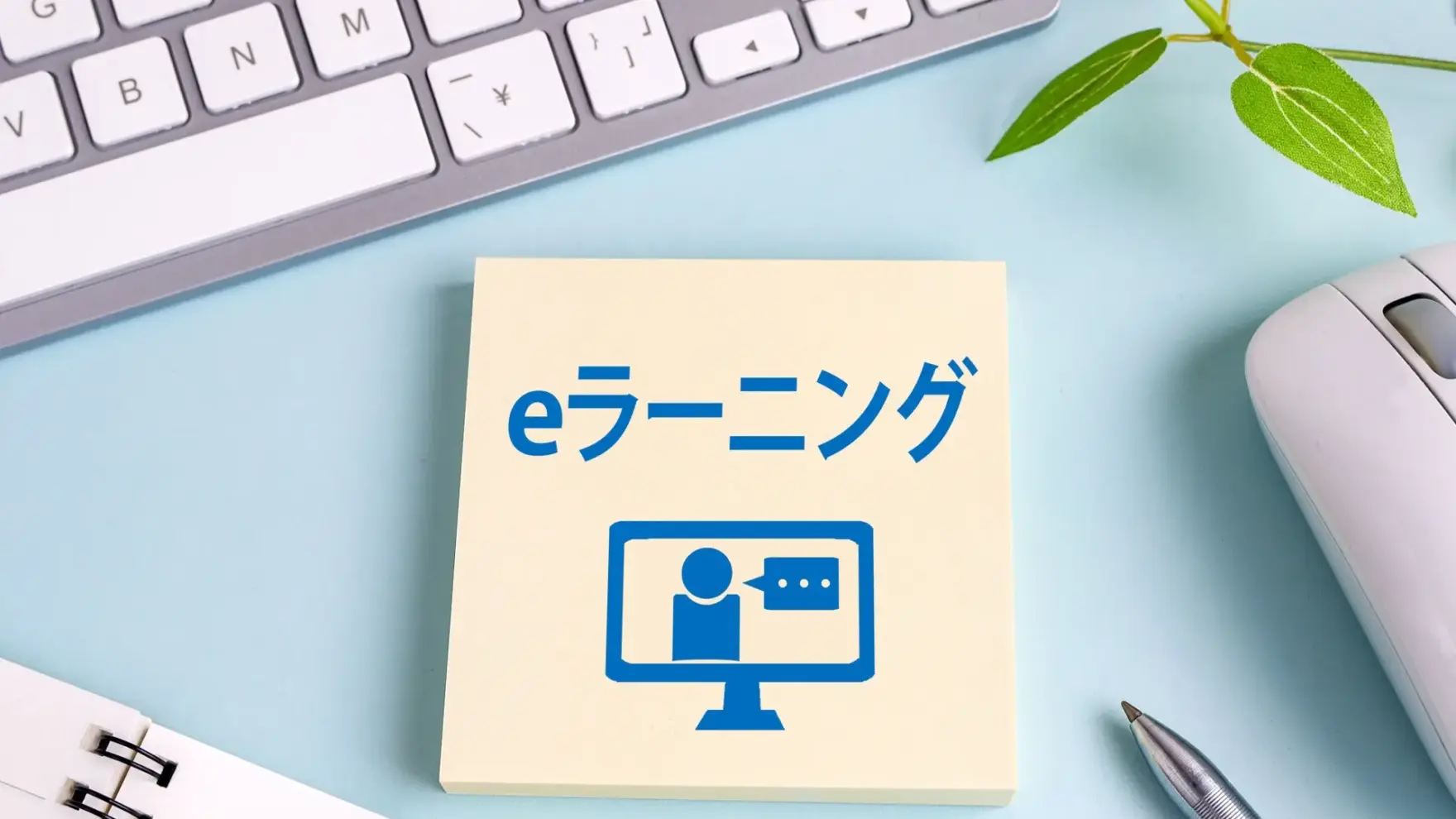
働き方の多様化が進む現代、効率的で効果的な人材育成は企業の成長に欠かせません。
その有力な手段として注目されるのがeラーニングですが、いざ導入を検討し始めると、「そもそも何から学べば良いのか」と戸惑う研修担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「eラーニングとは何か」という基礎知識から、具体的な機能、企業・受講者双方のメリット・デメリットまで解説します。
さらに、学習効果を最大限に高めるためのシステムの条件や、導入で失敗しないための具体的な5つのステップもご紹介。eラーニングの全体像を体系的に理解できる内容です。
eラーニングとは?

新人研修のオンライン化を任されたが、「eラーニングって、そもそも何だろう?」と思っている方もいるのではないでしょうか。
この章では、eラーニングの基本的な意味から、その歴史、学習を支える仕組み、そして企業が導入する目的までを解説します。
eラーニングの歴史
eラーニングの歴史は意外と古く、その起源は1950年代にまで遡ります。
【eラーニングの進化の歴史】
- 1950年代: コンピュータ支援教育(CAI)が起源
- 1990年代: PC普及でCBT(コンピュータベーストレーニング)、WBT(ウェブベーストレーニング)へと進化
- 2000年代: 日本でも「eラーニング元年」
- 現在: スマホ普及で隙間時間に学習可能に
その始まりは、コンピュータを使った教育(CAI)でした。その後、パソコンの普及とともにCD-ROM教材を使う形が広まり、インターネットの発展でウェブを通じた学習へと形を変えてきました。
2000年代には政府の後押しもあり日本で急速に普及し、今ではスマホを使って通勤中などに手軽に学ぶスタイルが定着しています。
eラーニングの仕組み
eラーニングの仕組みは、学習コンテンツである「教材」と、学習を管理する「LMS(ラーニング・マネジメント・システムの略)」という2つの要素で成り立っています。
【eラーニングを構成する2つの要素】
- 教材: 動画やテキストなどの学習コンテンツ
- LMS: 学習の進捗や成績を管理するシステム
受講者は、PCやスマホからインターネットを通じて、動画やテキストといったデジタル教材にアクセスして学びます。
一方、LMS(学習管理システム)は、誰がどこまで学習したか、テストの結果はどうだったか、といった情報を記録・管理する裏側の仕組みです。
このLMSがあるおかげで、管理者は受講者一人ひとりの状況を把握し、適切なフォローができます。
以下の記事ではオフショア開発の国別平均コストや国内開発との違いについて比較・解説しています。eラーニングシステムの開発を検討している場合は、あわせてご覧ください。
→ オフショア開発の国別の価格帯!費用を抑えるコツや国内開発との比較も解説 – トッパジャパン株式会社
eラーニングを導入することの目的
企業がeラーニングを導入する目的は、研修の「効率化」と「質の向上」を両立させることにあります。
【eラーニング導入の主な目的】
- 時間や場所に縛られない柔軟な学習環境
- 研修コストの削減と業務との両立
- 全社で均一な水準の教育を提供
- 学習データに基づいたきめ細かな人材育成
いつでもどこでも学べる環境を提供することで、忙しい社員でも自分のペースでスキルアップに取り組めます。
また、優れた講師が作った質の高い教材を全員が利用できるため、講師による教え方のバラつきをなくし、教育レベルを均一に保てるのも大きなメリットです。
また、以下の記事では教育DXの活用事例やメリット・デメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育DXをAI活用で加速!教育現場での活用事例やメリット・デメリットを解説
オンライン研修やWebセミナーとの違い
eラーニングとよく似た言葉に「オンライン研修」や「Webセミナー」がありますが、それぞれ学習の形式に違いがあります。
一番の違いは、リアルタイムかオンデマンドか、という点です。
オンライン研修やWebセミナーは決まった日時にライブ配信で行われ、その場で質問や議論ができます。一方、eラーニングは録画された教材を受講者の好きな時に学ぶスタイルです。
| 項目 | eラーニング | オンライン研修・Webセミナー |
| 学習形式 | オンデマンド(録画) | リアルタイム(ライブ) |
| 時間 | 自由(いつでも) | 指定された日時 |
| 対話性 | 低い(一方通行) | 高い(双方向) |
| メリット | 繰り返し学習しやすい | その場で質問・議論できる |
| 活用例 | 知識のインプット、反復学習 | グループワーク、質疑応答 |
一般的に、eラーニングは自分のペースでじっくり学びたい場合や復習に、オンライン研修やWebセミナーは他の参加者と対話しながら理解を深めたい場合に適しています。
また、以下の記事では教育アプリをオフショア開発するメリットについて解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育アプリをオフショア開発するメリットは?費用相場やおすすめの開発会社も紹介
eラーニングでできること
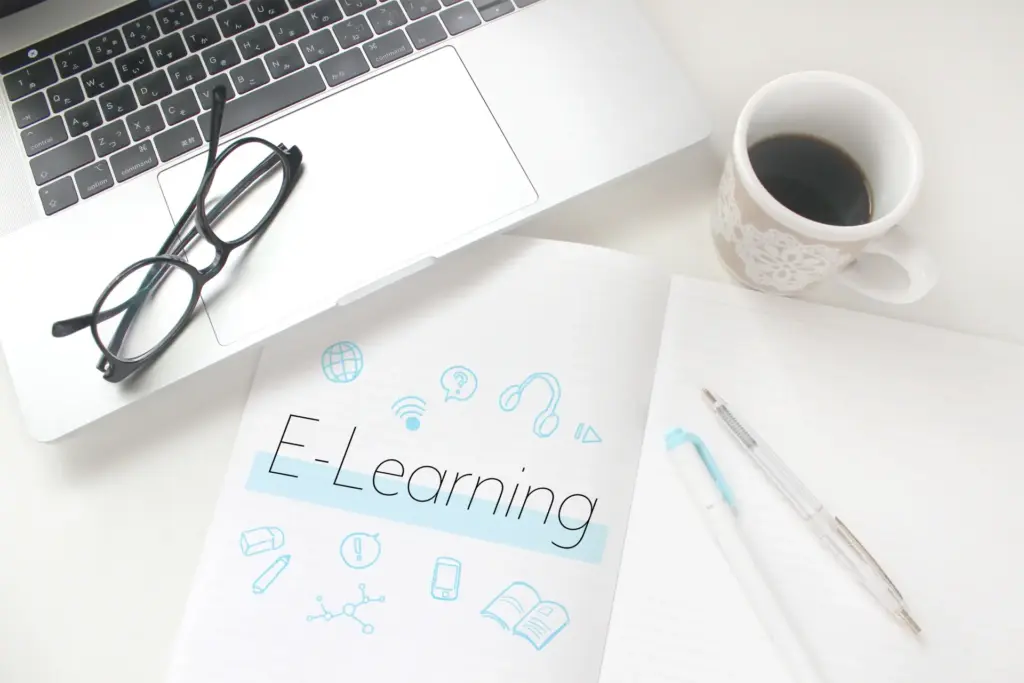
eラーニングというと、ただ動画教材を見るだけのイメージを持っている方もいるでしょう。
実は、現在のeラーニングシステムは非常に多機能で、学習効果を高めるためのさまざまな仕組みが備わっています。
この章では、eラーニングで具体的に何ができるのかを、「学習コンテンツの配信」「学習管理」「テスト・評価」「コミュニケーション」「通知・リマインド」という5つの機能に分けてご紹介します。
学習コンテンツの配信
eラーニングでできることの基本は、学習コンテンツの配信です。
【配信できるコンテンツの例】
- 動画講義やスライド資料の配信
- PDFなどの文書ファイルの配布
- スマホやタブレットでの受講
受講者は場所や時間を選ばず、自分の好きなタイミングで学習を進められます。また、理解できるまで何度も繰り返し視聴できる点もeラーニングの大きなメリットです。
学習管理
学習管理機能を使えば、受講者一人ひとりの学習状況を正確に把握できます。
【学習管理でできることの例】
- 受講者の学習進捗や成績を一覧で確認
- 未受講者や進捗が遅れている人を把握
- 学習データを分析し、人事評価などに活用
「誰が、どの講座を、いつ終えたか」といった情報が自動で記録されるため、研修担当者の管理負担は大きく減ります。
データに基づいて個別にフォローアップを行うなど、きめ細かな人材育成計画を立てるのに役立ちます。
テスト・評価
eラーニングシステムには、学習の成果を測るためのテスト・評価機能も備わっています。
【テスト・評価機能の例】
- 理解度を確認するオンラインテストの実施
- 解答の自動採点と、その場での結果表示
- テスト結果を分析し、個人の弱点を把握
研修の最後にオンラインテストを設定すれば、受講者の理解度を簡単にチェックできます。
採点はシステムが自動で行うため、講師が手作業で丸付けをする必要がありません。テスト結果を分析して、受講者ごとの苦手分野を把握することも可能です。
コミュニケーション
eラーニングでは、コミュニケーション機能を通じて交流もできます。
【コミュニケーション機能の例】
- 掲示板やチャットでの質疑応答
- フォーラム形式での非同期ディスカッション(受講者同士の意見交換)
- 講師から受講者への個別アドバイス
eラーニングでは、多くの場合、学習中に生まれた疑問を気軽に質問したり、他の受講者と意見交換したりする場が用意されています。トピック(スレッド)を立てて投稿し、他の人が返信・コメントをつけていく形式など、他の受講者や講師と時間を合わせなくてもコミュニケーションを取ることができます。
講師からも個別にフォローできるため、オンラインでありながら対面に近いサポートが期待できるでしょう。
通知・リマインド
通知・リマインド機能は、研修の受講率を高めるための便利な仕組みです。
【通知・リマインド機能の例】
- 研修の締切をメールで自動的にお知らせ
- 未受講者へ受講を促すアラートを送信
- 講師へ質問などの未対応を知らせる
システムが自動でリマインドメールを送ってくれるので、受講忘れを防ぎ、研修の完了率アップにつながります。研修担当者が一人ひとりに連絡する手間を省き、運営を効率化してくれる心強い機能です。
eラーニングは意味ない?研修に導入するメリット・デメリット

「eラーニングを導入しても、結局意味ないのでは?」そんな疑問や不安を感じていませんか。
どんな研修方法にも、良い面と注意すべき点があります。
この章では、eラーニングを研修に導入するメリットとデメリットを、「企業側」と「受講者側」それぞれの視点から解説していきます。
両方の側面を理解することで、eラーニング導入の判断や、導入後の失敗を防ぐための対策を考えるのに役立つでしょう。
企業側のメリット
企業側のメリットとして最も大きいのは、コスト削減と研修管理の効率化です。
【企業側の主なメリット】
- 研修にかかるコストを削減
- 受講者の学習状況を簡単に把握できる
- 全社員に均一で質の高い教育を提供
- 通常業務への影響を抑えて研修を実施
研修会場の費用や交通費、宿泊費などが不要になるため、研修全体のコストを圧縮できます。
また、誰がどこまで学習したかをシステムで一元管理できるので、研修担当者の負担も軽くなります。全員が同じ教材で学ぶため、教育の質にバラつきが出ない点も大きな利点でしょう。
企業側のデメリット
一方で、企業側のデメリットとしては、教材開発の負担や受講者のモチベーションの維持が挙げられます。
【企業側の主なデメリット】
- 自社で教材を作る場合、コストと時間がかかる
- 受講者のやる気に左右され、受講率が低下する可能性がある
- 学習内容が定着しにくい可能性がある
質の高い教材を自社で一から作ろうとすると、予想以上に手間と費用がかかることもあるでしょう。
また、受講者の自主性に任されるため、「いつでもできる」と後回しにされ、途中で離脱してしまうケースも考えられます。適切なフォローがないと、研修効果が上がらない恐れがあります。
受講者側のメリット
受講者側のメリットは、何といっても学習の自由度が高い点です。
【受講者側の主なメリット】
- 好きな時間・場所で学習できる
- 理解できるまで何度でも復習可能
- 動画などを使った教材で分かりやすい
インターネット環境があれば、通勤中の電車内や自宅など、自分のペースで学習を進められます。
分かりにくい部分は何度も見返すことができ、動画やアニメーションを使った教材は、文章だけの資料よりも直感的に理解しやすいと感じる人が多いのではないでしょうか。
受講者側のデメリット
しかし受講者側にも、自己管理の難しさや、他の受講者や講師との交流が減るといったデメリットがあります。
【受講者側の主なデメリット】
- モチベーションの維持が難しい
- 実技やロールプレイングには向かない
- 講師や他の受講者と交流しにくい
一人で学習するため集中力を保つのが難しく、孤独を感じることもあるかもしれません。
また、画面越しの学習が中心のため、実習やグループワークには適していません。他の受講者の質問から新たな気づきを得る、といった機会が失われがちな点も課題です。
eラーニングの学習効果を最大化するシステムの条件
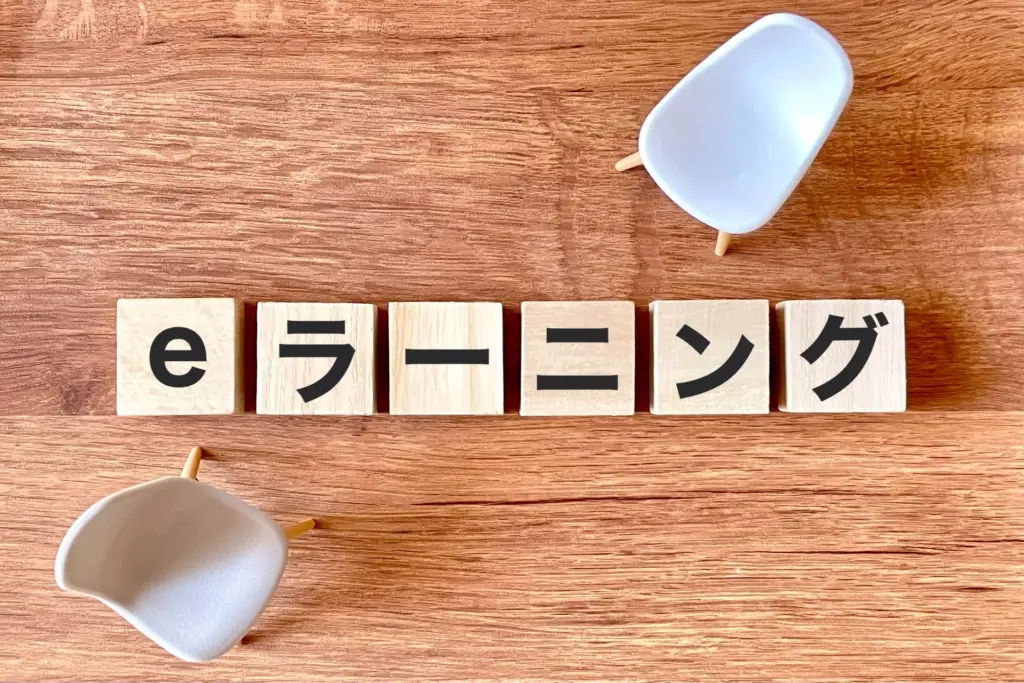
eラーニングの導入で失敗しないためには、システムの機能選びが重要です。
デメリットとして挙げた「モチベーション維持の難しさ」を克服し、学習効果を最大限に高めるには、どのような条件が必要なのでしょうか。
この章では、受講者のやる気を引き出し、学習を継続させるための2つの条件を解説します。
モチベーションを維持する仕組みを取り入れる
学習効果を最大化するには、モチベーションを維持する仕組みを取り入れることが不可欠です。
【モチベーション維持の仕組みの例】
- 学習の進捗状況をグラフなどで可視化
- 質問に対して素早く回答するサポート体制
- 学習をゲーム感覚で楽しめる工夫
eラーニングは、どうしても受講者のやる気に左右されがちです。
自分の頑張りが一目で分かるようにしたり、疑問点をすぐに解消できるサポート体制を整えたりすることで、受講者の「学び続けよう」という意欲を高めます。
オフラインでも学習できるようにする
オフラインでも学習できるようにすることも、学習効果を高める重要な条件のひとつです。
【オフライン学習機能のメリット】
- ネット環境がない場所でも学習できる
- 通信状況を気にせず集中できる
- 計画的に学習を進めやすくなる
「インターネットがないと学べない」というeラーニングの弱点を補う機能です。
事前に教材をダウンロードしておけるようにすれば、移動中の電波が悪い場所でも学習できます。通信環境に左右されることなく、スムーズな学習が可能になれば、学習を継続しやすくなり、学習効果も上がるでしょう。
また、以下の記事ではeラーニングのおすすめ開発会社について解説しています。あわせてご覧ください。
→ eラーニングシステムのおすすめの開発会社13選!選び方や費用相場も解説
eラーニングを導入するステップ

eラーニングのメリットや成功のポイントが分かったところで、次はいよいよ導入の具体的なステップです。 どのような手順で進めていけば、スムーズに導入できるのでしょうか。
この章では、eラーニングを導入するためのプロセスを、5つのステップに分けて解説します。
- STEP1:導入目的の明確化
- STEP2:受講対象者の特定
- STEP3:システムとコンテンツの選定
- STEP4:環境の準備
- STEP5:導入・運用開始
ステップに沿って計画的に進めることで、導入後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぎ、eラーニングを社内にしっかりと定着させられるでしょう。
STEP1:導入目的の明確化
STEP1は、導入目的の明確化です。
- なぜeラーニングを導入するのかをはっきりさせる
- 導入後の形骸化を防ぐ
- 達成したいゴールを設定する
まずは、「研修を効率化したい」「全社の知識レベルを統一したい」など、eラーニングを導入する目的を具体的にしましょう。
目的が曖昧なまま進めてしまうと、せっかくのシステムが使われないまま放置される、といったことになりかねません。
STEP2:受講対象者の特定
STEP2では、受講対象者を特定します。
- 誰に研修を受けてもらうかを決める
- 対象者に合った学習内容を考える
- 後の教材選びがスムーズになる
研修の対象者は、新入社員でしょうか、それとも特定の部署のメンバーでしょうか。
「誰に、どんなスキルを身につけてほしいのか」を具体的に決めることで、必要な教材がわかります。
STEP3:システムとコンテンツの選定
STEP3で、システムとコンテンツの選定を行います。
- 自社に合ったLMS(学習管理システム)を選ぶ
- 必要な機能や費用を比較検討する
- 教材は自社制作か市販品かを決める
LMSを導入すると研修管理が楽になるため、自社の目的に合ったシステムを選びましょう。教材についても、市販のコンテンツを利用するのか、自社でオリジナル教材を作るのかを検討します。
また、以下の記事では教育アプリの開発費用相場について解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育アプリの開発費用相場を解説!見積り前にやるべきことも紹介
STEP4:環境の準備
STEP4は、環境の準備です。
- ネットワーク回線やWi-Fi環境の確認
- 受講に使うPCやスマホ、タブレットの用意
- 必要なアプリのインストール
システムを導入するだけでなく、受講者がスムーズに学べる環境を整えることも大切です。
クラウド型のシステムであればインフラ面での大掛かりな準備を要しないことが一般的ですが、、必要な通信環境が整っているかは事前に確認しておきましょう。
アクセス制限やアカウント管理などセキュリティ対策なども含めるとより包括的です。
STEP5:導入・運用開始
最後のSTEP5で、いよいよ導入・運用開始となります。
- システムの動作テストを行う
- 受講者への使い方周知やマニュアル準備
- 運用開始後の改善計画を立てる
eラーニングは導入して終わりではありません。運用を始めた後も、定期的に学習状況を確認し、教材内容の見直しや改善を続けることが大切です。
また、以下の記事では教育アプリの開発会社について解説しています。あわせてご覧ください。
→ 教育アプリの開発会社おすすめランキング19選!選び方や費用相場も解説
トッパジャパンのeラーニングシステム開発
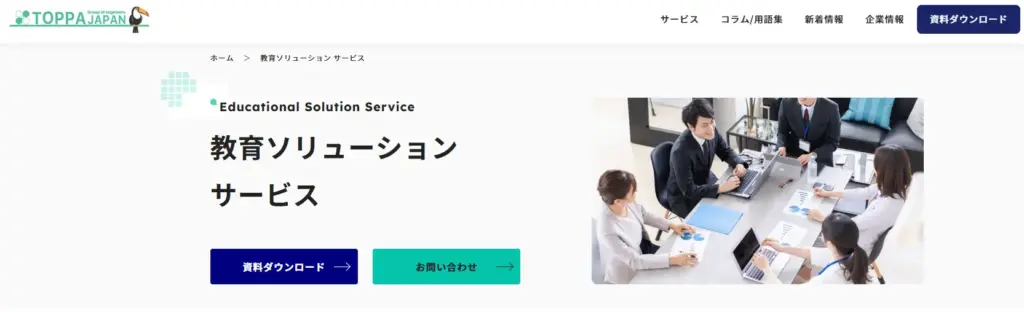
eラーニングの導入を検討する中で、「そもそも何から手をつければいいか分からない」「導入後のシステム保守やトラブル対応が心配」「セキュリティは大丈夫だろうか」といったお悩みはありませんか。
トッパジャパンはシステムを開発するだけでなく、導入前のコンサルティングから保守、ヘルプデスクまでをワンストップで支援する教育ソリューションを提供しています。
お客様の現状とゴールを丁寧にヒアリングし、最適なeラーニング環境を設計・ご提案。セキュリティを考慮したシステム構築はもちろん、導入後のサーバートラブルやメンテナンスにも、経験豊富なエンジニアが迅速に対応します。
さらに、研修担当者や受講者がシステムをしっかり活用できるよう、操作研修や活用アドバイスといった手厚いサポート体制も万全です。学校教育のICT化で培った豊富なノウハウをもとに、企業のeラーニング導入をきめ細かく支援します。まずはお気軽にご相談ください。
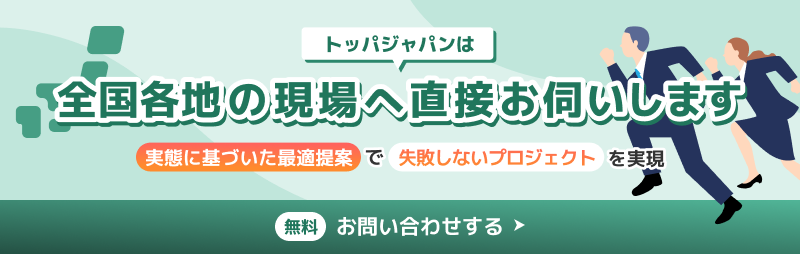
まとめ
eラーニングはコスト削減や教育の質の均一化といった多くの利点がありますが、成功させるには受講者のモチベーションをいかに維持するかがポイントとなります。
eラーニングの導入は、目的を明確にし、計画的なステップを踏むことで失敗のリスクを減らせます。
しかし、システムの選定や導入後の運用、トラブル対応など、自社だけでは不安な点も多いでしょう。
そのような場合は、導入前のコンサルティングから保守、ヘルプデスクまでをワンストップで支援するトッパジャパンに、ぜひご相談ください。
この記事の著者
- 教育系・製造業のシステム開発・AI開発に強い開発会社「トッパジャパン」。現場密着のサポート体制や、豊富な実績・経験をもとにした幅広い対応力、国内外で実績を積んだ優秀なメンバーによる高いコストパフォーマンスで、お客様のニーズにお応えしています。
関連記事
- 2026年1月5日オフショア開発オフショア開発におけるNDAの重要性|締結内容や国別の注意点を解説
- 2025年12月19日AI開発システム内製化の移行支援とは?支援内容や導入ステップ・注意点を解説
- 2025年12月11日AI開発企業がやるべきエンジニア不足の解決策10選|日本の現状や原因も解説
- 2025年12月4日AI開発【業種別】AIチャットボットの導入事例10選|導入方法や注意点を解説